一度読んですべてを頭に入れる、という発想は捨てよう。

「東京大学は読解力を非常に重視している」と昔からいわれ続けている。それは入試問題を見れば明らかだ。
国語はもちろん、1000ワード近い英文を100字程度の日本語でまとめさせる英語、問題文が長い数学。資料や文章を要約させる日本史・世界史や生物、グラフや問題文のヒントを読み解いて文にすることを求める地理、化学など、すべての科目に読解力を求める問題が出されている。読解力があれば、事前の知識をそれほど多く持っていなくても解答できてしまう問題もある。
そのため東大入試に臨む受験生は、読解力をつけようと努力する。その多くは、教科書がボロボロになるまで何度も何度も読んでいる。下の写真は過去の東大模試で1位になった東大生の教科書だ。いろいろな参考書を読み知識量を多くして対応するのではなく、1つの絶対的に信頼できる教材である教科書を、何度も読んで力をつけているのである。

では読解力とは何か。私の周囲の東大生と議論したところ、2つの力に分けられるという結論に至った。それは「読む力」と「解く力」だ。読む力とは、文章を読んで大事なポイントがどこにあるのかを探す能力のこと。解く力とは、読んだ内容を理解して要約する力のことを指す。


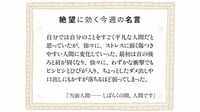






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら