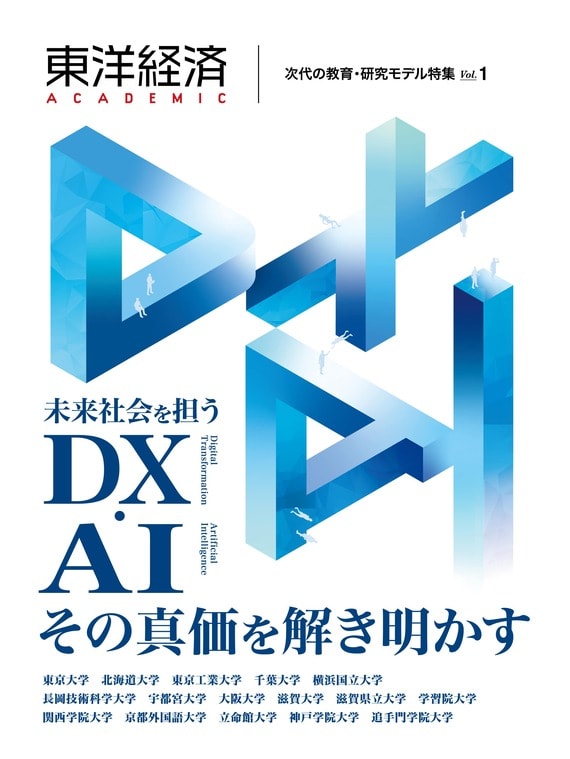同地区は全体開業に先駆けて2024年に一部開業(まちびらき)される予定であり、産学連携による新産業創出も期待される。
「関西経済連合会では、『うめきた2期地区』において、大企業のオープンイノベーション部門等が『出店(でみせ)』のように集う場の設置に向けた検討をしています。ベンチャー企業や大学・研究機関等がアイデア・課題を相談できる機会を提供し、イノベーション創出の拠点としてのまちづくりに貢献します」(香川氏)
各地区での実績を基に大阪・関西全域へと展開する
特に万博開催後は、未来都市の実現に向けてよりシビアに課題が検討されたうえで、新しい技術・仕組みが社会に実装されることが見込まれる。
「本学は『大阪大学2025日本国際博覧会推進委員会』を立ち上げ、全学的な視点で万博に対応しており、iLDiのターゲットはまさに万博のテーマ『いのち輝く未来社会のデザイン』に合致します。万博の意義は、開催中の技術展示にとどまらず、その技術をいち早く我々の社会生活に取り入れることでしょう。PLRについては、必ず個人の同意の下に収集したうえで安全・安心に活用できる仕組みづくりを進め、社会に浸透させるための素地をつくっていきます」(尾上副学長)

夢洲・うめきたでの先端的な取り組みは、やがて関西全域への拡大が望まれる。そこで広域におけるデータ活用の仕組みとして検討が深められているのが、都市オペレーティングシステム(OS)だ。
「例えば効果的な防災減災など、新しい住民サービスの提供には多岐にわたるデータ連携が不可欠です。そこで関西経済連合会では、2019年度から都市OSワーキングを継続的に開催しています。大阪大学サイバーメディアセンター長の下條真司教授を座長として、企業や大学、大阪府・市など32団体が集まりさまざまなテーマを議論し、大阪府下での都市OS構築に向けた検討を産官学が連携して進めています」(香川氏)
未来都市への変貌を遂げるには、産官学連携によって多方面からの検討と実践を積み重ねることが望まれる。大阪・関西が先端的な事例となれば、他地域に展開されて日本各地に未来都市が見られる日も遠くないだろう。
東洋経済ACADEMIC
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら