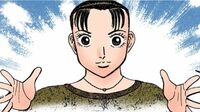女子新御三家、鷗友が「最高級幕の内弁当」の訳 勉強以外の経験も超重視で主体性と胆力を育む

学校生活のすべてを深く味わう「幕の内弁当」を目指して
東京の私立「女子御三家」といえば桜蔭と女子学院、そして雙葉だが、近年では「新御三家」が台頭し、元祖御三家の牙城を切り崩すほどの成長を見せている。
豊島岡と吉祥女子とともに、この新御三家を成しているのが、1935年に創設された鷗友学園だ。初代校長である市川源三氏の「女性である前にまず一人の人間であれ」という理念を守りながら、時代に即した教育を実現すべく、80年代後期から2010年にかけて学校改革を実施してきた。校長の大井正智氏は、同校の学びを「幕の内弁当」に例える。
「たくさんのおかずが入っていて、そのどれにも栄養がある幕の内弁当が理想です。うな重やとんかつ弁当のような1つのおかずで一点豪華主義を目指すような方針ではありません。学校で経験するすべての活動を通して成長を目指しています」
そうそうたる大学の合格実績から、「たくさんのおかず」は主要5科のバランスのことを指しているのかと思いきや、そうではない。あくまで英語や数学などの勉強は多様な食材のうちの1つで、芸術や園芸のほか部活動や委員会、イベント、生徒同士のコミュニケーションなども重視している。その一つひとつに最高級の食材を使っているイメージだと大井氏は説明する。取り組みの具体例を挙げてもらうと、その多彩さに驚く。
「鷗友学園のイベントは生徒が主体になって行われており、体育祭の審判や裏方も生徒自らが担当します。体育祭当日、校庭には司会を務める生徒の声が響いていますよ。また、コロナ禍でオンライン開催となった21年の学園祭では、生徒がサイバーチームを組み、専用ホームページを立ち上げて運営しました。この経験をきっかけに、情報系の学科に進もうと決めた生徒もいます」

鷗友学園女子中学高等学校 校長
(撮影:吉濱篤志)
中学で沖縄、高校で京都と奈良へ行く修学旅行も、生徒の主体性が伝わる行事だ。
「事前学習にとても熱心に取り組み、『日本一仏像に詳しい女子高生』を自称するまでになった生徒がいます。中学の修学旅行では、医学部を志望していた生徒が沖縄の地で心を打たれ、のちに琉球大学の医学部に進学した例もありました」
一方、創立当初から続く園芸は、鷗友ならではの学びといっていいだろう。これは中1で週2時間、高1で週1時間、全員が学ぶ必修科目だ。校内にある園芸実習園で一人ひとりに小さな畑が与えられ、そこで各自が野菜や花を育てる。
ホームルームで行う米国発のコミュニケーション手法「アサーショントレーニング」も特徴的だ。葛藤が生じるシーンを想定し、専任のトレーナーの指導の下、互いに配慮しながらも率直な意見を伝え合うことを学ぶ。これは中学1・2年生を対象としたものだが、6年間を通して3日に1回席替えを行うという同校の珍しい取り組みは、さまざまな生徒との関わりを増やし、コミュニケーションスキルを磨くためのものでもある。
「授業でも席ごとのグループワークが多いので、頻繁に席替えをすることで、より多くの生徒と交流できるようになります。休み時間などでも、女子はあまり移動せずに周囲の生徒とおしゃべりする傾向がありますが、席替えによってその相手も多彩になります」