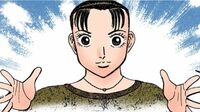女子新御三家、鷗友が「最高級幕の内弁当」の訳 勉強以外の経験も超重視で主体性と胆力を育む
大井氏は、あるOGに「鷗友学園はどんな学校だったか」と尋ねたことがあるそうだ。
「その卒業生は『学校は人と話す場所だと感じていた』と話してくれました。いろんな意見を聞いて、自分の意見も言う所だと。『黙っている子がいると心配になっちゃう』とも話しており、伸び伸びと過ごしていたのだなとうれしくなりました」

「自ら考える人に育てたい」入試も〇×式の訓練では駄目
入試にも鷗友学園の学びの姿勢が表れている。
「本校の入試は記述式の問題が多く、算数などでは計算の過程にも部分点を与えます。知識を詰め込み、一問一答形式の問題しかやってこなかったお子さんは戸惑ってしまうと思いますが、自分で理解して順を追って考えれば解けるはず。そうした練習をたくさんしてきてほしいと考えています」
見せてもらった実際の答案用紙は、一つひとつの解答欄がとても大きいものだった。「40字以内で答えなさい」などという設問や、算数でも途中式や考え方も含めて書かせる形式の問題が多くを占める。詰め込んだだけの知識では到底答えられるものではなく、問題を丁寧に読み込むことはもちろん、自分の言葉で論理的にまとめる力なども求められる。中途半端な対策では太刀打ちできないが、鷗友ではこうした記述式のほうがチャンスを広げると考えているようだ。
「人間は〇と×で分けられるものではなく、大人だって間違えるものです。いわば人間自体が△の存在。だから本校の入試は〇か×かという問題だけではなく、△をたくさん積み上げて得点していくことになります」
「ケアレスミスも実力のうち」ともいわれるが、大井氏はこの言葉に異を唱える。鷗友では最終的な答えが合っていなくても、算数は途中式や補助線、国語でも考え方が合っていれば部分点を与えている。
記述の多い独特な入試に個別の対策が必要になることも相まって、偏差値や倍率の上昇とともに、鷗友学園を第1志望にする家庭が増えているという。近年は2月1日・2月3日の両方の入試日程に出願するケースが多く、2021年度の入試では2回目試験の合格者のうち、実に35%が1回目の試験で不合格になった受験生だった。
受験生とその家庭の「受かった学校にではなく、鷗友学園に入りたい」という意志を感じさせる結果だ。
「本校はつねに生徒を中心に、生徒主体の学びを提供しています。入学してからは、自ら考えて発信する機会がとても多くなるでしょう。入試の時点でも、自分がどこまで理解できたかをしっかりと書いて発信してほしい。そうしたことが苦でない子、新しい知識を得ることに喜びを感じられる子なら、本校でも楽しく学んでいけるはずです」
共学では得がたい幅広い経験が、未来の選択肢を増やす
すべての行事を重視する鷗友学園だが、もちろん学生の本分である勉強もおろそかにしない。ただ、授業の中身もユニークなものが多い。教員がただ教えるのではなく、どの教科にも生徒自身が主体的に学ぶようになる仕掛けがある。
「例えば生物ではカエルの解剖を行いますが、目的を考えるところから始めて、1カ月という長い時間をかけて発表までまとめます。『この1つの命を使って、あなたは何を学びますか』と、課題設定も生徒自身に委ねています」
新しい学習指導要領では、主体的・対話的で深い学び、いわゆるアクティブラーニングが重視されているが、そんな言葉が定着する前からずっと鷗友はその姿勢を貫いてきたわけだ。そのため、高校で「総合的な探究の時間」が新たに追加されると聞いたときも、とくに慌てることはなかったという。