「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 上智大学が教える「真の語学力と教養」とは?

コロナ禍でオンラインの学びが世界を広げた
――コロナ禍で海外との往来も制限され、国内でグローバル化が感じにくくなったとの声があります。

言語教育研究センター
教授/センター長
藤田 保氏
藤田 日本人の海外への関心が薄れ、“内向き傾向”にあるというのは、コロナ前から言われてきました。コロナで海外との往来も途切れ、さらにその傾向に拍車がかかってしまった印象です。
一方で、この期間にオンラインでの学びが一般化しました。それによって国内にいながら海外の講座を受けられたり、異なる国にいながら意見交換ができたりなど、外とつながりやすい環境が出来上がってきましたね。
その意味ではグローバルな事象に関心を持つ人とそうでない人の間

カントリーマネージャー
根本 斉氏
根本 確かにコロナ前から日本人の内向き傾向はありましたが、世界に目を向けると学生の流動性は高まっています。海外で学ぶと母国でのキャリアアップや社会貢献につながることが周知されて、アジアの学生を中心に、海外で学ぶことが一般化しています。
海外での学びがさらに広がる中で必要なのは、やはり共通言語である英語です。私たちETSはテスト会場受験型のTOEFL®テストに加えて、昨年から自宅でも受験できる「TOEFL iBT® Home Edition」の提供を開始しました。コロナ禍でも英語学習への意識は落ちていないと感じています。
大人こそ英語学習法のアップデートが必要
――近年の日本教育における英語学習の課題は、何でしょうか?
藤田 今の大学生や新社会人は、小学校から外国語の授業を受けている世代。大学で教えていても、意見を述べたり発表したりと英語でコミュニケーションを行うことに対して、学生の抵抗が減ってきているのを感じます。
そういった意味で、英語学習に関するアップデートが最も必要なのは、私たち大人なんです。
私たちが学生時代に学んできた英語は、単語の暗記や文章を翻訳することが中心でした。しかし、今はコミュニケーション中心の学びになっています。教科科目(content)の学習と外国語(language)の学習を組み合わせた「CLIL=内容言語統合型学習(Content and Language Integrated Learning)」が主となりつつあります。ただ英語を話せるということより、新聞などを読んで理解した問題について議論し、解決のために他者と協働する英語です。TOEFL®テストでも、リーディングやリスニングをし、スピーキングで解答するなどの形式も増え、技能統合型になってきていますよね。
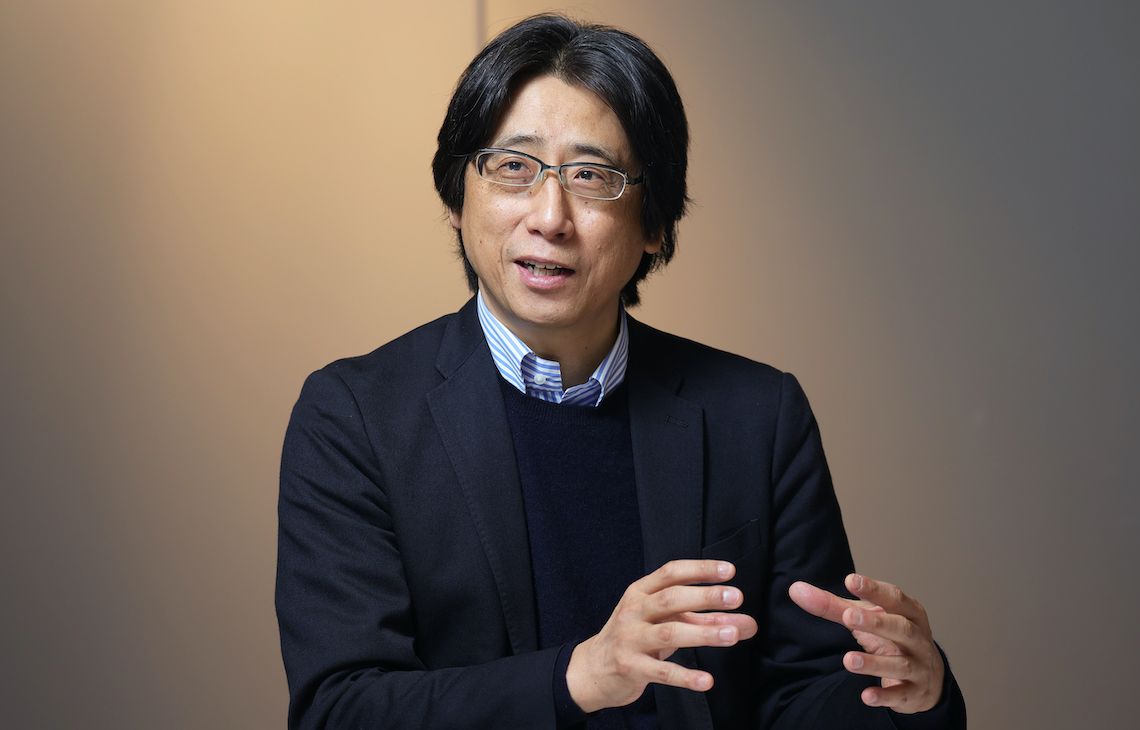
根本 世界における英語を学ぶ目標がこれまでと変わってきていますね。「なぜ英語を勉強するのか」という根本的な問いに立ち返るときが来ています。ただ、海外の人と交流したい、旅行がしたい、という目的ももちろんあっていいです。
しかし、このVUCAといわれる変化の多い時代において、つねに学びをアップデートし続けられる生涯学習者であることが、何よりも強みとなります。例えばテクノロジーや経営学の分野では、最新情報の日本語訳を待っていると非常に不利です。昔はある本や論文が出たら翻訳されてから読んで勉強していましたが、今はそのスピードだと最新の議論に追いつけない。やはり英語「で」理解するという能力が必要になってきていると思います。
これからの時代、学び続けられる人間でいなければ、自分たちの社会や未来をよい方向に変えていくのは難しいのです。学ぶための英語は、その生涯学習の1つのツールとして欠かせません。
AI翻訳に人間が勝る思考力と背景理解力
――高精度なAI自動翻訳ツールが広まり、英語学習不要論も出ています。
藤田 使えるものは手助けとしてどんどん使えばいいと私は思っています。AIや翻訳ツールの進化は目覚ましく、マニュアル的な技術文章はとりあえずAIでできてしまうでしょう。
しかし、交渉ごと、ニュアンスを伝える、行間を読んで議論をする、というようなことは、まだAIには任せられません。
言語は、思考するツールでもあります。その言語の背景となる文化や思考法を理解して話す必要があります。複数の言語を話せるということは、それだけの思考法を体得しているということでもあり、物事に対して複眼的な捉え方ができるのです。
根本 私は外資系企業の管理職という立場でもあり、日々グローバルでの会議に参加しています。共通言語はもちろん英語ですが、さまざまな国の人がいる中で、相手のカルチャー、人間性、立場を理解したうえで自分の意見を伝えることが求められます。
残念ながら現在のグローバル企業において日本人の管理職が少ないのは、語学力に加えて多様性や異文化を理解したうえで交渉できる人が少ないからでしょう。AIは補助的に使うには便利ですが、英語を一から学び、文化も含めて体得してこそ、本当に大切なコミュニケーションができると考えています。

懇親会で仕事以外の話で盛り上がれるか?
――改めて、今こそ子どもからビジネスパーソンまで身に付けていきたい語学力、人間力とはどんな力でしょうか?
根本 国際的な舞台で仕事をしていくためには、専門知識があることの証明が必要です。その1つがTOEFL®テストをはじめとする語学テストですが、TOEFL®テストはよく「傾向が読みづらくて対策しにくい」といわれます。それは、問題集で対策できるマニュアル的な問題だけでなく、自分の専門や仕事以外の話題でも話ができる教養や、統合的な力を必要とする問題だからです。
海外とのビジネスでは、実は交渉や会議の場と併せ、その前後の食事やちょっとした会話の場で関係を築けるかも重要になります。懇親会が苦手という日本人は多いですが、そうした場で怖がらずに話せる教養力は、自分自身にとってもさまざまな扉を開いてくれるはずです。語学力と国際的な教養力は、グローバルな人材に必要不可欠だと思います。
藤田 上智大学の教育の精神に「他者のために、他者とともに」という言葉があります。多様な人々と協働しながらこれからの社会をつくる人材を育てるためには、英語教育はもちろん、相互理解の基盤となる教養を育てることが重要です。
多くの国・地域における文化背景などの教養を身に付けるためにも、上智では「複言語主義」を取り、英語と日本語以外に20の言語を学べるようにしています。英語も教養も、テストでいい点を取るためのものではなく、さまざまな言語や文化を身に付け、心を豊かにするもの。言語学習を通じて、グローバル人材に必要な思考ツール、教養を習得してほしいですね。




 「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値
「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?
「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」
国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術
AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由
今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳
「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設
GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方
組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び
上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは
上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは
「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像
上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由
日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意
「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道
産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは
ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由
上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは
元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」
国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い
データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義
あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う
「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」
マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由
経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?
人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?
国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦
コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性
上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」
国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」
スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」
上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?
上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立
日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由
事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質
上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい
「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩
上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

