元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際公務員という「転職の選択肢」を考える

国際機関は「働いたことに悔いがない」と思える職場
――茶木さんは国連、玉内さんはユニセフと世界保健機関(WHO)で働かれていました。どのような仕事をされていたのでしょうか?

元国連人事官
国際基督教大学卒。同大学で国際法の修士号、アメリカン大学で法学修士号を取得後、国際基督教大学に戻り国際法の博士号を取得。88年よりニューヨークの国連本部人事部に勤務し、97年から2年間ジャマイカの国際海底機構に勤める。その後国連本部人事部に戻り、2006年から “Umoja”(統合業務システム)の開発に尽力
茶木 私は大学で法学修士号、大学院で国際法の博士号を取得後、国連が実施している競争試験に合格して法務官として採用され、最初は国連本部の人事部で人事規則の解釈や改訂の起案、運用のアドバイスをするセクションに赴任しました。5年ほどそこで働いた後は実際に人事規則を運用している現場を見てみたいと、職員の待遇や採用、労使関係を扱う仕事に移動しました。その後は、人事部内で移動しながらさまざまな人事行政に従事しました。
玉内 WHOでは人材育成担当官として働きました。私は、外資系投資銀行で人事・総務の仕事からキャリアをスタートしており、その後シリコンバレーの米国コンサルファームで日米企業の合併交渉や外資系ホテルグループで人材育成に従事しました。私がWHOの人材育成担当官に応募したときは、ちょうど民間企業の評価や人材開発の方法を参考に組織改革をしていたころなので、求める人材にマッチしていたのだと思います。ユニセフでも人事部で人材の発掘や育成のプログラムの設計に取り組みました。
――人事に関わる仕事をされていたお2人、そして国際機関で豊富なキャリアを積まれている植木教授が考える、国際機関で働く魅力について教えてください。
茶木 国連の目的や、普遍的価値の実現に微力ながらも貢献できるところです。実質的(Substantive)な仕事をしている方はもちろんそうですが、人事などのサポート業務でも国連の任務や発展に間接的に貢献することができると考えています。例えば、私が担当した仕事の1つに、統合業務システムの開発・実現がありました。自前のシステムから既成のシステムを導入するプロジェクトでしたが、コンピューターシステムの刷新だけでなく、国連の古い業務形態を一新し、例えばセルフサービスを導入し効率化を図るというような根本的な改革を伴うものでした。こういう仕事に関わることによって、国連行政の改革や発展に寄与することができ、間接的には国連の目的や使命の達成に関わったといえると思います。パーソナルなレベルでは多様性や個性が認められており、「人と同じことをしなくてよい」というのが当たり前だったので、とても働きやすかったです。

元ユニセフ人事官
ハンボルト州立大学およびベルビュー大学院卒。専門は異文化間コミュニケーションと国際組織管理学。外資系企業で人事・総務や国際企業研修に携わった後、95年からハワイのシェラトンホテルグループにて国際人材育成ディレクター。2000年よりフィリピンのWHO地域事務局、ユニセフ・インドネシアにて人事官。2005~2016年までは国連事務局人事官、ユニセフNY本部人事マネージャー、ユニセフインド事務所人事チーフ等を歴任
玉内 私も茶木さんと同じで、多様性の中で自分の専門性を生かして働くところに醍醐味を感じていました。日本企業はメンバーシップ型が主流ですが、国際機関は専門性と経験、スキルを重視するジョブ型の職場なので、自分の専門性がはっきりしている場合は、大いに活躍できると思います。また、平和構築・貧困撲滅・ジェンダー平等などの実現に尽力したいという強い志を持つ仲間と一緒に、地球規模の問題に取り組み、インパクトのあるアクションを起こせることは、何よりの醍醐味です。
植木 国際機関は、国際社会が直面するグローバルな課題を解決するための組織なので、毎日のように多種多様な課題が飛び込んできます。そうした大きな課題に向き合い、自分の強みを生かして果敢に挑戦できるので、非常にやりがいがあります。日本人初のユニセフ事務局次長を務めた丹羽敏之さんが、著書『生まれ変わっても国連 国連36年の真実』を書かれていますが、タイトルからもわかるとおり国際機関は「働いたことに悔いを感じない職場」だといえると思います。
職場環境のよさや待遇面も「世界基準」
――職場としての働きやすさや待遇面の魅力については、いかがでしょうか?
茶木 ワーク・ライフ・バランスの観点からすると、とても働きやすかったです。私は通常19時までに帰宅できましたし、どんなに多忙でも21時を超えて仕事をすることはほとんどありませんでした。健康保険や有給休暇、病気休暇など社会保障も充実しています。とくに子供を持つ親には優しい職場で、子供の病気や学校の行事に由来する時短・早退などには寛容で、柔軟な働き方ができると思います。給与については、ずば抜けて高水準かと言うと、そうではないかもしれませんが、十分なレベルだと思います。

国際協力人材育成センター所長 大学院グローバル・スタディーズ研究科 教授
上智大学卒。米コロンビア大学で修士号、博士号を取得。82年より国連事務局広報局、92~94年日本政府国連代表部(政務班)、94~99年国連事務総長報道官室、99年~広報局に勤務。2014年4月より上智大学にて教鞭を執る
玉内 私は母の介護と子育てを両立しながら国際機関で働いていました。母の介護を私がメインで担う必要があったのですが、その時は母のビザも出してくれました。途上国で働く場合は、育児や介護をサポートしてくれるスタッフ(ハウスホールドチーム)の協力を得られるので、私のような働く女性にとっては非常に心強かったです。また、ユニセフはブレストフィーディング(母乳育児)を推奨しているだけあって、オフィスにも授乳室が完備されていたりするので、仕事の合間に授乳をすることは当たり前の光景でしたね。
植木 国連に勤める国際公務員の給与は、加盟国の中で最も高給な国家公務員(現在まで米国)の給与体系を参考にして設定する「ノーブルメイヤー原則」に基づいて決定されます。そのため、収入面で困ることはないと考えて差し支えないでしょう。また、国連は各国に拠点がありますが、比較的安全な都市には家族を帯同できます。私の場合は、ニューヨークの国連本部に勤務をしており、中東やアジアなど各国を出張の形で飛び回っていましたが、家族はニューヨークにいました。勤務形態については、状況に応じてさまざまな選択肢があるので、それほど心配する必要はないと思います。
国際機関が求める「専門性を持った人材」とは
――国際機関で働く上で、身につけておくべきスキル・経験について教えてください。
茶木 必要条件としては、英語を使って仕事ができることですね。読み・書き・表現のいずれにおいても、英語で「自分の言いたいことを過不足なく」伝えられるスキルは必須です。そしてもう一つ必要なのは専門性です。国連は基本的に中途採用で専門知識と経験をすでに持っている即戦力を求めています。さらに、さまざまな国籍、文化を持つ人と働くので相手のことを思いやれる能力も必要です。面接官に「この人と一緒に働きたい」と思わせるような人間性を持つ人が求められています。
植木 アフリカやアジアなど多様な国の人が英語を使うので、完璧な英語ではなくても大丈夫です。国連では自分の考えをしっかりと出して、積極的に議論に加わることが大事になるので、4技能を活用して議論できるレベルであれば問題ありません。あとは、専門性についても茶木さんがおっしゃるとおりで、国連というのは大きな組織なので、会計・IT・財務・広報などあらゆる職種を募集しています。中には、民間企業でロジスティクスの仕事を経て、50代で国際機関の物流部門で採用された方も。国際機関で働くために有利な経験やスキルは1つではなく、いろいろな可能性があります。
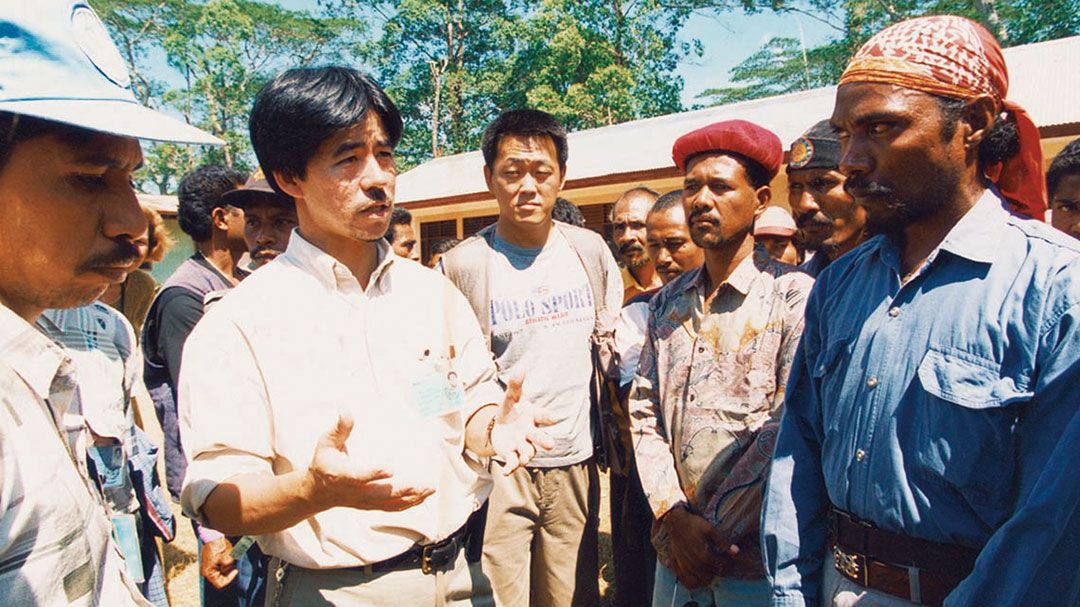
玉内 私がとくに大切だと思うのは「自己認識力」です。国際機関は専門家集団ということで、実績や結果を出すことが重視されます。そのため、自分の強みや意志、専門性・業績は何なのかをきちんと把握しておく必要があります。経験とスキルの棚卸しをして、「国連で使えるスキル・経験」があるかどうか洗い出してみるとよいでしょう。また、異なる文化的背景を持つ人たちと働くので、卓越したコミュニケーション能力を持つことは大切です。
植木 あとは自分の評判をコントロールするスキルはとても大事ですね。数年ごとにポジションチェンジの機会があるのですが、周りの同僚や上司のサポートが重要なので、その意味でもレピュテーションマネジメントは、ステップアップに欠かせないポイントかもしれません。また、与えられた仕事だけではなく、新しいアイデアを積極的に出すことも求められているので、前のめりに仕事をする姿勢が評価につながります。
――上智大学が注力する国際公務員の養成について、具体的な取り組みやどういった講座を展開したいか、お考えを聞かせてください。
植木 年2回の国連Weeksでは、国連の活動をテーマにさまざまなイベントや講演を行っていますが、国際機関でのキャリアを考えるセッションが毎回好評です。また、学生・一般人を対象にした「国際公務員養成コース」も、多種多様な業界から受講者が集います。ライティングを中心に、国際機関で働くうえで必要な英語の使い方や書き方について学ぶ英語コース、国際公務員試験を想定した養成コース、バンコク研修コース、人道支援講座の5つの講座を開講しています。
後者では茶木さんや玉内さんをはじめ、さまざまな国際機関で働いた経験を持つ講師が、待遇、働きがい、履歴書の書き方などを指導します。ほかにも、2021年4月に開設した大学院修士課程の「グローバル・スタディーズ研究科 国際協力学専攻」は、国際機関を目指す社会人に対して、即戦力となるような実践的なカリキュラムを提供しています。
茶木 若い学生や社会人は、国連で働きたいと思ったとしても、周りにモデルがなければ、どうやって国際公務員になればいいか具体的なイメージがわからないと思います。私が講師をしている養成コースでは、受講者にどうしたら国際機関で働けるかという具体的なイメージを持ってもらう事を目的の一つにしていたいと思っています。あまり一般的ではない国際公務員という仕事の選択肢を提示し、受講者がキャリアの選択肢に国際公務員を加えてくれるとうれしいですね。国際公務員になる道は1つではないので、意思があれば道は開けてくると思います。その前に、まずは「国際公務員が自分のやりたいことなのか」をしっかり見極めてほしいです。
玉内 私は面接時のスキルを上げるお手伝いをします。日本人はどうしても「WE」に重きを置きがちなので、個人としてどのような考えや志を持っているのか、意識して伝える方法をお話ししたいです。また、選考に必須の英文履歴書も作成のコツがあるので、伝わりやすい書き方など実践的なことも教えたいです。そのほかにも、キャリアだけでなくあらゆるライフイベントに寄り添ってくれるステキな職場だということも伝えることで、国際公務員という選択肢を目指す方が1人でも増えてくれるとうれしいですね。
上智大学国連Weeksは10月11日から26日まで開催。18日には国際機関・国際協力分野で働くことに関心のある方を対象としたキャリアセッションも。



 「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値
「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?
「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」
国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術
AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由
今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳
「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設
GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方
組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び
上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは
上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは
「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像
上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由
日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意
「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道
産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは
ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由
上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」
国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い
データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義
あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ
「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う
「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」
マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由
経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?
人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?
国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦
コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性
上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」
国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」
スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」
上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?
上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立
日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由
事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質
上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい
「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩
上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

