ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 「人材戦略の変革期」企業と大学が進むべき道
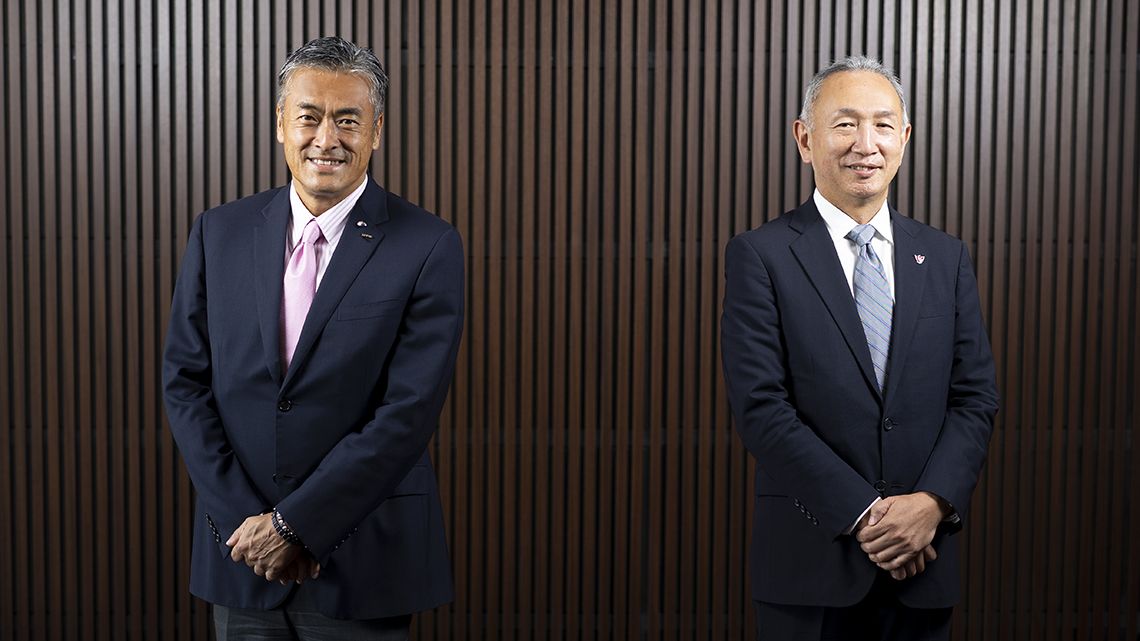
企業の変革を加速させる人材の「質的な多様性」
――現在、VUCA時代の到来で多くの企業は変革を急いでいます。ビジネスの環境変化が激しい今、どのような人材が求められていると考えていますか?
玉塚 「柔軟な発想力」「物事の本質を捉える力」「リスクがあっても飛び込める力」を持つ人材がたくさん必要だと思います。今の日本は産業構造が硬直化しており、既得権益でがんじがらめになっています。しかし、ここ数年でAIやブロックチェーンなど、新しいテクノロジーが続々と出現してきました。すでに一部の産業では大変革を迫られていますが、おそらく今後10年くらいでどの分野でも、旧態依然とした構造を変えざるをえない局面がやってくるはずです。
今ほど、面白い時代はないともいえる。それを念頭に置いたとき、臆せずに新たなステージを選び取れる人材は強いですよね。
曄道 おっしゃるとおり、主体的に人生の多様なステージを並行・移行する、いわゆる「マルチステージ」を自分自身でデザインできる人材の育成が、大学教育にも求められていると感じます。企業にキャリアパスを委ねるのではなく、学び直し、副業、ボランティアといった多様な選択肢から、自らの個性や専門性を生かせるステージをデザインできる力を持つ人が、企業や社会にも必要な時代に変化していると思います。

代表取締役社長
玉塚 元一氏
玉塚 加えて、人材の「質的な多様性」も重要ですね。例えば大学を卒業後、最初はNPO法人に入職して社会課題の解決に取り組んできた人が、今度はまったく異なるデジタル分野で前職の知識・スキルを生かしながら新しい事業にチャレンジする。こうした多様な経験やキャリアを持つ人材が企業の内部に増え、それぞれが意見を交わしアクションを起こすことが、イノベーションにつながるはずです。
曄道 確かに受け身ではなく、自ら課題を見つけて未来を展望できる人材の育成は急務といえます。上智大学では2022年度にすべての1年生から4年生が履修する共通科目を刷新し、学生が自ら学びをデザインする新たなカリキュラムを作りました。先々に起こりうる変化に対応するためには、自らの置かれた環境を俯瞰的に捉え、自律的に物事を学ぶ訓練が要ります。現状の経済社会が抱える課題を理解し、「これからの時代に生き残れる組織」を見極められる人材を送り出すため、まずは大学教育のあり方を率先して変えなければいけないと考えています。
「自分とは遠い世界」が、好奇心を刺激する
――変わらなくてはと自覚しつつも、何をするべきか悩むビジネスパーソンは少なくありません。不確実性の高まる時代においても活躍し続けるためには、どのようなマインドが必要でしょうか。
玉塚 つねにアンテナを立て、物事に興味を持ち、行動することだと思います。今だとWeb3やDAO(分散型自律組織)が話題ですが、それらが求められている背景に興味を持ち、自分なりに仮説を立て、詳しい人とディスカッションしてみるのもいいでしょう。または、所属している企業だけにコミュニティを限定するのではなく、数人の仲間と一緒にスモールビジネスにトライしてみるのもいいでしょう。いずれにしても、突き詰めると「好奇心を持ち続けること」が必要ではないでしょうか。
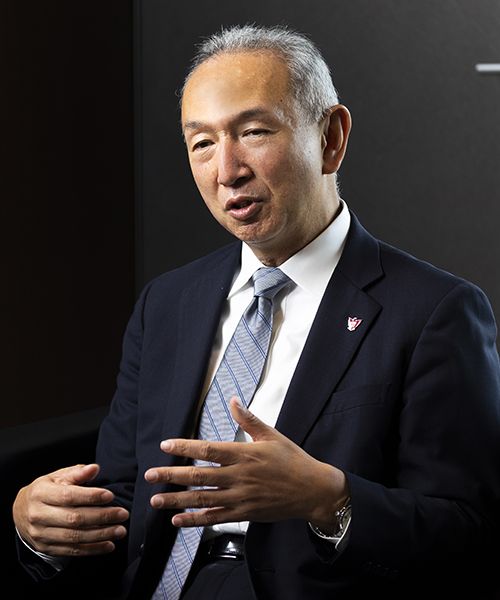
学長
曄道 佳明氏
曄道 その好奇心を喚起するにはどうすればよいか。私は、「自分にとっていちばん遠いと感じるものや、自分の置かれた世界とは真逆の世界に目を向けること」だと思います。それによって感受性が揺さぶられ、好奇心を抱くきっかけになるはずです。
玉塚 確かに、僕もアメリカの大学に留学したとき、アントレプレナーに出会ったことが経営に興味を持つきっかけになりました。時価総額数千億の企業経営者がTシャツにジーンズというラフな格好でプレゼンし、学生からのどんな質問にも真摯かつ正確に答えてくれたんです。日本ではアントレプレナーという存在がまだまだ珍しい時代でしたから、すごく大きな刺激を受けました。
企業×大学のシナジーで人材を育成
――これからの時代に活躍できる人材を育成するうえで、企業に必要なことは何でしょうか。
玉塚 1つは人材への投資です。例えば、ロッテグループは現在バイオやEV電池の素材事業など、日韓で連携して新事業に取り組んでいます。そのために必要なのがリーダーシップ人材です。そこで、1年前にロッテ大学を立ち上げて、幹部候補生を40人ほど選出し、企業経営者とのディスカッションや、マーケティング講座などを展開しています。社内の人材にどれだけ投資し、育成できるかというのは企業の持続的な発展において重要なポイントになるでしょう。
また、社会全体では、デジタル関連の教育をはじめ「リスキリング(学び直し)」が必要です。人口減少の中、縮小する産業に人材が張り付いていては大きな損失となりかねません。産業の新陳代謝と人材の流動性を高めるためにも、国・産業・教育機関が三位一体となって、成長産業に人材がシフトできる仕組みづくりに取り組まなくてはいけないと思います。
曄道 リスキリングという文脈では、上智大学では社会人向けの講座「プロフェッショナル・スタディーズ」を開設し、国際通用性のある教養をテーマに多様な講座を提供しています。ここでは、スキルの習得一辺倒ではなく、「1つの題材からどのような発想を得るのか」という根源的なことを学ぶ場を用意したいと考えています。「すぐに仕事に役立つ何か」を得られるわけではありませんが、われわれは「こんな考え方があるのか」という発見を得られる場を提供したいと思っています。
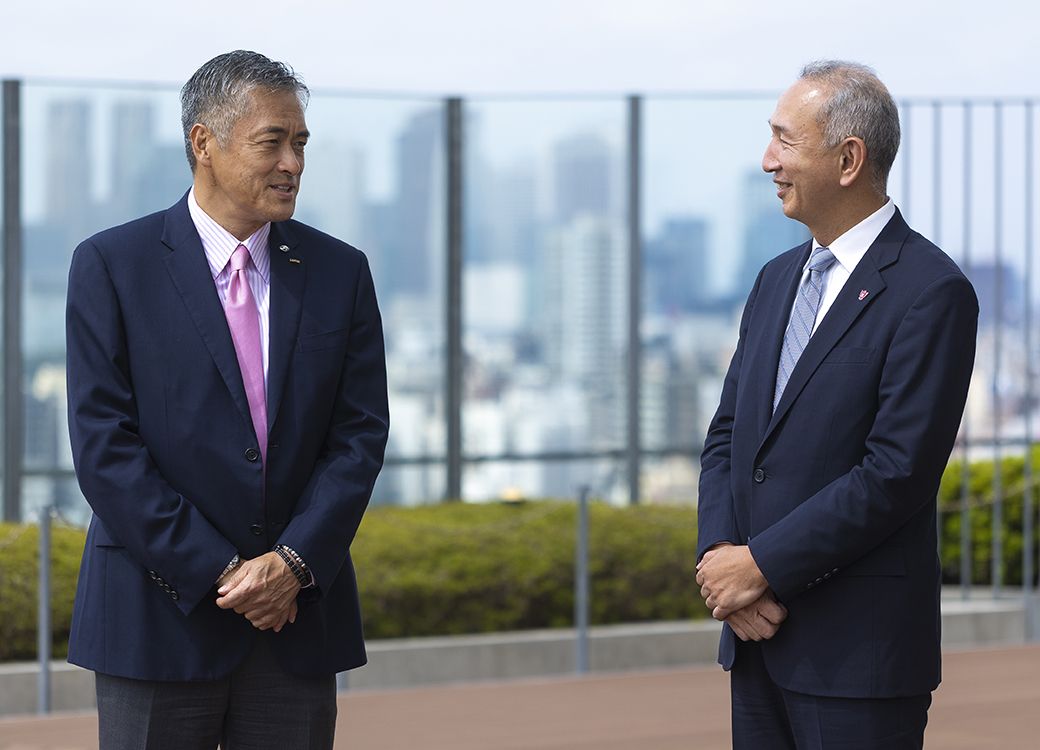
玉塚 根源的な学びが重要だと思っているので、とても意義深い講座だと感じます。企業、国や自治体、NPOなどの組織は、あくまでも「社会的な課題解決」のためにある集団です。まずは、自分の感受性で課題を認識し、その解決のために仮説を出し、速やかにアクションに移すためにどのフィールドに身を置けばいいかを考えなくてはいけませんし、企業もそれを考えられる人に来てほしい。そのためには、産業界と教育機関がお互いにリソースを出し合って、新しいタイプの学びの場をつくれるといいですね。
曄道 まさに、「プロフェッショナル・スタディーズ」は産業界とのコラボレーションで講座を構築しています。具体的には、会員企業の人事部門の方の協力を得ながら、これからの社会人教育がどうあるべきか議論し、講座内容をブラッシュアップしています。もちろん大学の教員も講座に携わりますが、ビジネスの現場を理解している産業界の皆さんとパイロットケースをつくり出しています。受講生も幅広い業界から年齢・経歴も異なる多彩な方々が参加し、意見交換や議論を活発に行っています。世界を変える新たなアイディアやイノベーティブな考えは、こういった場所から生まれると実感していますね。
玉塚 現実問題としてリーダーシップやアントレプレナーシップを持つ人材が増えれば、社会の変革は加速するとは思いますが、同時に物事を深掘りする専門家も不可欠です。ロッテにも、噛むことを研究する人やポリフェノールを研究する人など、専門性の高い人材もいます。さまざまな分野で活躍できる人材を育てるためにも、アカデミアとビジネス双方の領域のコラボレーションが活発になることで、いろいろなシナジーが生まれ、ひいては人材の多様性にもよい波及効果がありそうですね。



 「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値
「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術
AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由
今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳
「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設
GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方
組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び
上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは
上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは
「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像
上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由
日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意
「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道
産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由
上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは
元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」
国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い
データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義
あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ
「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う
「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」
マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由
経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?
人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?
国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦
コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性
上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」
国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」
スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」
上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?
上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立
日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由
事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質
上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい
「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩
上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

