「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う 上智の国連Weeksで触れる「リアルな現場感」

パンデミックでいっそう求められる国際協力
――新型コロナウイルスの対策で、改めて国を超えた協力が必要になっています。国連はどのような役割を果たしていくのでしょうか?
根本:世界的大流行が始まって1年半余りが過ぎました。SDGsでいえば、「グローバルヘルス」の分野における危機として始まりましたが、またたく間に他の分野の危機へと連鎖してしまいました。教育、女性への不平等、経済や金融、環境……と広範に影響し、国連のシステムを総動員しなければ立ち向かうことができない大きな危機になっています。
植木:国連としてもパンデミックの中で国々が紛争をしている場合ではないと、アントニオ・グテーレス国連事務総長がグローバルな停戦を呼びかけましたね。ワクチン開発や国を超えてワクチンを公正に普及させるためにCOVAXというワクチン提供の枠組みもできました。COVAXは、これまでにない国際協力の枠組みです。WHOも主導機関の1つですが、国際民間組織や財団などが力を合わせてできたネットワークです。これは画期的なことですよね。
根本:今、アフリカと先進国のワクチン普及の差は、25倍もあるといわれています。これを「国力の差」で片付けていいのか。

所長 根本かおる
東京大学法学部を卒業後、テレビ局のアナウンサー、報道記者勤務を経て、フルブライト奨学生として米コロンビア大学に留学。同大学国際関係論大学院で修士号を取得。1996年〜2011年まで国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)職員として、トルコ、ネパールなどで支援活動。ジュネーブ本部での政策立案も手がける。その後国連からは一度離れ、フリージャーナリストを経て、13年より現職
それだけでなく、ここまでグローバルな感染症は、グローバルで抑え込まなければ、また広がってしまいます。自分たちだけのことを考えるのではなく、グローバルな目線でのワクチン接種の推進が不可欠なのです。
また、パンデミックは、医療だけでなく情報の面でもインフォデミックという問題を引き起こしています。デマ、不確かな情報、ヘイトスピーチ……そうした情報が蔓延すると、中傷を恐れたり正しい判断が難しくなったりして、声を上げられなくなる人が増え、治療や支援が必要な人に回らない状況を引き起こします。正しい情報は退屈に思われてしまい、衝撃的なデマのほうが圧倒的に拡散しやすいという問題が改めて浮き彫りになりました。
だからこそ、国連のグローバル・コミュニケーション局の一員でもある私たちは、インフォデミックとの戦いで大きな役割を担います。「Verified(ベリファイド:検証済み)」という、信頼できる正確な情報を増やし、普及させることにより、新型コロナウイルス感染症にまつわるデマの蔓延を防ぐための国連のイニシアチブがあり、「#TakeCareBeforeYouShare(シェアする前に考えよう)」というSNSを中心としたキャンペーンや拡散の前に確認すべきポイントの解説などを通じて、正しい情報を精査するよう呼びかけています。

植木:パンデミックにより、経済、教育、雇用など、これまでに存在していた格差が一気に拡大してしまいました。日本にもともとあった相対的貧困がさらに広がり、仕事を失う人も増えています。オンライン授業も、世界的に見たら取り組めている国や地域はほんの一部で、学校に通えずに教育機会を奪われている子どもはたくさんいます。
根本:パンデミックを通して「誰一人取り残さない」というSDGsの理念がいかに大事かを改めて痛感しました。コロナ前からあった社会のゆがみが一気に可視化され、シワ寄せが脆弱な立場にある人々にいってしまうことが世界でも日本でも明るみに出ました。「誰一人取り残さない」という大原則を、私も心の中で何度も繰り返し、忘れないようにしています。
人間は希望が欲しいものです。大変な状況にあっても、トンネルの先に少しでも希望が見えると、頑張る力が湧いてきますよね。小さな積み重ねや、みんなで力を合わせることで見えてくるソリューションと希望の光を見せることが、私たちの重要な役割だと思っています。
無料で誰でも聴講可能な上智大学「国連Weeks」
――いよいよ10月に上智大学で国連Weeksが開催されますが、今回のポイントを教えてください。
植木:6月と10月の年2回、根本さんたちの協力も得て開催するようになってもう8年、今度の10月で16回目の国連Weeksになります。もう上智の伝統になりました。国連や国際協力分野に興味のある学生や社会人はもちろんのこと、将来の夢を模索している方など、どんな方でも参加できます。きっと自分の関心分野とつながるトピックがあると思いますよ。
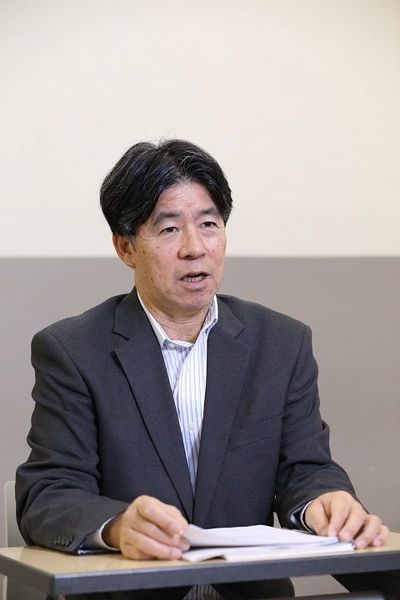
教授 植木安弘
1976年上智大学外国語学部ロシア語学科卒(国際関係論副専攻)。米コロンビア大学で修士号、博士号を取得。82年より国連事務局広報局、92~94年日本政府国連代表部(政務班)、94~99年国連事務総長報道官室、99年~広報局に勤務。ナミビア、南アフリカ、東ティモール、イラクなどの国連フィールド活動にも従事。2014年4月より上智大学にて教鞭を執る
コロナ禍で昨年からオンラインになりましたが、そのおかげで地方や海外からも参加や登壇が可能になりました。昨年10月にはフィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官にジュネーブから登壇いただき、今年の6月には国際連合訓練調査研究所のニキル・セス事務局長がやはりジュネーブから登壇され、10月にはアミーナ・モハメッド国連副事務総長がニューヨーク国連本部から参加されます。コロナ禍のグローバル・ガバナンスの課題、持続可能なエネルギーと太陽電池、SDGsのグローバル課題などの講演会やシンポジウムが予定されています。
根本:国連Weeksは、今や上智大学のフラッグシップイベントになっていますよね。植木先生が国連を退職されて上智大学の教授になられる頃から、「いつか大学と連携した国連のシリーズを一緒にやりたいですね」と話していたのを覚えています。
上智大学は、国連と大学との連携の枠組みである「国連アカデミックインパクト」にも加入していますが、それだけではなく国連と企業連携の「グローバル・コンパクト」にも加盟しています。ESG投資にコミットする責任投資原則にも加わり、学術だけでなく、経営体、投資体も三位一体になって国連に関わっているのが、上智大学。国連にとっても心強い仲間だと思っています。今回の国連Weeksも多くの方に参加していただきたいですね。
これから国際社会で活躍する若者たちへ
――最後に、将来国連で働きたい若者や、それ以外の仕事でもこれから経験を積んでいく若い世代にメッセージをお願いします。
植木:つねに好奇心を忘れず、オープンマインドでさまざまなことを学んでほしいと思います。気候変動、人道支援、今ある社会の持続がどうしたら可能なのか、そういった問題に対して好奇心を持って、自分で解決策を考えてみるといいですね。また、人脈を大事にしてください。困ったときには信頼できる人に相談して、協調しながら問題解決に向かっていくことが大事なのです。
人生は一度しかありません。人生にはいろいろな曲がり角があり、その曲がり角でベストの選択をすればいいのです。もちろん振り返ってみるとその選択がベストじゃなかったと思うこともありますが、少なくともその時のベストを尽くして、その後に自分なりに努力をすれば納得できるはずです。一方で、全力を尽くして失敗したことが、たまたまいい結果につながることもあります。できる限りの最大の努力をしてほしいです。
根本:私が大学生をもう一度できるなら、エッセイやプレゼンなど英語をもっと使う機会を増やすでしょう。さらに、各国の代弁者でもある留学生たちと積極的に交流して、彼らの考えやバックグラウンドを知りたいですね。

もう一つは、自分の根っこを大事にすること。子どもの頃になんとなく思い描いていたことと、大人になってやっている仕事を比較してみると、実は根っこで問題意識がつながっているのを感じます。興味のあること、疑問に思ったこと、理不尽に思ったこと、そうした若い頃に思ったことを大事に温めていくと、どんな仕事にもつながる核があるはずです。
最後に、将来を考えるときにHOWよりもWHATとWHYを突き詰めてほしいです。目的の職業にどうやったら就けるかよりも、何をやりたいのか、なぜやりたいのか、それを大事にしてほしいです。どんな社会を目指すべきかを問い、その社会にどう貢献したいかを考える。そう捉えると、国連ではなく、NPOや民間企業のほうが、自身の根っこに近いことができると感じるかもしれません。
国連Weeksで国連の仕事や空気、社会課題に触れてみてください。自分のやりたいことを見つけるきっかけにもなるでしょうし、社会人の方であればご自身の仕事の課題解決への糸口がきっと見えてくるでしょう。



 「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値
「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?
「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」
国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術
AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由
今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳
「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設
GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方
組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び
上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは
上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは
「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像
上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由
日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意
「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道
産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは
ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由
上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは
元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」
国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い
データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義
あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ
「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」
マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由
経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?
人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?
国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦
コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性
上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」
国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」
スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」
上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?
上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立
日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由
事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質
上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい
「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩
上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

