上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 SDGsはバッジを付けただけでは意味がない

投資家に説明できるSDGsとは?
ここ数年で「SDGs(持続可能な開発目標)」や「ESG(環境・社会・ガバナンス)投資」といったキーワードを目にする機会が増えている。次世代のために持続可能な地球環境を維持すべきという倫理的な捉え方がある一方で、SDGsやESGに注力する企業が投資家からの信認を得やすいという背景もある。
だが、上智大学の引間雅史特任教授は、「日本企業もSDGsやESGへの取り組み機運は高まってきていますが、まだイメージ戦略的なレベルにとどまっている企業も少なくない」と指摘する。
CSRリポートなどにSDGsの17のゴールに本業を当てはめてアピールしている例を見かけることも増えているが、それだけでは不十分というのだ。
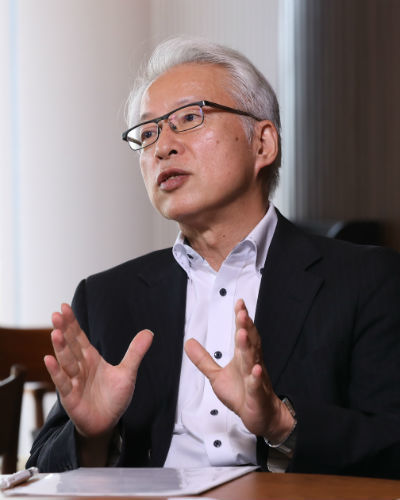
特任教授
学校法人上智学院 理事
引間 雅史
「単に、『わが社のこの事業はこのゴールに近いだろう』というのではスローガンで終わってしまいます。持続可能な世界を実現する17のゴールの先には、169のターゲットが構成され、さらに244(重複を除くと232)のグローバル指標があります。これらを丹念に見ていくと、社会課題を解決するために必要なKPI(成果指標)があることがわかります」(引間教授)
つまり、そのKPI達成に資する企業は、「世界的な課題解決に貢献できる企業」と言い換えることができる。
「自社のサービスや製品がKPIにどの程度貢献できるのか、そしてそれが自社の企業価値にどうつながるのか、投資家に説得力を持って具体的に説明できることが大切なのです。自ら検証し、できていないことを改善し次のアクションにつなげていく。そのようなPDCAを回すものがSDGsなのです」(引間教授)
民間企業抜きでは大きな効果はない
そもそもSDGsとは、2015年の国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標だ。SDGs自体は4年程度の歴史しかないが、地球環境に対する取り組みはこれまでにも各国が行ってきている。上智大学の浦元義照特任教授が解説する。
「これまでに国際社会は、開発、貧困、環境などの課題に取り組んできた長い歴史があります。1990年には『子どものための世界サミット』が、92年には『地球サミット(国連環境開発会議)』が開かれたほか、さまざまな会議も行われてきました」

グローバル教育センター
特任教授
浦元 義照
浦元教授は国連児童基金(ユニセフ)、国連工業開発機関(UNIDO)、国際労働機関(ILO)などに36年間にわたり勤務した経験を持つ国際協力のプロフェッショナルだ。
「国レベルのさまざまな取り組みが進められる一方で、現場では政府開発援助(ODA)などの公的な施策だけでは課題解決ができないという問題に直面していました。こうした中、提唱されたのが当時のコフィー・アナン国連事務総長による『国連グローバル・コンパクト(UNGC)』でした」
「グローバル・コンパクト」は99年の世界経済フォーラム(ダボス会議)の席上でアナン氏が提唱したものだが、大きな特色は、民間企業を含むさまざまな団体にグローバルな課題解決への参加を求めた点にある。
国家レベルでコミットを強めても、最終的には現場で手を動かす民間企業が腰を上げないと大きな効果はないとアナン氏は見抜いていた。その流れを受けて、SDGsが採択され、民間企業のコミットは狙いどおり年々強まっている。
投資家は「統合報告書」を見ている
今では、前述のとおり、SDGsに掲げられた指標の達成に貢献できる企業は成長性や競争力が高いと見なされ、投資が集まる傾向が出てきているが、その評価を得るのは容易ではない。
そこで統合報告書に注目が集まっている。統合報告書とは、企業が外部に向けてどのように価値を創造していくかを、財務情報(定量データ)や非財務情報(定性データ)を使って説明したもの。国によっては、企業に公表を義務づけているところもある。
浦元教授は、「統合報告書には、欧州をはじめとする世界の潮流に対応したものが求められます。投資家だけでなく、株主や消費者などを含め、企業のステークホルダーがグローバル化しているからです。一方で、これらに携わる人材は国内ではまだまだ不足しているのが現状です」と話す。
2019年11月18日~22日にかけて上智大学で行われる「企業価値を創造するESGと統合報告の最先端」は、まさにこのニーズに応えるものだ。特筆すべきは充実した講師陣。浦元教授が講座のコーディネーターを、引間教授が講座のアドバイザーを務めるほか、ESG投資や統合報告書などの分野で世界的権威である英レディング大学のグンナー・リメル教授など、国内外から第一線で活躍する講師陣がそろう。
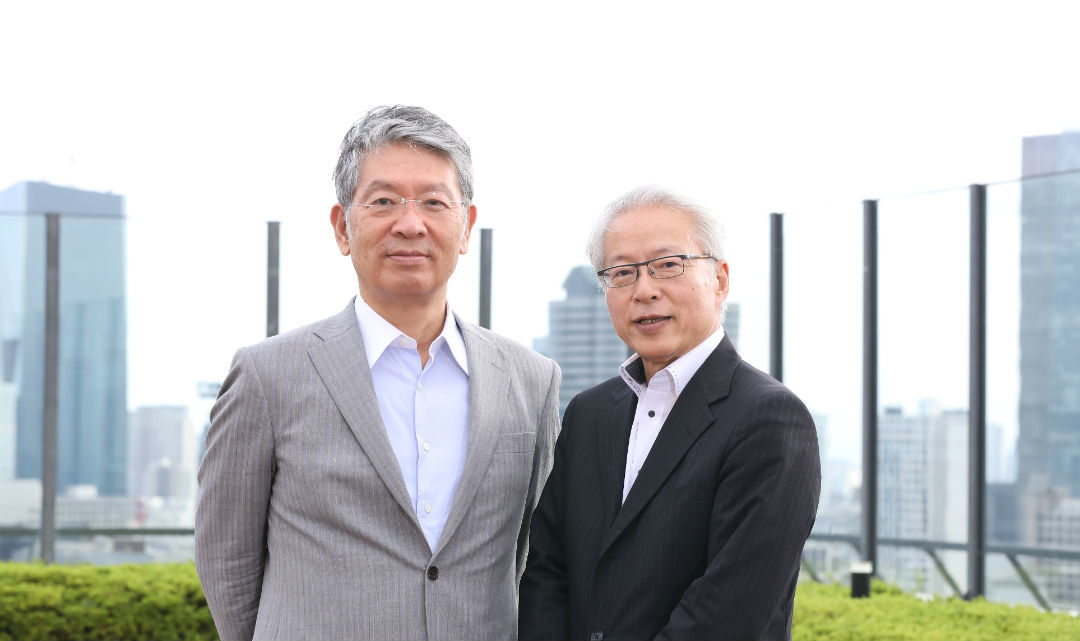
浦元教授は「講座のサブタイトルに『世界水準のESG投資の課題分析と統合報告書作成のスキルとノウハウを学ぶプログラム』と掲げているように、情報収集などにとどまらず、企業に戻ってすぐに実践していただけるように工夫を凝らしています」と紹介する。
講義では欧州連合(EU)の制度化の動向なども含め、国内外の最新の事例がふんだんに活用される。さらに、講師との対話式セッションが中心だが、ほかの受講生とのワークショップなども多く用意されている。共同作業を通じて、自らの経験を生かしながら、新たな気づきを得られそうだ。外国人講師による講義を含め、すべてのセッションに同時通訳が付く。なお、対話式セッションおよび共同作業は日本語中心で行われるため、特別な英語能力は必要ない。
講義のコマ数は、1時限90分のコマが1日3コマ、5日間で15コマにもなる。よくある半日間のセミナーなどに比べればかなりタフな内容だが、それだけにこの講座を終えれば大きな手応えを得られるに違いない。
「ESG投資で重要なのは、どういったESG要因が投資対象の将来価値にとって重要性が高いのかを見極めることです。マテリアリティーを踏まえた総合的な分析評価をしなければ投資の適切な意思決定ができません。統合報告書を作成する日本企業は増えていますが、まだ投資家に評価されるような発信は限定的なようです。日本企業が投資家とのコミュニケーションを密にし、それが企業価値向上や資本コストの削減につながるような取り組みを支援したいと考えています」(引間教授)
この講座には、業種業態を問わず、SDGsやESG投資に関心を持つ意欲の高い企業の人材が集まることになりそうだ。ここで得た知識やスキル、人的ネットワークは将来にわたって個人の財産になり、それを抱える企業の成長につながりそうだ。



 「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値
「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?
「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」
国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術
AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由
今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳
「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設
GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方
組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び
上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは
上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは
「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像
上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由
日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意
「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道
産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは
ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由
上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは
元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」
国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い
データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義
あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ
「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う
「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」
マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由
経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?
人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?
国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦
コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性
上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」
国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」
スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?
上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立
日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由
事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質
上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい
「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩
上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

