マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 上智大学「プロフェッショナル・スタディーズ」
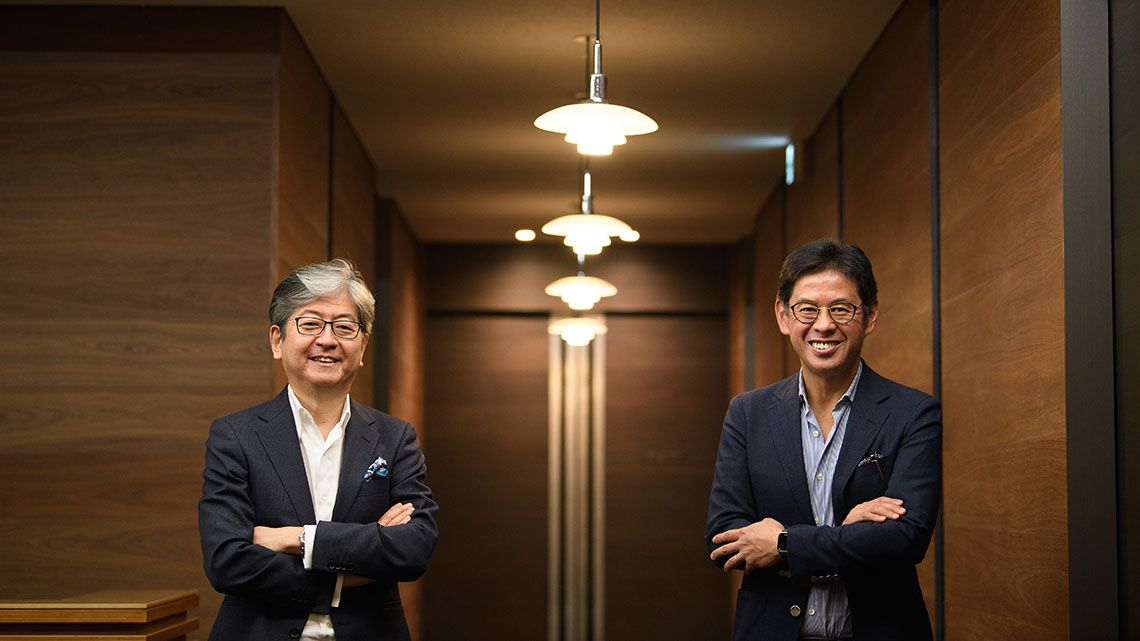
誰でも世界の最前線にアクセスできるわけではない
――松本CEOと西澤副学長との縁は深いと聞いています。
西澤 今日はあえて「松本さん」と呼びますが(笑)、中学・高校の同級生で、机が隣同士になったこともありました。卒業後もさまざまなところでご一緒しています。
松本さんは金融業界の第一線で30年以上にわたって活躍していますが、よく「そろそろ自分たちの次の世代の人材を育てなければならない」と話しています。本学の「プロフェッショナル・スタディーズ」は、社会人に向けた新たな学びのプログラムとして2020年秋に開講しました。そこで、これからの日本を担うような人材の育成に協力いただけないかと、松本さんにもプログラムへの参加をお願いしました。
松本 私もあえて「西澤さん」と呼びますが(笑)、話をいただいて、私自身の経験を伝えることも役に立つのではないかと考えました。

代表執行役社長 CEO
松本大氏
私は社会人になってからずっと資本市場の仕事に携わってきましたが、私が社会人になりたての頃と比べると、環境はとてつもなく変化しています。テクノロジーも進化し、コンピューターを使うことも当たり前になり、ブロックチェーンのような新しい技術も生まれています。さらには、ESG(環境・社会・企業統治)などの新しい投資の考え方が広まるなど、あらゆる面がアップデートされています。
そして、グローバル化です。私は米国の上場企業の社外取締役を務めていることもあり、米国に行くことも多いですが、米国をはじめとする海外の市場も日々アップデートされています。
一方で、国内にいる社会人の皆さん全員が、仕事でそのような機会が得られるとは限りません。私の話を通じて、何か気づきや発見を得ていただければと思っています。
西澤 上智は世界で通用し活躍できる人材の育成を目指しています。しかしながら、学生の場合は通常の生活の中では国内のマーケットしか見られなかったり、人付き合いも友人などに限られていたりするでしょう。また、世界で活躍している方に、海外から大学に来ていただくことは多いのですが、日本から海外に出て活躍している人のほうが親近感を持ちやすいですし、学生たちもまた自分の将来のイメージ像を持ちやすいわけです。
先日、松本さんに「デジタル通貨とデジタル資産〜金融最前線」というテーマで経済学部主催の講演をしてもらったところ、たくさんの学生たちが参加してくれました。Zoomを利用したオンライン講演会でしたが、松本さんのライブ感覚での話が非常に好評でした。
松本 チャットで質問を受け付けながら話をしたんですが、参加者の方は皆熱心で、読み切れないぐらいたくさんの質問がありました。中には鋭い、本質を突いた質問もいくつかありました。学部の学生でもよく勉強しているなと感心しました。
不平を言う人と、考える訓練をする人
――「プロフェッショナル・スタディーズ」は社会人を対象としたプログラムであることが大きな特長です。社会人になってから学ぶ意義はどのあたりにあるのでしょうか。
松本 スポーツに関して、トレーニングもしないで、いきなりゲームに勝てると思う人はいないでしょう。テニスの試合に勝つためには、筋トレや素振りなど基礎的なトレーニングが欠かせません。
ところがビジネスに関しては、何の準備をしていなくても、いざとなればひらめくのではないかと思っている人が案外いるんです。筋肉は日頃から使わないと筋力が落ちていくように、頭もつねに使っていなければ脳のシナプスは増えません。学び続けていないと、力はつかないんです。

副学長
経済学部 教授
西澤茂氏
西澤 社会人の方と話すと、学生時代にもっと勉強しておけばよかったと後悔している人が多いですよね。そうなってしまう最大の理由は、学生時代に勉強していたときは、勉強の目的や意味がわからなかったということだと思います。例えば、人間学です。人間はなぜ生きているのか、どこに人生の喜びがあるのかといったことを勉強しても、大学生にはなかなかピンときません。大きな病気をしたわけでもないし、何らかの苦難に直面したわけでもないからです。しかし、社会人になっていろいろな問題に直面すると、自分の人生の意義は何だろうか、生きるとは何かと考える機会は意外とあるのではないでしょうか。
松本 社会人の方でも、毎日同じ仕事をしているので学びはないという人もいますね。私はそれも違うと思っています。というのも、スマホを見れば毎日世界中のニュースを読むことができます。中には不祥事を起こした企業のニュースもあります。そのときに、なぜそのようなことが起こってしまったのか、自分が経営者だったらどうすべきかと考えるんです。
自分の会社でもいいでしょう。上司や社長から何か言われたときに、自分が逆の立場だったらどう言うか、どう行動すべきかという視点を持って考える。
ただ単に、毎日不平不満を言っている人と、考える訓練をしている人とでは、1年後、2年後に大きな差になるでしょう。

西澤 そのときに1人で考えていると情報がなかったりして答えが出ないこともありますね。そこで、一緒に議論してくれる人や過去の経験からアドバイスしてくれる人がいると助けになるでしょう。とくに異業種の人とディスカッションをするのは価値があると思います。
本学の四谷キャンパスは、都心の四ツ谷駅前にあります。社会人の皆さんの職場からのアクセスもいいので、「プロフェッショナル・スタディーズ」にはさまざまな業種業態、さまざまな年代の方々が参加しており、一緒になって、情報共有をしたり、ブレーンストーミングをしたりしています。そこから新しい発見や新しい視点が得られるのではないでしょうか。
IFRSは「世界の共通言語」
――「プロフェッショナル・スタディーズ」は2021年度、36のプログラムが開講されます。西澤副学長が担当されるプログラムについて教えてください。
西澤 私がコーディネートするのは「国際会計〜IFRSの会計情報とグローバル企業の財務分析〜」というプログラムです。会計は全世界で使われているビジネスランゲージ、すなわち共通言語です。逆に言えば、共通言語が理解できなければ意思決定ができませんし、世界で通用する人材として活躍できません。
意思決定できるようになるためには、さまざまな国々のビジネスの情報を誰かが解説した内容で理解するのではなく、オリジナルの情報を自分で把握し判断することが大切です。プログラムではそのような視点を提供したいと考えています。もちろん、一方的に教えるだけではなく、松本さんのようなゲストスピーカーから、最先端の金融やグローバルマーケットの動向を説明してもらったり、受講生同士でディスカッションしたりする場も設けます。それにより、今後の成長のためのインスパイアになるようなものをつくりたいと思っています。

松本 当社も14年にIFRS(国際会計基準)を適用することを決定しました。当時、私たちは、今は小さい会社だけれども世界標準にしよう、そこから始めていつかグローバル企業になろうと考えたからです。その頃、国内ではまだIFRSを適用する企業はさほど多くありませんでした。適用のための作業はなかなか大変でしたが、そこで頑張ってやらないといつまでも国内のドメスティックなローカルルールのままの開示になってしまいますから。
西澤 松本さんはよく、「既存の金融機関はいずれなくなる」という話をしていますね。10年前なら、金融機関は学生の人気の就職先でした。ところが最近では、大手の金融機関ではなく、ベンチャー企業など新しい取り組みの金融サービスや事業をしたいという学生が増えています。そういった学生は、松本さんの話に共鳴するようです。中には、日本ではやりたいことができなさそうだから海外に行こうという学生もいます。
松本 私はまだまだ日本も捨てたものではない、むしろチャンスがたくさんあると思います。
東京オリンピックでは日本選手が大活躍し、たくさんのメダルを取りました。10代前半で金メダルを取った選手もいます。それは単純に明確なルールで、強い人を選手に選んだからだと思います。外国人のコーチを起用したことにより躍進した競技もあります。年功序列でチームを組んでいたら勝てるわけがありません。
日本企業も年功序列をやめて、メリトクラシー(能力主義)に基づいてチーム編成をするだけで、世界でも競争力を発揮できると思います。
西澤 これからの元気な日本をつくってくれるような人材を育成したいですね。そのためにも多くの方々に「プロフェッショナル・スタディーズ」に足を運んでいただきたいと願っています。



 「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値
「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?
「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」
国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術
AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由
今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳
「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設
GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方
組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び
上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは
上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは
「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像
上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由
日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意
「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道
産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは
ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由
上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは
元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」
国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い
データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義
あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ
「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う
「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由
経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?
人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?
国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦
コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性
上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」
国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」
スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」
上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?
上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立
日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由
事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質
上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい
「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩
上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

