中学・高校から「金融経済教育」拡充で何が変わる? 本格実施を前に「体験型学習教材」導入のススメ

新必修科目「公共」で学ぶ金融経済のしくみ
学校教育の現場では、新学習指導要領に基づいて、本格的に金融経済教育の授業が始まることになった。すでに中学校では2021年度から金融リテラシーを高める授業が盛り込まれているが、高校でも22年度入学の生徒から新科目「公共」で、基礎的な金融経済の仕組みについての授業が行われ、「家庭科」の授業では投資信託などの金融商品や資産形成の視点にも触れた授業が本格的にスタートする。
これまで資産形成も含めた金融経済の学びといえば、大学の特定の学部において学ぶというのが通例だった。しかし、これからは高校卒業までに社会で生きていくために必要な金融経済の知識を身に付けることで、将来的に日本全体の金融リテラシーを高めていく狙いがある。
こうした中、金融経済教育の支援に力を入れているのが日本証券業協会だ。金融・証券系の業界団体だが、新学習指導要領の実施に伴い、学校向けの金融経済教育支援に本腰を入れ始めている。同協会の金融・証券教育支援センター長である内田直樹氏が言う。

(写真:日本証券業協会提供)
「これまでも私たちは先生方に対する金融経済教育の支援活動に携わってきましたが、今回、新学習指導要領において金融経済教育の内容が拡充されたことで、さらに学校向けの支援に力を入れていきたいと考えています。先生方もセミナーなどを通して、知識をアップグレードしようと積極的に準備を行っています。金融経済教育は重要であるという認識を皆さんと共有しており、子どもたちにいかに教えていけばいいのか。研究を続けているところです」
もともと同協会が教員向けの金融経済教育支援を始めたのは1980年代から。90年代半ばからは株式学習ゲームなどの教材を学校に提供するなど、長く金融リテラシーの向上に努めてきた。しかし、さまざまな課題を抱えている教育現場では、指導すべき事柄や取り組むべき内容がたくさんあり、どうしても金融経済教育に対する関心は薄かった。保護者にしても「金融経済の動きや資産形成は受験に関係ないし、大学から勉強すればいい」という考えが大半で、なかなか金融経済教育が中学、高校でなじむことはなかったのだ。
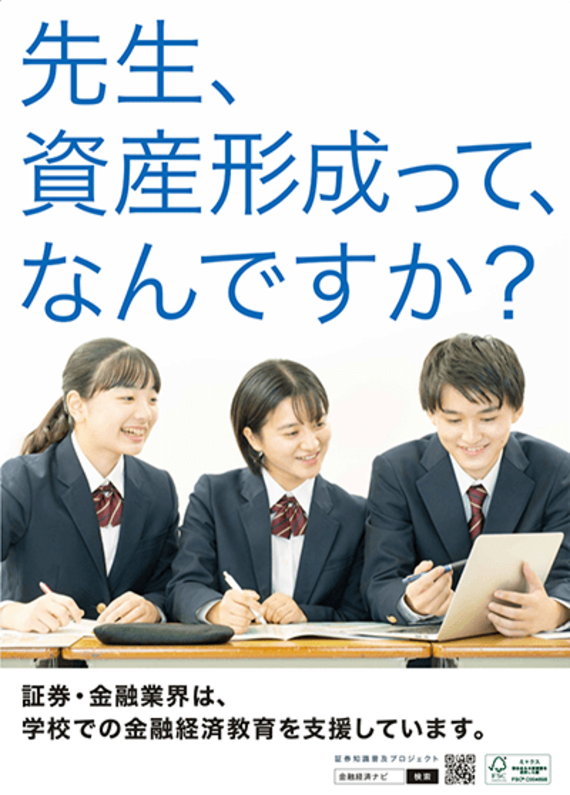
(資料:日本証券業協会提供)
しかし今回、同協会では『先生、資産形成ってなんですか?』というコピーのポスターを制作。学校で金融経済教育が実施されており、証券・金融業界が金融経済教育の支援をしていることを世間にアピールするほか、独自に金融経済教育支援を行う証券会社もあり、証券・金融業界を挙げて取り組む方針を示している。






























