睡眠不足が脳の発達や自尊感情を脅かす深刻実態 「睡眠教育」の推進で不登校数が減少した例も
保護者への働きかけがうまくいっている例として、西野氏は、自身も3年前から協力している大阪府堺市の睡眠教育を挙げる。いったいどのような活動なのか。
不登校生徒数が約半数にまで減少
現在、同市の小中学校では、学期ごとに2週間分の睡眠と朝食の記録をつけるほか、21時までに寝ることを目指す「はよねるデー」を月に1回設けるなど、睡眠教育、通称「みんいく」に取り組んでいる。
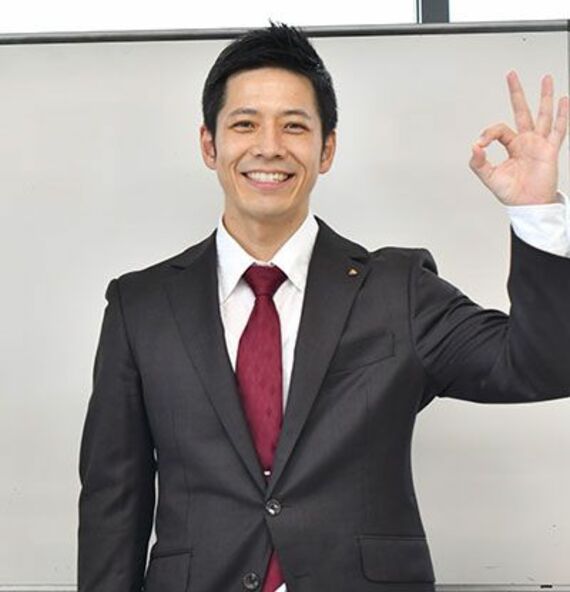
堺市教育委員会指導主事。中学校保健体育科教諭として勤務後、現職。日本眠育推進協議会評議員。上級睡眠健康指導士。大阪教育大学教職大学院修了。平成28年度読売教育賞最優秀賞受賞、平成28年度国際学会「Higher Education Forum」Best Paper Award(2位)受賞など。著書に『睡眠教育(みんいく)のすすめ―睡眠改善で子どもの生活、学習が向上する―』『「みんいく」ハンドブック』(ともに学事出版)、『ねこすけくん なんじにねたん?』『ねこすけくんがねているあいだに…』(ともにリーブル)など
(写真:本人提供)
主導するのは、堺市教育委員会指導主事の木田哲生氏。きっかけは、不登校問題だった。木田氏は、堺市立三原台中学校で生徒指導を担当していた当時について、こう振り返る。
「最近の不登校は、しんどい、だるいなどの訴えが多く原因がはっきりしないことが特徴です。学校としては『体調不良が治ったらおいで』と言うことくらいしかできませんでした」
そこで睡眠に注目し、専門医である熊本大学名誉教授の三池輝久氏の協力を得て、15年度からみんいくをスタートした。生徒指導の教員ネットワークを基盤に、地域の幼・保・小・中・高、PTA、子ども会、自治会などによる「みんいく地域づくり推進委員会」も発足させ、地域一体で推進。木田氏が教育委員会に異動した17年度には、全市へと取り組みが広がった。
その結果、三原台中学校では、15年度の不登校生徒数は35人、20年度は16人と約半数にまで減った。「市内中学校の不登校生徒数推移(17年度~18年度)も、みんいく実践校は非実践校に比べて有意な減少が確認されました」と、木田氏は語る。また、15年度から18年度のアンケート調査の結果によると、三原台中学校では、「自尊感情」と「学習に対する集中力」が毎年向上しているという。
保護者と担任に言われても効果がないことが判明
みんいくでは、睡眠記録を基に、睡眠が乱れている子どもや、いつも調子が悪そうにしている子どもに声をかけて睡眠改善の支援をしていく。木田氏の場合、主に子どもと面談して改善目標を立て、その内容を保護者に伝える形で実施してきた。
よい睡眠を取るには腸を動かして生活リズムをつくっていくことが重要なので、朝食を取るよう促すことも大切だが、「とくに小学校高学年から中学生に関しては、夜間のスマホ使用をいかに制限できるかが最も大きなポイントになる」と木田氏は言う。しかし、ただ「スマホをやめよう」「早く寝よう」と言っても効果はない。
「当初、私も熱意と知識を持って『寝よう』と訴え続けましたが、最初の半年間は1人も改善しませんでした。自分の心身を大事にする手段として睡眠があるわけですが、睡眠が乱れている子は自尊感情が低い場合が多く、『自分を大事にしよう』というメッセージが届きにくいのです。それに気づいてからは、まず子どものしんどさや、寝る前にスマホを触ってしまう弱さなどを否定せずに受け止めることを大切にしています」






























