クラスに2、3人?学校のLGBTQの「現実」 教員は、ポジティブな「肯定」を伝え続けるべき
「私は、小学校1年生の時に男の子が好きだということに気づきました。でも、好きな女の子もいたので、他者との違和感はありましたがうまく説明できなかったんです。学校の先生に相談したかったのですが、『先生にバカにされるのでは』『周りの人に言いふらされるのでは』『そうなったらもう学校に行けなくなるかもしれない、そうなるくらいなら黙っていたほうがいい』と無意識に口をつぐんでいました」
鈴木氏を息苦しくさせたのは、同性を好きになる気持ちを揶揄するような言葉だ。たとえ直接向けられたものでなくても、「あいつはオカマだ、ホモだ」といった嘲笑交じりの言葉が放たれれば、心が閉じてしまう。
「子どもですから無邪気に言っているんですが、そういう人がいる場所では心理的な安全性がまったく保証されませんから『絶対に明かさない』となってしまいます。私も、20歳になるまで社会からやんわりと否定されているような感覚がありました。ずっと『自分は変だ』『なぜこうなってしまったんだろう』と思っていましたし、大学に入学した頃まではどう生きていけばいいのかまったくわかりませんでした」
ポジティブな「肯定」を伝え続ける意味
鈴木氏がその閉塞感を打破したのは20歳のときだ。
「仲のいい女性の友達にカミングアウトしました。そうしたら『びっくりしたけど、シゲはシゲで変わらないからいいんじゃない?』と温かく受け止めてもらえました。その瞬間、まるでトレヴィの泉のように大きな安心と自信が湧き上がり、体の中を駆け巡ったことを覚えています。気持ちを共有してもらえるということは、こんなにも大きなエネルギーになると気づきました。この経験がなければ、現在のように社会に自分の性的指向を公表することはなかったと思います」
この鈴木氏の経験が示すのは、カミングアウトの大切さではない。自分を否定せず、すべてを肯定してくれる安心感がいかに大きいかということだ。
「先生は日常的に子どもたちと接していますので、何となく気づくこともあると思うんです。でも、その気持ちを先生に伝えるかどうかの選択肢を持っているのは、先生ではなく子どもたち自身です。無理やり言わせようとしたり、詮索したりするのは、“してはいけない対応”だと思います」
では、どうすればいいか。鈴木氏が提案するのは「環境整備」と「窓口の開放」の2つだ。「環境整備」は、前述のように「ありとあらゆる場面」で多様性を受容することの大切さを伝えたうえで、LGBTQに対するポジティブなメッセージを発信することを挙げる。
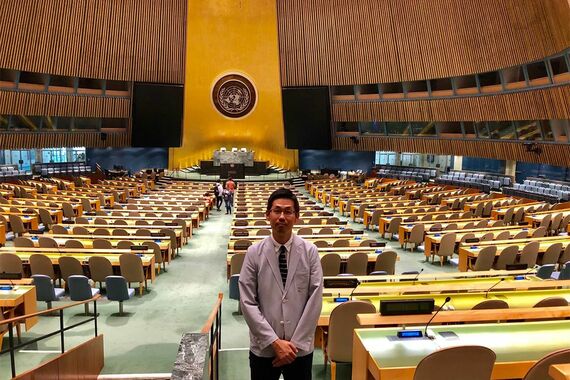
「例えば、学級文庫の中に性の多様性について書かれた本を入れるだけでもいいと思いますし、朝の会で先生がLGBTQのポジティブな話をするのもいいでしょう。“1人1台PC”の環境が整いますので、動画教材などを活用するのも効果的です。そうやって多様性を受容する環境を整えることで、LGBTQ当事者だけでなくすべての子どもたちの心理的安全性を広げられます」






























