上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 必要なのは「議論への貢献」「意思決定の質」
曄道:日本の「教養」という言葉の使われ方は少し特異ですよね。「物知り」といったような意味合いが強い。学生たちに教養の話をした時に、彼らがそれを情報と勘違いすることがあります。しかも、今の学生は情報が無尽蔵に詰まったスマホを持ち歩いているので、教養にあふれているという錯覚に陥りかねない。そういう時、大学の教育機関として「教養がどうあるべきか」「人材育成をどうあるべきか」ということをつねに自問自答しつつ、長澤さんのように実際の社会で働く方との対話も必要だと感じています。
大学は最後の学びの機会ではない
――国際的に通用する教養は、大学など教育機関で育てていけるものでしょうか?

アジア太平洋地域業務執行委員、北アジア代表
長澤和哉
慶應義塾大学理工学部機械工学科卒。同理工学研究科修士課程修了後、明治生命保険(現:明治安田生命保険)入社。後にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントに転職し、計量投資戦略グループの日本責任者を務める。2012年MSCIに入社し、18年より現職。日本ファイナンス学会理事
長澤:過去20年にわたり、企業は多様性の確保に一生懸命取り組んできました。今日のグローバル社会は、環境変化の程度もスピードも非常に激しく、同じような人材だけだと変化に対応できずに破綻する可能性が高まってしまう。性別、国籍、キャリア、アカデミックな背景などにおいて、さまざまな人材を抱えておけば、幅広い強みがあるおかげで環境変化にも対応できます。
このような多様性に触れる体験を大学時代から積むことは大事でしょうね。学生さんの出身国の数が多いとか、教員がバラエティに富んでいるとか、同級生に社会人や研究者もいるとか。企業との接点もそうですよね。自分とは異なるバックグラウンドを持つ人たちと交流し、学び合うことで、教養とは何か、何が欠けているのかに気づくきっかけになると思います。
曄道:そういう意味で、上智は現在約80カ国から1500人を超える留学生がいますし、教員も15%強は外国籍です。そのほかにも海外で学位を取った教員も多いです。このような多様性に富んだ構成員が四谷のワンキャンパスに集うのは、本学の大きな特徴ですね。
ただ重要なのは、大学が学びの最終機会ではないということです。大学を卒業してもこれからずっと学び続けていく。これからの世代はおそらく50年近く学び続ける。個人も組織もです。教養もそうですし、専門性もですよね。そのような視点に立った教育を再構築していかないと、長澤さんがおっしゃる人材像には近づかないですね。
長澤:当社でも学ぶことは重視しています。どうやって学ぶですが、7割は職務を通じて、2割は視野を広げるための機会を積極的に会社が用意する。たとえば当社の場合、ファイナンス学会や米国証券アナリスト協会、ポートフォリオ理論フォーラムなどに会員権があり、月に1度くらいはその時々の第一人者の話を聞けます。そして、残りの1割は体系的な知識を身に付けるために勉強する。そうすることで日々の業務などを全体像の中に埋め込んでいけるのです。

学生時代からアウトプットの機会を
――上智大学では、人材育成プログラムにも力を入れているそうですが、大学ではどんな学びが理想だと考えていますか?
曄道:学びと同時に経験を積むことが必要だと思います。ある経験を積むことで何が必要か見えてくる部分がありますよね。グローバル社会の中では、その経験が自分自身を展望する拠り所にもなります。上智は今さまざまな機会を学生たちに与えるようにしています。アフリカに行って貧困の現実を知る、カンボジアやインドでボランティアをしながら現地の社会について学ぶ、その一方で国連本部に行って現役の職員からレクチャーを受ける、ワシントンDCで元米国務副長官とディスカッションしてくる――。
このようなチャレンジを通して、学生たちにはもがいてもがいて、何とか踏ん張ってほしい。実際、帰ってきてからその経験がどう生きるのかというと、正直言えば、それはわからない。ただ、学部や研究室で学ぶ専門性とそうした経験とが有機的に結合を図ることが理想なので、もがいて踏ん張った経験がある学生はやはり強いと思います。



 「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値
「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?
「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」
国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術
AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由
今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳
「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設
GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設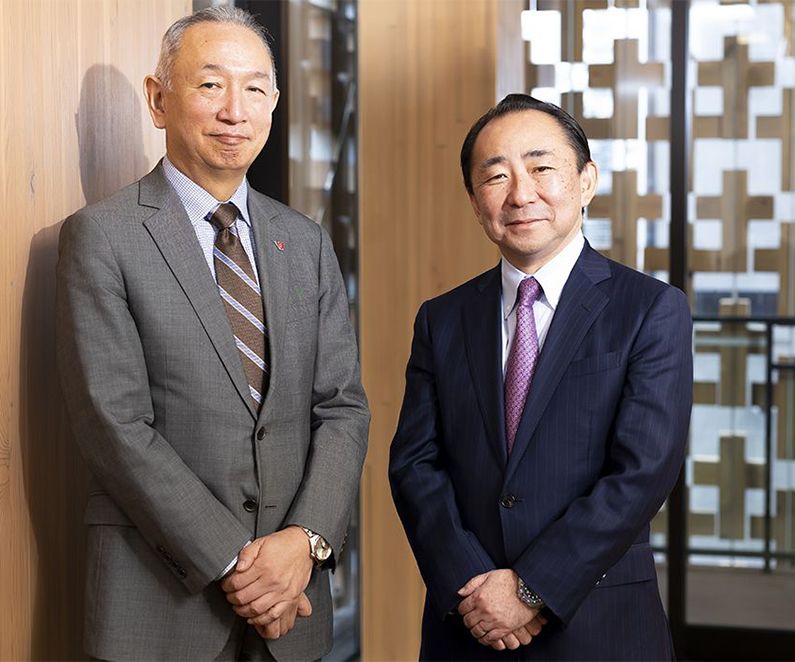 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方
組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び
上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは
上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは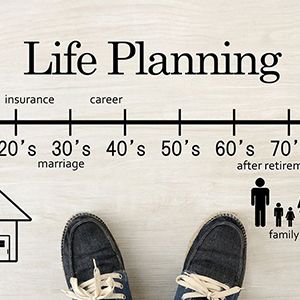 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは
「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像
上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像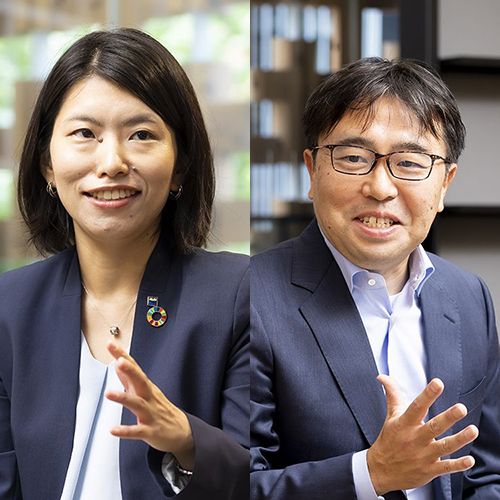 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由
日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由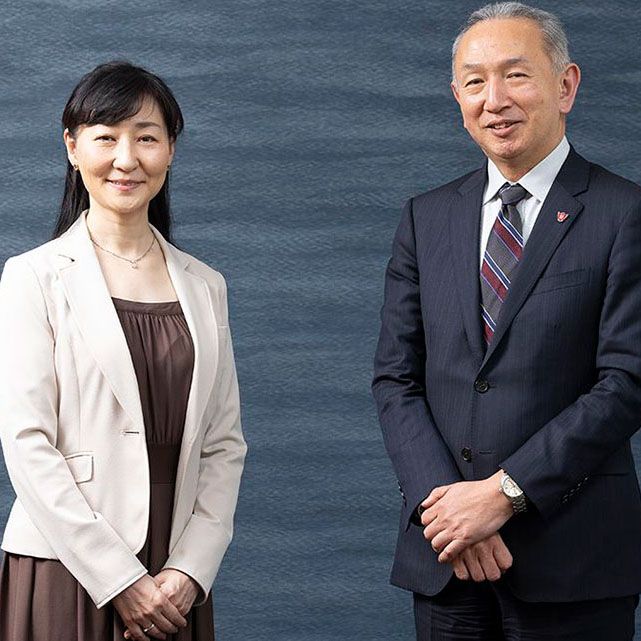 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意
「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道
産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは
ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは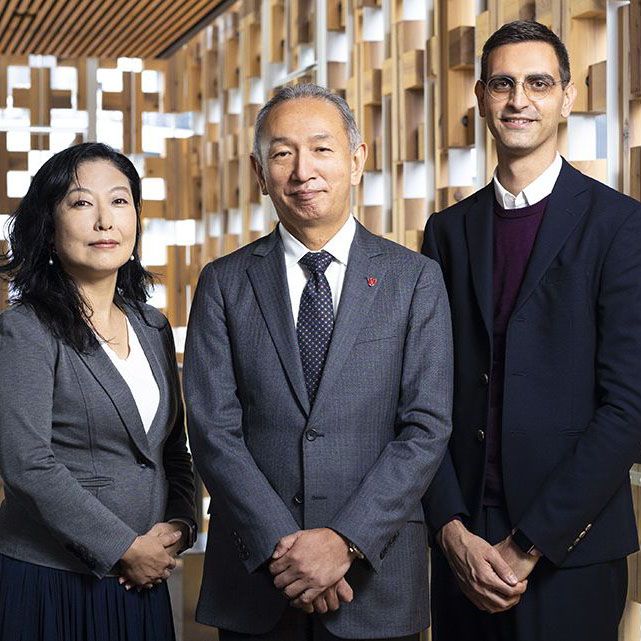 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由
上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは
元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」
国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い
データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義
あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ
「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う
「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」
マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由
経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?
人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?
国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?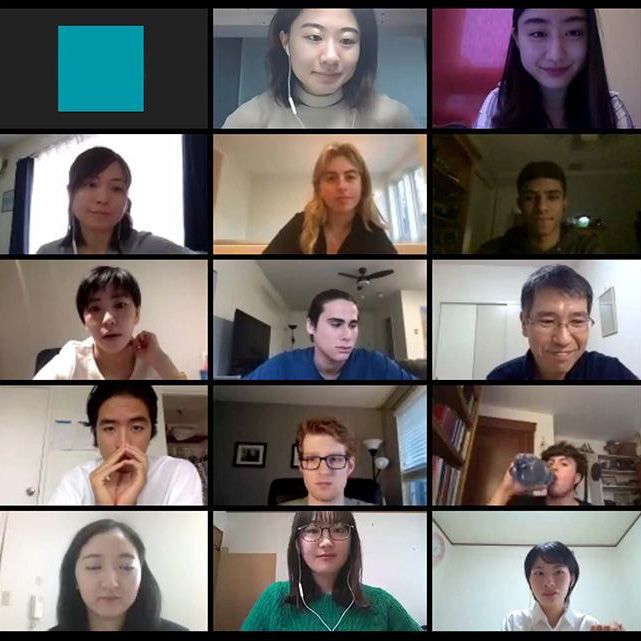 コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦
コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性
上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」
国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」
スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」
上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?
上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立
日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由
事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい
「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩
上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

