「大学入学者選抜ルール」が一部変更、話題の「学力型年内入試」2026年度はこう着地した 年内入試の学力試験容認も解釈に幅が残る
例えば、「英語100点満点+数学100点満点+調査書の評定平均値の素点」とした場合、調査書の評定平均値はオール5の場合「5点」ですので「100:100:5」となり、明らかにバランスに欠けています。

教育ジャーナリスト 、大学入試ライター、リサーチャー
1985年河合塾入職後、20年以上にわたり大学入試情報の収集・発信業務に従事。2007年に河合塾を退職後、都内大学で合否判定や入試制度設計などの入試業務に従事し、学生募集広報業務も担当。2015年に大学を退職後、朝日新聞出版「大学ランキング」、河合塾「Guideline」などでライター、エディターを務めるなど多くの媒体に寄稿。その後、国立研究開発法人を経て、2016年より大学のさまざまな課題を支援するコンサルティングを行っている。河合塾グループのKEIアドバンスで入試データを活用したシミュレーションや市場動向調査等を行うほか、将来構想・中期計画策定、新学部設置、入試制度設計の支援なども行っている
(写真:本人提供)
また、「小論文・面接・実技検査等の活用」または「志願者本人が記載する資料や高等学校に記載を求める資料等の活用」と「必ず組み合わせて丁寧に評価」することになっていますので、この場合、調査書だけですので条件を満たしていないと受け止められる可能性もあります。ここは「大学入学者選抜実施要項」の文面の解釈に幅が出る部分です。
なお、受験生・高校側としては、合格したあとの日程、とくに最終手続きの締め切り日が、生徒の志望順位が上位となる大学の合格発表日よりも前か後かはとても大切な情報です。入学金あるいは入学手続き金は納入することにはなりますが、上位志望大の合格発表を待ってくれないのであれば「学力型年内入試」を受験する意味合いが半減します。そして、さらに大切なことは、合格したことで第1志望の大学にチャレンジする意欲が減退しないよう、周りの大人が受験生を励まし続けることです。
現在、大学入学者選抜は、大きく分けて総合型・学校推薦型・一般の3分類となっています。今後「学力型年内入試」が拡大すると、出願・合格発表日程のルールが残ったとしても、3分類の境界線があいまいになります。
一方で、東北大学が国際卓越研究大学の研究等体制強化計画の中で、すべての入学者選抜を総合型選抜へ段階的に移行すると記しているように、特定の分類の選抜のみを行う大学が出てくることもあり得ます。果たして2026年度入試は境界線の溶解元年になるのでしょうか。
(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

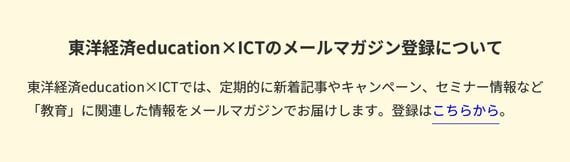































無料会員登録はこちら
ログインはこちら