ビルの運営主体は、都の外郭団体の傘下にある「東京テレポートセンター」。名称は、臨海副都心プロジェクトの前身に当たる「東京テレポート構想」に由来する。今となってはほぼ使われていない「テレポート」という言葉は、海の港、空港に続く「テレコミュニケーションのポート(港)」との意味で造られた。
都は1980年代に、テレコムセンターが「高度な情報通信基盤」(当時の鈴木俊一都知事)になると見込み、臨海副都心の開発においても先導的な役割を果たす目的で整備が進められることになった。
臨海副都心の計画や設計に最初期から携わった東京都市大学名誉教授の平本一雄氏(80)は「(当時)インターネットという言葉もまだなく、情報化が進み始めた時代だった。ビルにワイヤーを入れて情報装備し、ニューヨークとも簡単に通信できる、通信費用が安い特別区にしようとやり始めた。新しいビル群を集約して、国際競争に打ち勝っていこうとしていた」と振り返る。
バブル崩壊で運営会社が経営破綻
ところが、ビルの開業はバブル崩壊で日本経済が停滞する時期に重なった。バブル期の過大投資があだとなり、オフィスの利用や賃貸料収入自体も低迷したとされる。

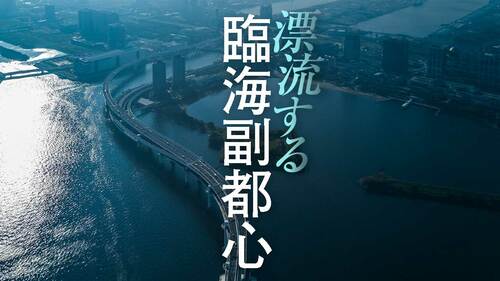































無料会員登録はこちら
ログインはこちら