定義上は「まだデフレ?」でも日銀は気にしない 需要不足に見えるのは「人手不足で設備が稼働できない」から
しかし、今の日本が考えるべき問題は「なぜ設備は使われていないのか」である。この点、2025年1月に日銀が公表した展望レポートのBOX欄「資本と労働の代替性と労働の供給制約」が有益な視座を与えている。
このBOX欄は「生産・営業用設備判断DIと雇用人員判断DIの関係をみると、過去においては、両者が概ね連動して動いていたが、最近では、人手不足感が強まっても、設備判断DIは不足超に動きにくい傾向があり、特にそうした傾向が非製造業において顕著である」との現状分析から始まる。
また、その背景としては「需要が改善する時には、通常、資本と労働の両方への需要も増加することになるが、業種によっては、資本と労働への需要の増え方が異なるケースもある。これは、業種ごとに、生産関数における資本と労働の代替性が異なることに起因する」と指摘されている。
設備を使いたくても、人がいないから使えない
要するに、製造業は資本と労働の代替性が高く、人手不足による制約を機械化やAI化などによって緩和できる度合いが大きい一方、非製造業ではその代替性が低い(≒補完性が高い)ため、人手不足問題が深刻化しやすいということである。
言い換えれば、非製造業に関しては人手不足とともに設備の利用すら難しくなっているという状況が推察される。人員が確保できずにランチ営業ができない飲食店や満室営業できないホテルなどを想像すればわかりやすいだろう。
「1%まで利上げ」発言が注目された日銀の田村審議委員も「
BOX欄ではこの資本と労働の代替弾力性を業種別に試算しており、サービス業や建設業が代替性の低さから深刻な人手不足に直面している実情を指摘している。より具体的に言えば、宿泊・飲食サービス、対事業所サービス、対個人サービスが「労働供給制約業種」として分析されている。
なお、対事業所サービスとは産業廃棄物処理業や土木建築サービス業やデザイン・機械設計業などが含まれ、対個人サービスは介護・福祉・教育業などが含まれる項目である。








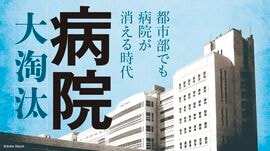



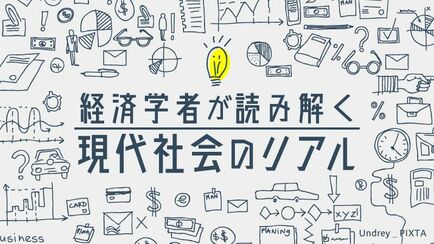



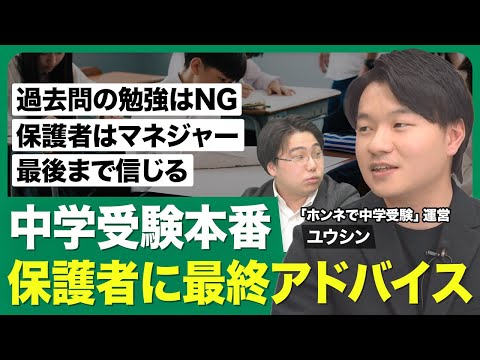



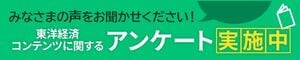
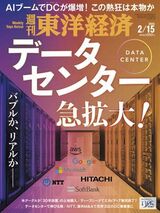







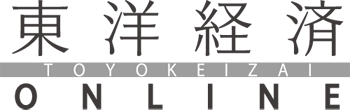


無料会員登録はこちら
ログインはこちら