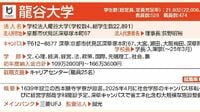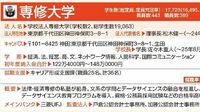福井県立大学に日本初「恐竜学部」が誕生、「学ぶのは恐竜だけではない」狙い 博物館とも連携、総合型選抜の倍率は10倍超
学部創設を発案したのは、進士五十八(しんじ・いそや)前学長と、日本の恐竜研究の第一人者である東洋一氏(恐竜学研究所前所長)だという。
現在、日本で確認された13種目の恐竜のうち、6種目が福井で発見されている。こうした学術的な功績は、「一連の発掘調査を推し進め、県立恐竜博物館を作り海外調査も含めて組織的に研究できる体制を整えた、東洋一先生の尽力によるものです」と西氏は言う。
恐竜研究と、恐竜王国という福井のブランドを継続させるためには、人材育成が欠かせない。そこで、恐竜研究を行うとともに、その成果を教育という形で反映することを目的に、2013年に恐竜学研究所を発足、2018年から大学院生への教育が本格的に始まった。そのうえで、人材を育成するには基礎から学べる学部が必要だということで恐竜学部が誕生したという。
「日本において恐竜研究を行う学科やコースはあるものの、学部名称として前面に打ち出すのは初の試みです。世界的に見ても恐竜と名の付く学部は珍しいです」と、西氏は説明する。
「フィールドワーク」と「デジタル技術」を融合
同大の恐竜学部では、恐竜だけを研究するわけではない。恐竜を自然科学の一環と捉えると、さまざまな分野が関係するからだ。
「トータルな自然史科学を学んでもらうようにしました。そのため、教員については、恐竜を主な専門としながら地質・環境・古生物などそれぞれ強みを持つ研究者を20人集めました。自然科学を基礎に、3年次からは『恐竜・古生物コース』と『地質・古環境コース』の2つのコースに分かれて専門性を磨いていきます」
学びの大きな特色としては、県立恐竜博物館との強力な連携体制、現場重視(フィールド科学の実践)、国際的視野に立つ教育・研究、先端技術による研究の4つを挙げる。
具体的には、福井県勝山市北谷恐竜発掘現場での化石発掘、発掘した化石の修復・補強などのクリーニング、研究・学習用標本をつくるレプリカ標本作成、博物館の展示を自身でデザインし発表する標本展示など、実践的な学びが盛りだくさんだ。
「2年次以降に通う新学部棟は恐竜博物館に近接します。博物館の研究員や学芸員の方々も教育研究に参加しますし、大学で製作したコンテンツは博物館に提供していきます」と、西氏は博物館との連携を強調する。

さらに、実際の化石からコンピューター上で3Dモデルを作り、バーチャル空間で展示・観察を行う古生物3Dモデル作成なども行うという。
「どんな分野もデジタルが必須となりましたが、古生物学においてもCTスキャンなどのデジタルによるアウトプット技術がないと論文が書きづらい時代になりました。そのため、『フィールドワーク』と『デジタル技術』という、今の恐竜研究に必要な2つの科学をうまく融合して学べるようにしています」