「サステナブルデザイン」は競争力強化の有効手段だ 全ての経営資源投入できれば日本の未来は明るい
また、これまで企業からは「消費者」、自治体からは「市民」と呼ばれてきた人々を高次で統合する「循環者」というペルソナ概念が提示され、企業や自治体が彼らを想定した取り組みを始めることによって、「循環型ものづくり」「循環型まちづくり」の認識基盤ができるとしている。
既存ビルのサステナビリティの重要性を指摘
井上惇(THIRD 代表取締役)
井上論文は、従来の不動産業界で排出されてきた大量のCO2と廃棄物を削減する取り組みをビジネスとして実践する実務者による論考である。日本では新築を重視し、老朽化した建物は廃棄するというスクラップアンドビルド・モデルが重視されてきた。
しかし、本論文が示すように、総住宅数における年間新築比率は1.4%、オフィスビルでは1%に満たないにもかかわらず、新築重視の日本ではスクラップアンドビルド方式が不動産ビジネスの基本となってきた。
また、最新技術の進展によって新築物件に搭載される省エネ技術が運用時におけるCO2排出量(オペレーショナルカーボン)を大幅に削減することからも、近視眼的には新築のほうが環境に優しく見える。
しかし、新築では資材や建設プロセスにおけるCO2排出量(エンボディドカーボン)も膨大であり、CO2の排出には建設から運用・廃棄に至るライフサイクル全体のいわゆるホールライフカーボンの考え方が重要なのである。また、欧州における環境認証のあり方が既存建築物の環境対策強化に向かっている現状も紹介されている。
そうした観点から、本論文は、圧倒的に流通量の多い既存ビルのサステナビリティの重要性を指摘する。そのカギとなるのが、IoTやAIを駆使して現場のデータを収集し、将来予測を進めるデジタルトランスフォーメーション(DX)なのである。設備機器(エアコンやポンプなど)の実際の稼働データを把握すれば、修繕費の大幅削減や長期使用が可能となる。
さらに、高齢化が進みデジタルリテラシーが低いとされる現場の設備員たちでもスマートフォンなどで簡単にデータ収集できるSaaS活用の取り組みが、既存ビルのデータ化を進め、効率的でサステナブルな維持管理を実現しうるとしている。
以上が、サステナブルデザインを各分野から検討した本特集の概要である。編集を終えて実感したのは、「サステナブルデザイン」こそ日本および日本企業の競争力を強化する最も有効な手段であるということだ。すべての経営資源をここに投入できれば、日本の未来は明るい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

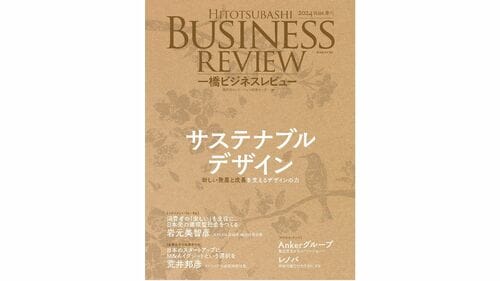































無料会員登録はこちら
ログインはこちら