「サステナブルデザイン」は競争力強化の有効手段だ 全ての経営資源投入できれば日本の未来は明るい
パトリック・ラインメラ(IMDビジネススクール ストラテジー&イノベーション教授)/米倉誠一郎(一橋大学名誉教授/デジタルハリウッド大学大学院特命教授)
ラインメラ/米倉論文は、産業革命以来の「連続生産工程」というテクノロジーが大量に生産しやすいデザインを求め、その結果生まれた大量の商品を大量に販売するためのデザインが考案された歴史を概観する。工業化の進展とともに、より豊かな社会を求めて「大量生産・大量販売・大量消費」というサイクルが拡大していった。
これに拍車をかけたのが、20世紀に入ってアメリカを中心に生まれた「計画的な陳腐化」なる戦略概念だ。必需品が満たされると、人為的に計画された「流行、トレンド、流行遅れ、陳腐化」という一連の煽動活動によって人々の欲望は刺激され、次々と消費が喚起された。まだ使える商品でさえ大量廃棄される事態が出現したのである。
その背景には、「広大なる地球は、人間の無謀な所業を受け止めて余りある」という暗黙の前提があった。しかし、母なる地球の寛容度は限界に達し、天変地異を通じて悲鳴を上げ始めた。ここに、「大量生産・大量販売・大量消費・大量廃棄」を前提としないサステナブルデザイン観が提唱され、それを実践する企業群が登場していることを紹介している。
欧米日の具体的な企業事例を取り上げながら、本論文が提起したのは、こうしたサステナブルデザインが新たな成長や経済発展と同義語であるという視点である。この楽観論には異論もあろうが、「楽観主義は意思に属する」のである。
第4の経営資源であるモノの戦略的有効活用を
似内志朗(ファシリティデザインラボ 代表)
似内論文は、ファシリティマネジメントの視点からサステナブルデザインを考えたものである。ファシリティマネジメントとは、組織目的のためにファシリティ(都市・建築・ワークプレイスといったハード面と、建築環境・働き方・ライフスタイルなどソフト面を含んだ総体)を取得(建設、賃貸、改修によって)し、それを運営・維持し、そのプロセスを評価しまた改善に向かうサイクルを回すことであるとされる。
いわゆる経営資源(人、カネ、情報)に続くモノ(ファシリティ)の戦略的有効活用のことであり、いまや「第4の経営資源」とも呼ばれるものである。本論文では、建物の企画・設計・建設・取り壊しという長いサイクルを、サステナブルにデザインすることの重要性を説いている。
経営学にとって最も注目すべき本論文の主張は、「人件費の10分の1にすぎないファシリティコストを考えれば、『富』の源泉である人の知を引き出すことができるファシリティへの投資対効果は高い」というワークプレイス観である。参考事例に挙げられている世界の先進都市の試みは知を生み出す人材(ナレッジワーカー)獲得競争であるという視点は、日本の都市開発をはじめとしたファシリティに対する考え方に新たな指針を与えるものである。

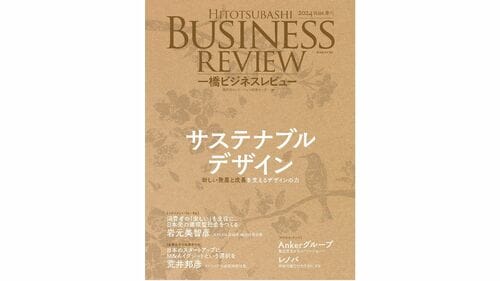































無料会員登録はこちら
ログインはこちら