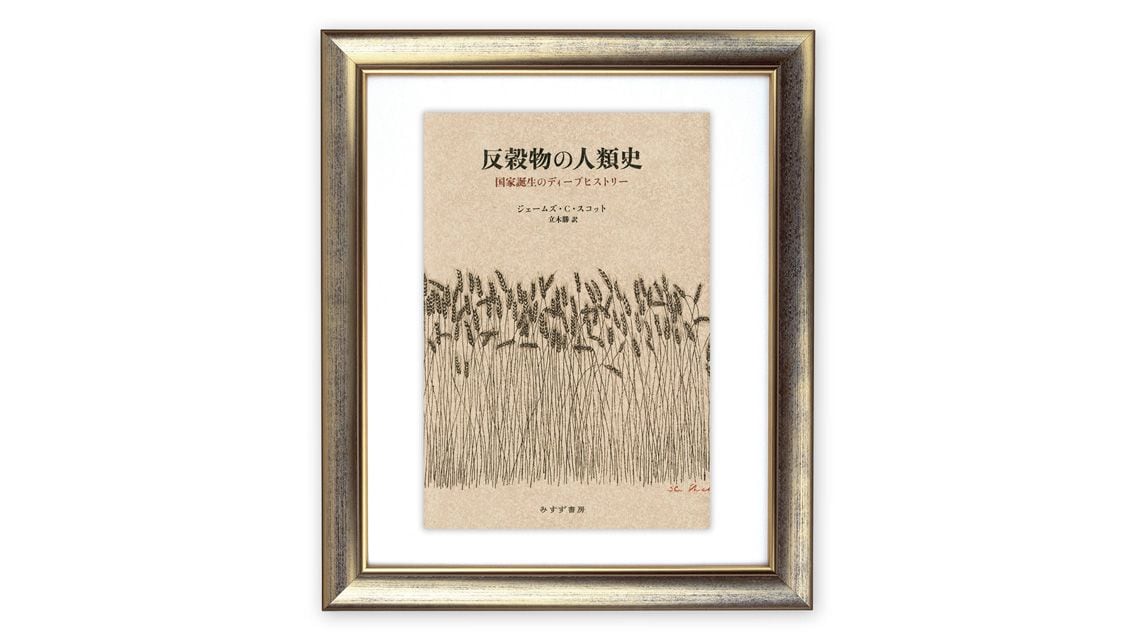
穀物栽培により、人類は土地に縛られ、国家に管理されるようになった。そしてもう1つ、深刻な問題が起こった。男性優位社会の誕生だ。
農耕生活における役割分担と代償
狩猟採集の時代にも、狩猟は男性、採集は主に女性といった大まかな役割分担はあったと思われるが、その関係は対等で平等なものだった。人類学者、ヘレン・フィッシャーは、使用に相当の腕力を必要とする農具の鋤(すき)が発明されたとき、生活の第1の担当者が男性に移ったとする。こうして、家(domus)の主人(dominus)として支配(dominatus)するのは男性となった。
女性に求められたのが、労働力確保のための頻繁な出産だ。狩猟採集民は、乳幼児を多く抱えての移動生活が難しいことから、出産間隔を最低4年ほど空けた。激しい運動をし赤身肉を食す生活スタイルにより、排卵は不定期で、妊娠可能期間も短かった。それが穀物食になったことで、初潮が早まり排卵が促進され、生殖寿命が延びた。離乳して軟食になるのを早めることも可能になった。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら