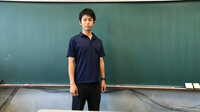1年の始まり「4月の学級経営」で大事なこと、バックキャスト思考のススメ 問題起こることを前提にベターな学級づくりを
これがかつてよりも多様化していることが、今の学級経営の難しさの要因になっています。教師が理想を掲げても、子どもに理解されなければ、教室内で教師が孤立することになります。また、子どもたちが互いのニーズばかり主張すれば、対立が絶えることなく、その陰で主張できない子どもは我慢の日々を過ごすことになるでしょう。
教師、子どもがそれぞれの願いに折り合いをつけて共に過ごす教室とはどのような姿なのでしょうか。学級経営に正解はないと思っていますが、今ある最適解として自治的集団や創発学級と呼ばれる姿を挙げてみたいと思います。
自治的集団とは、日常生活の諸問題などの話し合い活動などを通じて解決し、協力して実現する集団のことです。また、創発学級とは、自立した子どもが信頼に基づきネットワークを形成し主体的な活動を展開する学級のことです。
力点を置いているところや育成のプロセスは異なりますが、両者とも、子どもの主体性を尊重し、協力的な関係による問題解決や活動を行う点で共通点が見られ、それらは一定の秩序と相互承認などの信頼関係が基盤になっています。
現在、学級経営というと教師による管理や子ども同士の同調圧力などの問題が取り上げられていますが、日本の先生方は本来的には、教師が教え、子どもが教わるという縦型の役割関係を必ずしもよしとせず、子どもたちの開放的な関係性に基づく、子どもたちの自主的で自治的な活動で学級生活が展開されることを意図してきたという経緯があります。
現行の学習指導要領でも、特別活動や学級経営において「自発的、自治的活動」を重視しています。これは教師の指導を否定するのではなく、適切な指導の下に展開されるという意味で「的」という語句が入っていますが、教師主導の学級のあり方を推奨しているわけではありません。
ただ、学級経営を科学的に検証する視点が未成熟で、また教員養成、教員研修でも扱われることが少ないために、安易な管理的な学級経営が流布し、学級経営そのものを否定するマインドすら生まれてきているような状況もあります。
学級経営の本来の目的は、教育活動が円滑に進むように条件整備をすることです。しかし、古くは校内暴力、学級崩壊、近年はいじめ、不登校の増加などさまざまな問題によって、誰もが過ごしやすく学びやすい環境づくりをするという本旨が歪められてしまっているのではないでしょうか。