「ChatGPTの授業活用」で生徒の学びはこう変わる!教師が意識すべき3つの問い 英作文と総合探究の事例に見る「生成AIの利点」
一方で、生徒たちは生成AIにあまり興味を持っておらず、使ったことがないという生徒が大半です。それならば、生成AIに触れる機会を持つことが、生徒にとってプラスになるのではないかと考えています。
また、生成AIというと、課題などの「答え」をすぐに出してくれるツールとして捉えている人も多いかもしれません。もちろん、そうした一面があることは間違いないのですが、「答え」を一緒に作り上げる相談相手という面もあるのではないでしょうか。
相談相手として活用することにより、生徒がより深い学びを実現できる可能性も十分あると思っています。例えば前述のように、英作文を書く際に生成AIを使えば、「この単語の使い方をもっと教えて」「次の表現のニュアンスの違いは」といった相談を繰り返しながら、より自分の思いを伝えることができる文章を作り上げていくことができます。
私は冬休みに、生成AIと一緒に英作文を仕上げるという課題を出したこともあります。このように、家庭学習での活用も認められれば、新しい学びが可能になるでしょう。
最近では、プレゼンや意見交換、ポスター制作など、自分の考えや思いを伝える言語活動も増えてきています。その際、教師が支援を行うわけですが、1対40人の授業では限界があります。少しでも1対1の個に応じた支援を行うためには、生成AIの力を借りないと難しいでしょう。
このように生成AIを活用することで、これまで人手や時間の制限で実現できなかったことも可能になりますし、生徒の学び方は大きく変わっていきます。
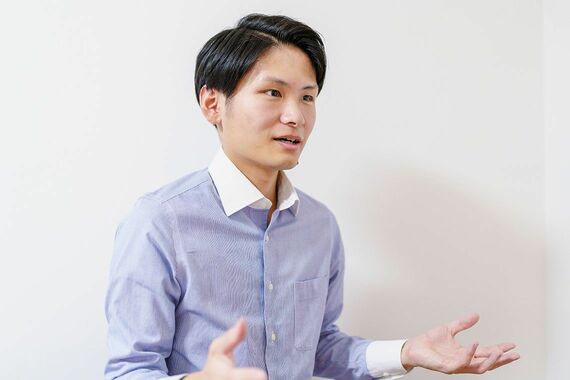
滋賀県立高校教諭
2018年より、滋賀県で英語科教諭として勤務。ICTを活用した教育に関心があり、2022年度には、滋賀県のICTコアティーチャーを務めた。最近では、ChatGPTを活用した教育に関して、単行本や雑誌記事の執筆などを行っている。著書に『ChatGPT×教師の仕事』(明治図書出版)がある
※本記事の内容は、あくまでも個人としての見解です
(画像と資料:南部氏提供)
関連記事
「劇的に仕事を効率化した教員の「ChatGPT」活用術 授業計画から問題作成、校務と幅広く使える」
執筆:南部久貴
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























