多様な子を前提に「教育のほう」変える、狛江第三小「あおば学級」の実践 環境を子どもに合わせるインクルーシブな学校
「『インクルーシブとは、単に“みんなで一緒に同じ教室で授業を受けること”ではなく“多様な子どもがいることを前提にして教育内容、指導方法、組織体制を変えていくこと”』など、野口先生の話を直で聞くと、通常学級の先生たちも、目から鱗なんですよ。『これがインクルーシブの考え方なんだ』ということがわかってくると、当事者である子どもを大事にしながら本人の意見を聞くことが必要であること、子どもの“好き”や“強み”がすべてのベースになることなどを改めて理解し、その価値観が学校全体に広がっていくんです」と話す荒川氏に、森村氏も続く。
「研修を受けた通常学級の先生が、『これまで子どもの苦手を何とかしなきゃとずっと思っていたのに、子どもの強みを見つける思考にシフトすることで、気持ちがすごく楽になりました』とおっしゃっていたのが印象的でした」
校内研究が終了した後も、森村氏を中心に教職員有志が自主的に「インクルーシブ有志の会」を発足。2023年度は研修会を年に3回、有志の会を年に12回、あおば学級を会場に開催しているという。指導教諭も務める森村氏は、こう話す。
「1回目はカフェ風にしてお茶を飲みながら、2回目は焚き火をテーマに教室にテントを張り、キャンプ場風の空間を作って開催しました。インクルーシブをテーマに『学校は多様な子どもたちがいることが前提となっているか』ということについて皆で徹底的に考えたのに加え、先生たちの対話の場としても活用し、困っていることや悩みを打ち明けたり、お互いの強みを認めあったりしています。
子どもたちだけでなく、先生たちも自身の強みを生かしながら教育活動に取り組んでいけたらと話しています。とはいえ、今学校は多忙で私自身も含め、先生たちも苦しい面もある。個人の努力や頑張りを求めるだけではなく、構造上の問題や苦労についても声を出していいんだと思えることが大事だと感じています」

学芸会で、あおば学級の児童が撮影・編集した特別支援学級の紹介動画を全校の児童や保護者に見てもらったりなど、特別支援教育の理解啓発にも力を入れる。
通常学級の児童から「あおば(学級)のイスにすわってみたい」という声があがり、あおば学級で授業を行ったり、通常学級のキャリア教育に森村氏が実践している「自分研究」のアイデアを取り入れたり、特別支援の外部専門家と通常学級が連携した授業や通級指導教室で用いている教材を職員室におき、通常学級の先生が必要に応じて授業で活用したりなどの取り組みが、校内にじわじわ広がってきているという。
「副校長先生も、通常学級の児童が使う廊下の一角に、気持ちを落ち着かせたいときに一時的に入るクールダウンの個室を作っていらしたんです。すばらしいなぁと思いました」(森村氏)
取材で訪れた狛江第三小学校は、目には見えないけれども、学校全体が温かで、明るく澄んだ空気に包みこまれているように感じた。
特別支援教育には、学校教育全体、そしてインクルーシブな教育において大切にしたい要素が数多く存在する。そして、学級の枠を超えた交流は、すべての子どもが安心して学び、成長できる学校を作るための土台であるといえるのではないだろうか。
(注記のない写真:長島ともこ撮影)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら





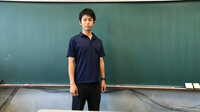


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら