多様な子を前提に「教育のほう」変える、狛江第三小「あおば学級」の実践 環境を子どもに合わせるインクルーシブな学校
「『ゲームが好き』という子とゲームについていろいろ話しているうちに、一人でプログラミングができることを教えてくれました。それを校長先生に話したら、プログラミング教育を通じて人材育成を行っているNPO法人『WRO Japan』とつないでくださり、連携してロボットプログラミング授業を行いました。
思考錯誤を繰り返しながらプログラミングでロボットを動かしたり指定コースを走らせたりすることを学ぶうちに、オリジナルのゲームを作って友達に楽しんでもらい、人の役に立ったり認められたりする経験を重ねることができました。ただ、これはあくまでも1つの成功例。うまくいかないことも、日々山ほどあります」(森村氏)

(写真:狛江第三小提供)
感情を言葉に表すことで、困りごとの解決につなげる
森村氏が日常的に実践しているのが、「感情を言葉に表すこと」だ。
「毎日朝の会で、子どもたちに、今日の感情を言葉に表してもらっています。グループで行うこともあり、ある子の『今日は疲れている』という言葉に対し、ほかの子が『心が疲れているの? それとも体が疲れているの?』と聞くと、その子は『いや、こんなことがあってさ』などと話すことで、少しずつ周りに自分のことを理解してもらったり、自分自身も感情のコントロールがしやすくなっていきます」と言う。
「例えばある子が『嫌だー!』と叫んだとき、そのままだと、その子はすべてが嫌だと感じたままになってしまうことがあります。本人とできる方法で『いつ嫌だったの? どう嫌だったの? 誰が嫌だったの?』など、嫌のおおもとを分解しながら聞いていくと、嫌な部分が実は全部ではなく限定的なことだったりすることもあります。それを解決する方法を、一緒に考えていきます」
感情表現が苦手で、ことあるごとに「うるせえ!」「あっちいけ!」などと叫び、ときには暴力をふるう児童がいた。時間をかけて少しずつ自分の感情を言葉で表せるよう関わるうち、その児童は“音”が苦手でうるさく感じ辛かったことがあるとわかった。
そこで、うるさい、嫌だと感じたときや心が落ち着かないときに、一人で安心してこもれる部屋を相談して教室内に作るなどの関わりを続けたところ、暴力をふるわなくなったという。
森村氏は、2012年に東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎氏と出会い、当事者研究の試みを参考に、子ども自身が困っていることや学び方などを自分で研究し、先生や仲間と一緒に対処法を考えていく「自分研究」という活動を行っている。
「自分自身が困っていることを分析し、『泣き虫ゴースト』『イカリボール』などとキャラクター化する→キャラクターに対する対処法を自分で考えたりグループで話し合ったりする→対応を実践しながら、最後に発表する」など、その子に応じたプロセスで取り組んでいるという。
「目に見える行動や表情だけではわからない気持ちもあります。子ども自身が表現する手段を持つことの大切さ、大人が子どもから謙虚に学び、子どもから見える景色について想像力を働かせることの大切さを日々実感しています」(森村氏)
「インクルーシブな学校づくり」を校内研究のテーマに
狛江第三小では、2022年度、インクルージョン研究者で一般社団法人UNIVA理事の野口晃菜氏を迎え、学校全体でインクルーシブな学校づくりの研修を行った。荒川氏は言う。
「本校では2021年度、文部科学省からの依頼で、特別支援教育に関する実践研究を行いました。そのときに専門家に伴走いただいたのですが、インクルーシブな教育の知見がすばらしく、非常に参考になったのです。通級指導学級と特別支援学級の専門性を高めるためだけの学びにとどめるのはもったいないと、2022年度は通常学級の先生もまじえ、学校全体の校内研究のテーマにしました」
同じ校内にいるのに、通常学級と通級指導学級・特別支援学級は、児童も教職員も交流が少ないことが多い。荒川氏は着任時から「チームKOMA3(狛江第三)」を合言葉に、専用の職員室にこもってしまいがちな通級指導学級・特別支援学級の教職員に、授業の合間や放課後はメインの職員室に戻るよう声をかけるなど、対話の機会を作り続けてきた。




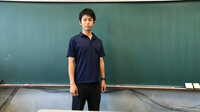


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら