多様な子を前提に「教育のほう」変える、狛江第三小「あおば学級」の実践 環境を子どもに合わせるインクルーシブな学校
タブレットやアバターロボットで「つながる」
狛江市の通常学級では、2020年10月に1人1台のタブレットが配られたが、あおば学級では2018年から利用を始めた。

狛江市立狛江第三小学校校長
公立小学校教諭として12年勤務した後、東京都総務局人事部及び教育庁学務部の課務担当係長、教育庁指導部統括指導主事、教職員研修センター統括指導主事、主任指導主事、教育庁総務部教育政策担当課長等を経て2018年から現職
「対面でコミュニケーションを取るのが苦手な子たちなので、学校に来られなくてもタブレットをツールとして学校とつながってもらおうと、全員持ち帰りOKとしました。ただ、タブレットを渡したから子どもたちとすぐに画面越しでつながれるのかと言ったら、そんな簡単な話ではなくて。
画面越しに信頼ある落ち着いた先生がいるからつながれるわけで、最初は『今日、元気?』など文字だけのやりとりから始まり、少し慣れたら自分の代わりにぬいぐるみを置いて話すなどしながら、少しずつ距離を縮めていきました。顔を出して話せるようになるまでに時間がかかることもありましたが、その子にとっては大きな進歩であり、この積み重ねが保護者の方の理解や信頼につながっていきました」(荒川氏)
2022年秋からは、アバターロボットも使い始めた。提案したのは、森村氏だ。

(写真:狛江第三小提供)
「感覚過敏があって家から出られず、学びたいけれども顔を出すことも不安で難しいという子がいました。本人が学校と楽しくつながれる方法を探していたときに、研修会で『アバターロボットkubi』の存在を知ったのです。
特別支援学級では使用例がなかったのですが、ぜひ試したいと校長先生に相談したところ、『どんどんやってください』と。何かを新しく始めようとするとき、『それは難しいんじゃない?』と言われてしまうこともあるのですが、すぐにGOサインを出してくださる校長先生の存在は非常に大きいですね」(森村氏)
ICTを活用し、自宅から算数の授業に参加したり、あおば学級の教室から通常学級の理科の実験に参加したり、図工の工作に取り組んだり。子どもたちは、森村氏のサポートのもと、オンラインで自宅と学校、特別支援学級と通常学級がつながり、自分に合う方法を試しながら授業に参加している。
また、東京芸術大学の先生と連携し、リモートで「香りの開発」の共同研究にも取り組んだ。その後、東京芸術大学と香料会社と児童が共同で、新しい香りを開発したという。
「ICTは、子どもの可能性を広げる道具の1つ。自分には無理だと思っていたことが、ICTの活用によりできるようになることで、『これまで自分はダメな子、できない子って思っていたけれど、“やり方”を工夫すればできるんだ』と気づき、自信につながるんです。それを積み重ねていくと、子どもは変わっていきます」(森村氏)
本人の「好き」から始める
「特別支援学級は、本人の苦手なことやできないことへのアプローチが多いんですよね。『苦手の克服』は、特別支援学級の自立活動の教育課程にも出ているのですが、そのためにはまず本人の『好き』から始めることを大切にしています。その子が好きなもの、得意なもの、心地よいと感じているものについて本人と保護者の方に聞き、それらをリソースとして学級経営や授業に取り入れています」と、森村氏は話す。
「学校なんか壊す!」と激しい言葉を発したり、言葉の代わりに暴力をふるう子も少なくないというが、時間をかけてその子と向き合い、「好き」を把握する。




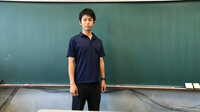


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら