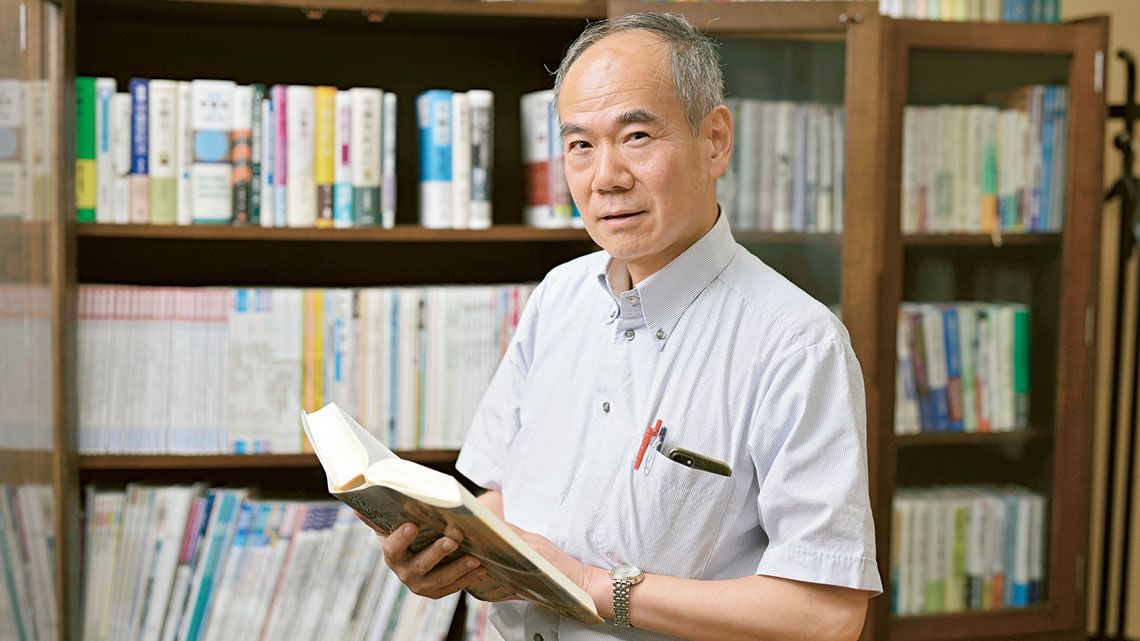
──これまで「メンバーシップ型」「ジョブ型」と雇用システムを大きな枠組みで捉えてきた濱口さんが、ピンポイントで家政婦を取り上げるとは意外でした。
労働問題のメインストリームから見れば傍流のトピックかもしれません。でも自分としては、ジョブ型雇用について論じることと焦点の合わせ方が大きく違うとは思っていないんです。家政婦という存在は小さなものだけれど、その小さな穴からのぞき込んで見えてくる映像には広がりがあります。
──家政婦に着目したきっかけは。
2022年9月に下された家政婦の過労死をめぐる判決です。ある家庭に泊まり込んで7日間働いた後に亡くなったのは過労死だとの訴えを、東京地裁は退けました。「『家事使用人』だから、過労死認定の根拠となる労働基準法などの適用除外」という理由です。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら