北海道初の公立夜間中学から見える、学びたい人の「ニーズ」と社会の変化 「ここは変わっていく学校」校長が語る予想図は

想像以上の入学希望者に「学び直しへの地域の期待を実感」
以前は戦後の混乱期に義務教育を受けられなかった人などが主な対象だった「夜間中学」。一時は大きく数を減らしたが、現在、文部科学省では再びその拡充を急いでいる。不登校の子どもや外国にルーツを持つ子どもの増加など、社会情勢の変化により、夜間中学には新たな役割が生じたからだ。2023年4月現在、23の都道府県と指定都市に44の公立夜間中学が設置されているが、25年度までにさらに13の都道府県と指定都市で新たに夜間中学を開校する予定だ。
こうした流れの中、22年4月、北海道で初めての公立夜間中学となる札幌市立星友館中学校が開校した。義務教育の年齢を超えた15歳以上を対象にして、同市立資生館小学校の敷地内に設置されたものだ。初代校長に就任した工藤真嗣氏は、初年度の入学者について次のように語る。
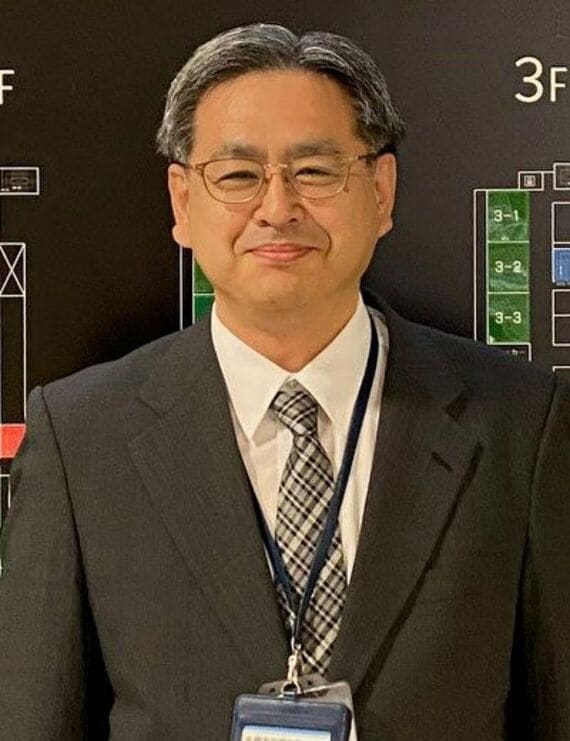
「ほかの夜間中学の平均から考えて、集まるのは60人ぐらいかと予想していました。しかし開校はメディアにも取り上げられて話題を呼び、前期期間中なら年度途中の入学も可能なことから、入学者は想像以上に増えました。昨年度末時点で89人が在籍していましたが、今年の入学者はさらに増えて100人を超えています」
北海道は、義務教育の未修了者が全国でも多い自治体だ。とくに戦後の混乱や家庭の事情で学校に通えなかった人が多いため、高齢者の学び直しのニーズもまだまだ高い。
「戦後すぐに公立夜間中学が設置された地域の学校に比べ、今の本校には70代以上の方が多数集まっています。学び直しをしたいという思いを持って開校を待ち望んでいた方が多く、地域の期待が大きいのだと実感しています」
開校バブルともいえるような活況を、工藤氏はそう分析する。札幌市およびその近郊の12市町村と、同校のカバーエリアは広い。遠いところでは苫小牧市から通う生徒もいるそうだ。
一方で、外国にルーツを持つ人の割合は1割程度と、こちらは全国平均に比べて低めだ。年齢層で見ると10~20代の若年層は3分の1ほどで、4割を占めるのは30~60代の大人たち。若者はたくさんの「人生の先輩」と一緒に学んでいる状況だという。
工藤氏は「若年層の生徒は100%、昼間の中学校での不登校を経験しています」と言う。
「考えてみれば、学校って非常に特殊な環境ですよね。同じ年齢の人間だけがいる均質な集団で、学習の効率はいいけれど、大人になったらそんな場所で過ごす機会はめったにありません。そうした意味で、本校はまさに社会の縮図です。『同じ年の子の集団の中でどうしたらいいか、前の学校では自分の身の置き方がわからなかった。でもここならいろんな人がいて何だかなじみやすい』と話してくれた10代の生徒もいます」






























