「蓑手章吾×川上康則」&「戸ヶ﨑 勤×今村久美」が語る、これからの学校のあり方 子も教員も自由に、前例にとらわれない改革を

▼アーカイブ動画はこちらから
(申込期限:2023年10月25日、視聴期限:2023年10月30日)
https://toyokeizai.net/sp/sm/summerfestival2023_archive/
【Talk Session1】
「大人都合」の学校からの脱却-足並みそろえさせない!令和の学校づくり-
東京都の公立小学校で14年間教員を務めた後、オルタナティブスクール「HILLOCK初等部」のスクールディレクター(校長)に就任。2023年9月代々木校を開校。東京学芸大学の非常勤講師(「教育の情報化基礎」の授業を担当)、文部科学省DX推進委員、デジタル庁デジタル推進委員も兼任。著書に『個別最適な学びを実現するICTの使い方』『子どもが自ら学び出す!自由進度学習のはじめかた』(ともに学陽書房)など
公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士スーパーバイザー、一般社団法人日本授業UD学会理事などを務める。著書に『こんなときどうする? ストーリーでわかる特別支援教育の実践』(Gakken)、『子どもの心の受け止め方』(光村図書出版)、『教室マルトリートメント』(東洋館出版社)、『不適切な関わりを予防する 教室「安全基地」化計画』(東洋館出版社)など
「自由進度学習」で子どもたちが学習意欲と自信を取り戻す
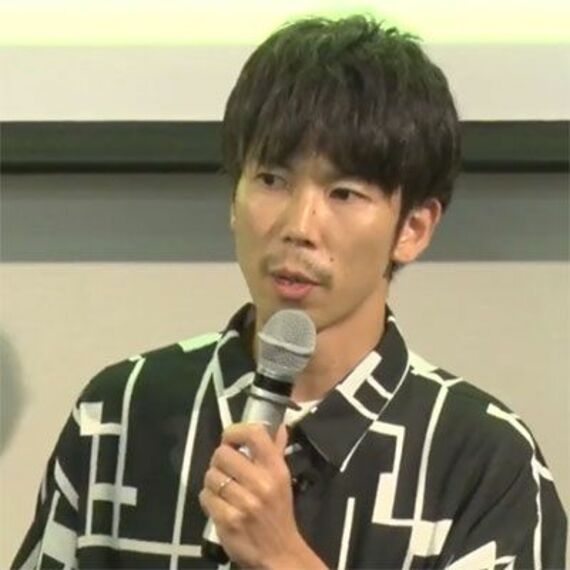
蓑手氏は教員7年目で杉並区立済美養護学校に赴任。発達段階に大きな差がある子どもたちの学びのために試行錯誤する中で、自由進度学習を導入した。その後も公立小学校の通常学級や、自身が創設したHILLOCK(ヒロック)初等部で取り組みを続けている。
自由進度学習について蓑手氏は「例えば5年生の通常学級では同じ教室に、算数の掛け算ができない子もいれば、高校3年生レベルの数学まで進んでいる子もいる。それぞれが手応えを感じる課題を選び、そのチャレンジを互いにリスペクトして一緒に学ぶ」と説明する。実際に算数でつまずいて学習意欲を失っていた小学5年生が、1年生の繰り上がり足し算に戻って学び直したことで自信を取り戻した経験から、「学習性の無力感は回復できる」と語る。
自由進度学習において、教員の役割は従来の「知識を与えること」ではなく「子どもの特性に応じて学び方を教えること」だと蓑手氏は話す。ヒロックでは、例えば運動会のプログラム作りなどを通して数字の便利さに気づく探究的学習と、算数のトレーニングをする自由進度学習とのループで、子どもたちに学びの楽しさを感じてもらうという。子どもたちは同じ教室の中で、自身の関心に合わせて教科にこだわらず学んでいる。
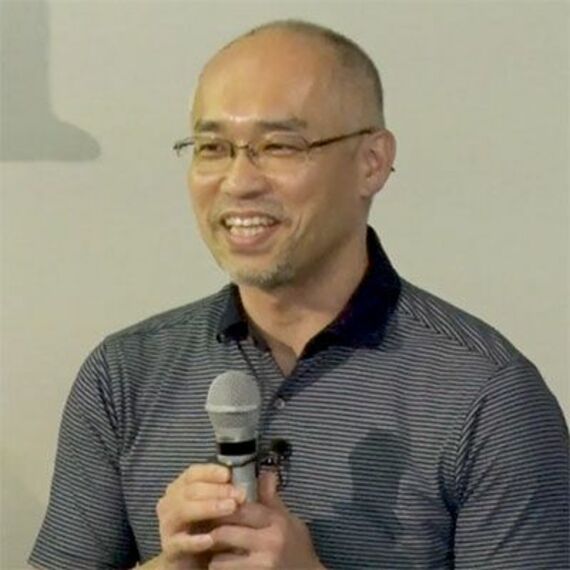
川上氏は、「子どもの習熟度の差は思った以上に大きい」と話す
「IQ」とは精神年齢を実年齢で割ったパーセンテージで、実年齢と精神年齢が一致すればIQは標準値の100だ。ここで知的障害と判断されるのは、IQ 70未満。つまり通常学級はIQ70〜130程度の子どもたちで構成され、小学4年生(10歳)なら精神年齢が7〜13歳の子が同じ授業を受けることになる。川上氏は「そもそもそろっていないものをそろえようとすることに問題があるのでは」と指摘した。
教員の余裕のなさが引き起こす「教室マルトリートメント」
子どもたちが自分の興味を探索するには、安心して戻ることができる「安全基地」の役割を教員が果たすことが重要だと川上氏は語る。しかしながら、逆に教員が子どもにいら立ち、不適切な指導をしてしまう「教室マルトリートメント」が起きている実態があるのも事実だ。問題のある状況を早く解決したいという焦りや自信のなさ、不安などの感情に、業務の多忙さや周囲とのコミュニケーション不足といった環境要因が加わり、追い詰められた教員が子どもに不適切な関わりをしてしまうと川上氏はみている。






























