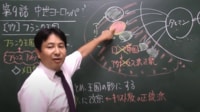大学入試は「歴史総合」が潮目、高校授業に期待する「歴史実践」の神髄は ルーブリック採点など工夫、正解つくると危険
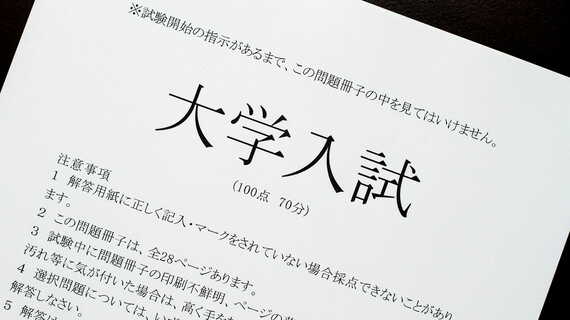
大学も高校の歴史総合に「期待」、知識よりも面白さを重要視
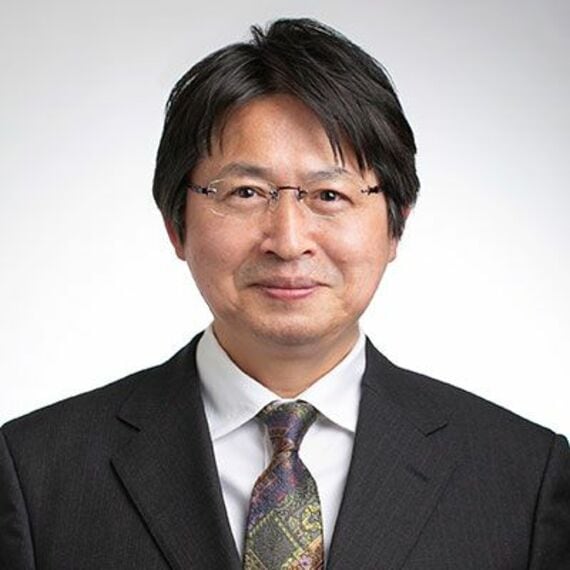
一橋大学大学院 社会学研究科 教授
人間文化研究機構 理事
日本学術会議 会員(第24期、25期)
専門は日本近世史・思想史研究
(写真は本人提供)
高校の新必履修科目である「歴史総合」では現在、生徒らは19世紀以降の歴史を「近代化」「国際秩序の変容と大衆化」「グローバル化」の3軸で捉えて学んでいる。教授内容重視(コンテンツベース)から転換して資質・能力重視(コンピテンシーベース)、つまり従来の知識詰め込み型から思考力を重視した歴史教育へ移行し始めたわけだが、大学側はこれをどう受け止めているのだろうか。一橋大学大学院社会学研究科教授の若尾政希氏はこう語る。
「歴史で重要なのは知識ではなく、しかるべき情報から何を考えるかです。私は大学で、高校での知識詰め込み型の歴史教育と、大学での歴史学習とは大きく異なることを常々伝えてきましたが、まさに高校から歴史的思考力が重視されることは歓迎すべきことだと捉えています」
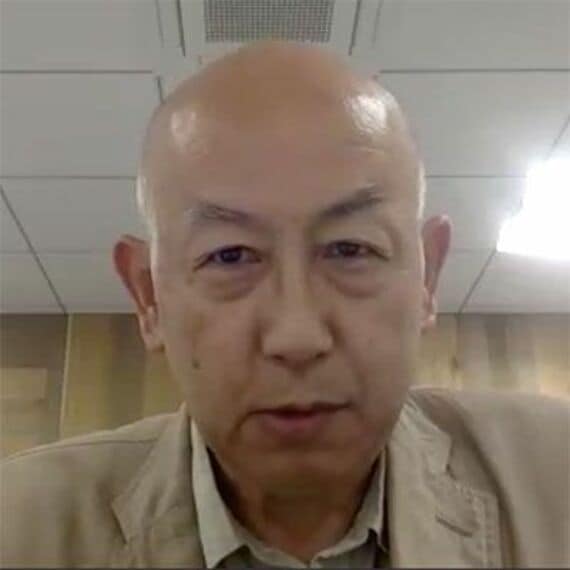
東京外国語大学名誉教授
名古屋外国語大学世界共生学部 学部長 教授
日本学術会議連携会員
専門は歴史学・ブラジル史・ラテンアメリカ地域研究
(写真は東洋経済撮影)
東京外国語大学名誉教授で現在、名古屋外国語大学教授を務める鈴木茂氏も、知識詰め込み型の教育には懸念を抱いてきた。
「高校生には歴史は暗記ものだという固定観念があります。しかし、歴史は考えるための素材であり、覚えるものではありません。歴史総合で学ぶ近現代は、世界の中に日本を位置づけられる時代ですから、大学教育にとっても非常にありがたいです」
大阪大学名誉教授で現在、ベトナム国家大学日越大学教員を務める桃木至朗氏は歴史総合への期待をこう述べる。
「ベトナムでも歴史教育については日本と似た状況にあります。私は日本学を教えていますが、単に日本史を教えるのではなく、学生たちが世界の中で日本とベトナムを捉えたり、学んだことをベトナムにどう生かすかを考えたりできるよう多角的な視点を重視しています。日本でも若者が世界に出る前に歴史総合で多角的な視点を得られることには意義があるでしょう」

大阪大学名誉教授
大阪大学歴史教育研究会 顧問
専門はベトナム史・海域アジア史・歴史教育
(写真は本人提供)