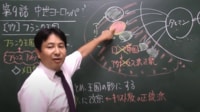大学入試は「歴史総合」が潮目、高校授業に期待する「歴史実践」の神髄は ルーブリック採点など工夫、正解つくると危険
「すでに25年度からの問題に関する議論は始まっています。知識を問うだけの問題は控える配慮が必要なこと、資料やデータを読み込むプロセスを評価する問題を入れることなどが話し合われています」(若尾氏)
とはいえ、思考型や自由記述型の問題は採点の面で大学側にも大きな負担がある。実際どうなのだろうか。桃木氏が語る。
「確かに過去にも、論述問題で大学側が期待した回答が出ず、平均点が下がったという話があります。よい答案がなかったため、結局は多く知識を並べたほうが高得点という本末転倒な事例も発生していました。そうした反省を踏まえ歴史総合では、すべてを論述にするなどの単純な改革ではなく、まず基礎的な知識問題を出したうえで、それらをヒントに関連する論述問題で思考力を問うといった形式がよいのではと考えています。採点方法も単純な点数加算減算方式ではなく、例えば安定的な採点ができるルーブリック(評価基準)などを設ける必要があるでしょう」
現在も試行錯誤が続くが、歴史総合の入試問題については高校と大学が議論する場の必要性も指摘されてきた。実際に、23年8月5日に高大連携歴史教育研究会が開催され、高校と大学の教員が参加して議論が行われたばかり。入試部会の責任者を務めた鈴木氏が言う。
「これまでは歴史総合をいかに科目化、入試化するかを考えてきましたが、今年は入試内容にとくに大きな影響を与える大手私立大学の歴史総合の対応も議論したいと思っていました。実は、大学の歴史研究者で歴史教育に詳しい者はそう多くいません。だからこそ、志を持った高校と大学の教員が自主的に集まり、議論する場を持つことが非常に重要なのです」
始まったばかりの歴史総合だが、生徒の「歴史実践」はもちろん、高校教育や大学入試の改革に大きな可能性を秘めているのは確かだ。最後に改めて、これからの歴史総合に期待するものを3氏それぞれに語ってもらった。
「日本の歴史教育はこれまで『the history』でした。同じ歴史でも人によって捉え方や見方は異なります。私たちが学ぶ歴史はそのうちの1つ『a history』にすぎないのです。物事には唯一絶対の正解があるわけではない。その中で、私たちは良識を持って人生や社会をつくっている。この感覚を伝えられる歴史総合になってほしいですね」(桃木氏)
「歴史総合の目標は知識の暗記ではありませんから、ぜひ歴史の面白さに気づく科目にしたいですね。一部の高校の先生方はすでに実践されていますが、生徒自身の『知りたい、学びたい』という意欲をかき立てる授業をしてほしい。大学側もそうした思いを引き取って、今後の入試に反映させていこうと思います」(鈴木氏)
「歴史を学ぶことは、私たちが生きていくうえで必要不可欠です。自分がどう生きればよいのか、そして、社会や国のあり方をも見えてきます。世界の中の日本についてしっかり理解するためにも、歴史総合が生徒たちに歴史の面白さと大切さを伝える科目になればと願っています」(若尾氏)
(文:國貞 文隆、注記のない写真:tetu / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら