GIGAスクール3年目、文科省・武藤久慶が語る「1人1台端末を使い倒す」重要性 地域・学校で顕著な差、基本操作に難ある子も
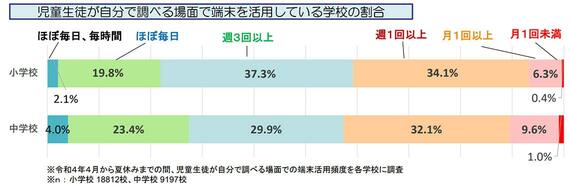

校務で活用を始め、授業で生かしていくのが最もスムーズ
――そうした地域間、学校間の格差を受け、とくに課題だと思われる点は何でしょうか。
ICT化は、一足飛びに進むものだとは思っていません。とにかく使ってみることが重要ですが、まずは校務での活用を始め、授業で生かしていくのが最もスムーズかもしれません。
例えば教師間で教材をクラウドで共有する、紙のアンケートをデジタル化することなどはすぐできるはず。それに慣れれば、授業でもクラウドやアンケート機能を使って子どもたちの意見をみんなで共有するといった活動もできるようになるでしょう。また、クラウド上で付箋ソフトを使うなどして協働的な教員研修をやってみると、さまざまな意見が可視化され、非常に民主的かつ効率的に議論ができることを実感できると思います。「ああ、こういう感じか」となれば、「子どもたちともやってみよう」と思えますよね。
子どもと教師の1人1台端末に搭載されているアプリやクラウドをフル活用すれば、お金をかけなくてもできることはたくさんあります。例えば、職員会議のペーパーレス化やリモート会議なども簡単にでき、育児や介護をしている先生も含めてもっと働きやすくなるはずです。
保護者とのコミュニケーションは校務以上にICT化が進んでいませんが、こちらも児童生徒の欠席連絡や保護者面談の日程調整、お便りなどの配布は今の環境ですぐにICT化でき、保護者のニーズも強いはずです。例えば、PTAや保護者会をリアルとオンラインのハイブリッドで行う学校もまだ約2割ですが、実施すれば仕事の合間に参加できるご家庭が増え、先生方もより多くの保護者とコミュニケーションが取れるようになり、双方にメリットがあるわけです。
ただ、校務については、ネットワークの問題、OSやソフトウェアの課題などによってサクサク動かない、あるいはいまだにシングルサインオンになっていない場合もあるでしょう。そこは自治体が状況をアセスメントし、教員や子どもたちが日常的にICTを使える環境に整える必要があります。私たちもOS各社をはじめ、関係企業に改善を強く働きかけていますし、アセスメントに財政支援もしています。
校務支援システムについては8割の学校が導入していますが、閉鎖的なネットワーク上に置かれており、現在は職員室でしか利用することができないケースがほとんどです。これを今後4~5年以内に、全国的にクラウドベースのシステムにリプレースして、校務系と学習系のデータを統合してダッシュボードも実装し、データの力も使った指導の充実や教員の働き方改革につなげていきたいと考えています。
――授業での端末活用については、格差解消に向けてどのような対策をお考えですか。
今年度は、新たに「リーディングDXスクール事業」を展開します。これは全国100カ所で小中学校をペアで指定し、1人1台端末とクラウド環境を使い倒していただき、その活用状況を把握・分析するとともに、効果的な実践事例を創出・モデル化する事業です。ICTアドバイザーの活用も含め、1校につき年間200万円の予算を用意しています。さらに希望する自治体には非常勤の教育CIO(最高情報責任者)やICT支援コーディネーターの設置も可能としています。
指定校には、周辺に設ける連携協力校や有識者とともにワークショップや講演などにも取り組み、実践事例を発信していただく。そんな形で好事例を全国に広めていきたいと考えています。






























