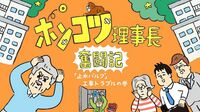成績だけで「やりたいこと」諦めないで、全国初「AI活用」した入試改革は 立命館×atama plus「入試改革」1年目の通信簿
また高校では2022年度から新学習指導要領が実施され、改訂のポイントとして、すべての教科において育成すべき資質・能力を、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の3つの柱で再整理。これまで大切にされてきた「生きる力」を育むという目標はそのまま、社会の変化を見据えた新たな学びへの進化が目指されている。
「UNITE Program」では、「atama+」を利用して基礎学力を客観的に評価・担保しつつ、「生きる力」を総合的に高めることを意図してきたようだ。
熊谷:「生きる力」を身に付けるために基礎学力は必要不可欠で、そのうえに学びに向かう力がある。ここのモチベーションを上げる入試にするためにはどうしたらいいかを考え続けてきました。
——学びに向かうモチベーションを上げるには、何が必要とお考えでしょうか。
熊谷:自分のやりたいことや夢に確実に向かっているという感覚です。入試に必要だから頑張れというのと、将来やりたいことに必要だから頑張れというのでは、モチベーションが全然違いますよね。ただ「数学が大事だよ」ではなくて、要するにそれを学んでおかないと入試のもっと先、自分が将来やりたいことを実現させられないということがわかれば子どもたちも動くと思うんです。将来の夢に必要な教科・単元は何かを学生は知るべきだし、大学側は入試を通じて提示する必要があると思っていました。
経済学では、政策を考える際に、実際に経済を動かす代わりに数式を使って人がどのような行動を取るかを予測・シミュレーションしますが、その際に「微分」の知識が必要になります。知り合いの高校教諭の方に、「『経済学部は数学の勉強しなくていいんでしょ』と生徒に言われたとき、こういう入試があると、なぜ数学が必要なのか、将来にどう生きてくるのかを伝えやすい」と言っていただきました。
「受験のため」という近視眼的な思考にとらわれては、生徒の大事な人生のためにならない。高大接続の議論は、まさにこうした課題を解決するためのものでしょう。
大学側としても、今回は各学部に本当に必要な教科、科目はもちろん、その中でもどの単元が生徒の将来に生きてくるのかということを真剣に考えてもらうことで、改めてアドミッションポリシーや、高校生へのメッセージを明確化させることができたのではないかと思っています。
・学校ではあまり触れなかった単元もあったため、新たな知識が増えた
・指定単元の範囲の模試やテストの成績が良くなった
・今まで数学を何に使うか理解できなかったが、経済学に繋がっていると考えると数学に対する意識が変わり、意欲的に学ぶようになった
・数学を解くのが楽しくなった、強みになったと感じた
出所:立命館大学の資料を基に東洋経済作成
——現在対象となっている学部は、経済学部・スポーツ健康科学部・食マネジメント学部ですが、ほかの学部や立命館アジア太平洋大学(APU)の入試にも、プログラムを広げていく予定と伺いました。
熊谷:2024年度からは薬学部で、化学の単元において実施することが決まっています。多くの学部生が目指す薬剤師の養成課程において、とくに大事な単元は何かというのを学部で議論してもらいました。
そのほかの学部にも、今後広げていく予定です。例えば理工学部の電気電子工学科なら電磁気の知識が重要ですし、機械工学科なら力学、環境問題に関連した研究をするなら、物理だけでなくて化学も必要など、より深掘りすべき単元であったり、見落としがちだけど必要な単元を議論したうえで、高校生に伝えていきたいと思っています。