初任者教員をどう育てる?カギとなる「ベテラン教員を巻き込む方法」とは 「現状は異常事態」現場教員が警鐘鳴らすワケ

電話応対から出席簿のつけ方まで必須の知識を身に付ける
4月。全国の学校ではたくさんの新1年生が入学式を迎えたが、学校という未知の世界に踏み出したのは子どもたちだけではない。3月に大学を卒業し、新社会人になったばかりの初任者教員たちもまた、学校における「新1年生」である。
東京都の東久留米市立東中学校では、主幹教諭である松田八幸氏が中心になり、同校に赴任した初任者教員や若手教員へさまざまな教育を行っている。

(撮影:梅谷秀司)
例えば電話応対について。これは業種・職種を問わず、新社会人が苦手意識を抱きやすいものかもしれない。そのため一般企業では電話のマナー研修を実施することも多いが、学校という職場ではなかなかそうもいかない。
松田氏は初任者教員を「電話に出たほうがいいのだろうと思う反面、自分が取っていいのか、どんなふうに答えればいいのか、ほかの教員につないでいいのかもわからない。この学校という組織のルールを、彼らはまったく知らないわけですよね」と語る。そもそも彼らはまだ、社会のルールもあまり知らない存在だともいえるだろう。そこで同校では、電話応対のための懇切丁寧なマニュアルを用意。「身内には敬称をつけない」「聞き取れなかったときの対処法」など、社会人としての基本的なマナーから詳しく解説する。
また、出席簿のつけ方や自己申告書の書き方も指導している。自己申告書は教員が1年間の目標を立てて校長や副校長とも共有し、自己評価の基準にするものだ。
「出席簿は担任を持つまで書くことがないケースも少なくないため、人によっては2年目、3年目までやり方を知らない場合もあります。初任者の時期を逃すと余計に学びにくくなるので、本校ではこれもきちんと時間を取って教えています」
ほかにも、評価の出し方や成績のつけ方、生徒指導の仕方や家庭との情報共有、連絡の方法なども教える。こうした知識は教員にとって必須のものであるにもかかわらず、具体的な指導を受けるチャンスはほぼない。松田氏は実際の事例や自身の経験を基にした資料を作成し、彼らと話し合う機会を設けているのだ。
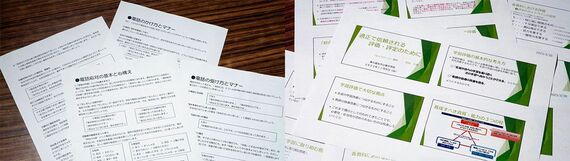
(撮影:梅谷秀司)






























