成長するのが楽しいからやる!子どもが自己調整で「自立して学ぶ」学校の仕掛け 何がどう違う?オルタナティブスクールの学び
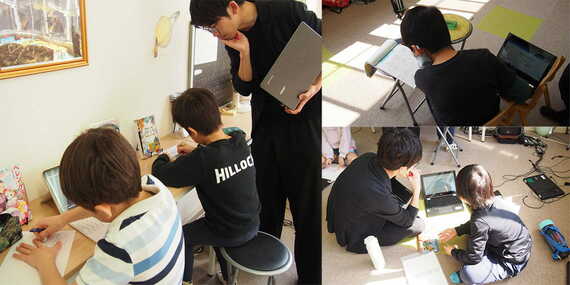
この日の午前中は、自由進度学習の次にゲストティーチャーが授業を行う「自由」、その後に「思考と言語」という時間割だった。「思考と言語」では架空の物語を作り、完成させた物語を互いに読み合ってフィードバックをしていた。ランチは「外で食べたい」という子どもたちの提案を受けて、シェルパも一緒に全員で元気に砧公園に出かけていった。
学年もテストも競争もない学校をつくった理由
小学校ならば当然のようにある教科別の時間割も学年もないヒロック。この学校をつくった理由を、公立小学校の教員としてキャリアを積んだ蓑手氏はこう話す。
「公教育の現場はやらなければいけないことが多すぎて、本質的にやるべきことの優先順位が低くなりがち。本来やるべき、子どもが育つ力、成長する力を身に付けられる環境を整えることをど真ん中に据えた学びの場をつくりたいと思いました。時間割、学年制、成績やテスト、比較競争があると、学びの楽しさがねじれてしまう。それらを全部なくしたとき、学習者である子どもたちがどうなるのか、この目で見てみたいと思ったのです」

HILLOCK(ヒロック)初等部 校長
公立小学校で14年勤務した後、2021年3月に東京・世田谷にオルタナティブスクール、ヒロック初等部を創設、22年4月に開校。専門教科は国語。特別支援学校でのインクルーシブ教育や発達の系統性、学習心理学に関心を持ち、教鞭を執る傍ら大学院にも通い、人間発達プログラムで修士号を取得。特別支援2種免許を所有。プログラミング教育で全国的に有名な東京・小金井の前原小学校では、研究主任やICT主任を歴任するなどICTを活用した教育にも高い関心と経験を持つ。著書に『子どもが自ら学び出す!自由進度学習のはじめかた』(学陽書房)、共著に『before&afterでわかる!研究主任の仕事アップデート』(明治図書)、『知的障害特別支援学校のICTを活用した授業づくり』(ジアース教育新社)、『個別最適な学びを実現するICTの使い方』(学陽書房)などがある
(撮影:梅谷秀司)
私立小学校で教員としてのキャリアを積んだ五木田氏も、設立への思いをこう話す。
「公立小学校が98%の日本では、その土地に生まれたからという理由で6年間地元の学校に通います。わずか数%でもオルタナティブスクールという選択肢ができることで、子どもたちに『さまざまな学びの場を与えられる社会』になればいいと思いました。教育の場は本来、一人ひとりに合わせたり、失敗を含めた多様な学びができる場のはず。僕は以前、バカロレア認定校の立ち上げに携わったこともあり、授業のみならず、積極的に学びの場をつくる、という動きをする教員像があってもいいと考えたのです」

HILLOCK(ヒロック)初等部 カリキュラムディレクター
私立小学校で10年間勤務した後、2021年3月に東京・世田谷にオルタナティブスクール、ヒロック初等部を創設、22年4月に開校。教員時代はクラス担任、学年主任、ICT部主任などを兼任し、学び合いの授業実践を研究しながら子ども同士が学び合う、自分たちを表現するクラスを運営。2014年度~20年度に私立開智望小学校の設立と運営にも参画し、ICTを用いて日本語版のインターナショナルバカロレアの理論を取り入れた探究学習を推進した。シンガポール日本人学校の研修講師や、大学の特別講座なども担当している。22年に『ICT主任の仕事術 仕事を最適化し、学びを深めるコツ』(明治図書)を刊行。またICTのみならず、学校組織のアップデートを目指し、ポリシーメイキングプロジェクトを主催している
(撮影:梅谷秀司)






























