リカレント教育とは?メリット・デメリットや補助金について解説
生涯学習とリカレント教育の違い
リカレント教育も生涯学習も、「学ぶ」という点では同じですが、学ぶ「目的」が異なります。リカレント教育は、「仕事に生かす」ことが目的なのに対し、生涯学習は「より豊かな人生を送る」ことが目的とされています。
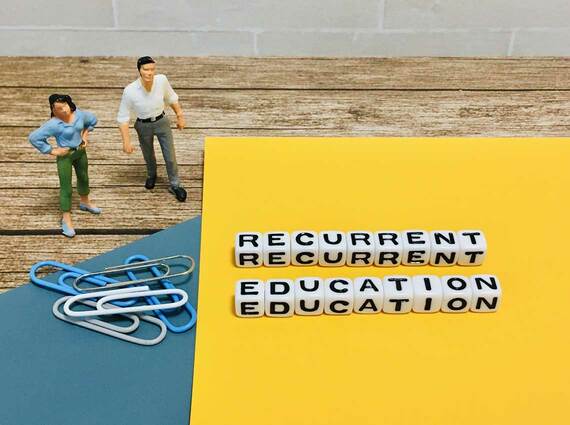
リカレント教育では、「外国語」、MBAや社会保険労務士など「資格取得系科目」、経営や法律、会計など「ビジネス系科目」、「プログラミングスキル」をはじめ、働くことを前提に仕事に生かせる知識を学びます。
一方、生涯学習では仕事に生かせる知識だけではなく、学校教育や社会教育、文化活動、スポーツ活動、ボランティア活動や趣味など「生きがい」に通じる内容も学習の対象に含まれます。
リカレント教育と大学
社会人が大学で学び直す方法として一般的なのは、リカレント教育プログラムのある大学で、自分に合う講座を探し受講すること。文部科学省事業として開設・運営しているWebサイト「マナパス」で探すことができます。
また、2015年に、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」(BP)として文部科学大臣が認定する制度が創設されました。
地方創生、医療・介護、女性活躍など毎年新たなプログラムが認定され、一部のプログラムの受講者や企業に対し、受講料などの一部が支給される制度もあります。
リカレント教育と企業・社会人
リカレント教育は、企業にとっては、導入による従業員のスキルや能力のアップにより生産性や競争力、従業員の定着率、企業価値などを高める効果が期待できます。
その一方で、導入に当たり
・ 休暇制度や評価制度の見直し
・ 教育環境やシステムの整備
などが必要なため、リカレント教育を導入している企業はまだまだ少ないのが現状です。
専門調査会「選択する未来2.0」の報告によると、2020年における企業従業員のリカレント教育実施割合は15%前後。企業のリカレント教育においては、働きながら学びの時間を確保できる仕組みづくりや、休職や退職をする場合の復職支援といった環境整備をいかに進めるかが課題です。
リカレント教育とシニア
高齢者の就業率は2004年以降上昇の一途をたどっており、2020年には65歳以上の就業率が25.1%となりました。定年以降もシニア世代を継続雇用する企業も増えています。
年齢を重ねると、体力が必要な仕事や長時間働かなくてはならない仕事を継続することが困難になりがちです。
だからこそ、シニアもリカレント教育を受け、時代に合わせた仕事のスキルを得ることが求められています。これまでに蓄積した知識や体験と関連づけたり、目の前の業務の課題解決を行ったりするための学びが有効であると考えられています。
リカレント教育と補助金
厚生労働省では、働く人の主体的な学びへの支援として給付金制度を設けています。
・教育訓練給付金
対象講座を修了した場合に、自ら負担した受講費用の20~70%の支給が受けられます。
・高等職業訓練促進給付金
ひとり親の人が看護師などの国家資格やデジタル分野の民間資格の取得のために修学する際、月10万円の支給が受けられます。居住する都道府県・市区町村で相談を受け付けています。
・キャリアコンサルティング
在職中の人を対象に、キャリア形成サポートセンターでキャリアコンサルタントに無料で今後のキャリアなどについて相談することができます。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら