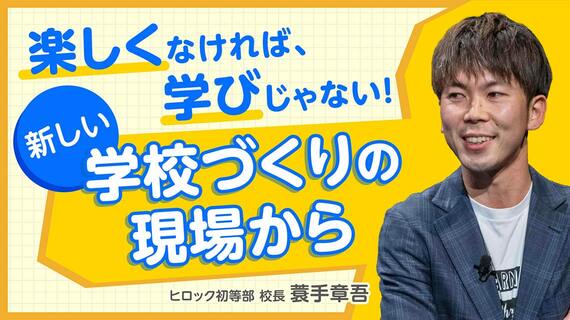子どもは大人にとって「異文化で多様性に満ちている」
大人の判断ということで言うと、例えば友達がみんなの前で話している時に、聞いていない子がいると「話している子がかわいそう!」なんて思ったりしますよね。でも意外と、話している本人に聞いてみると、全然そんなこと思っていないことが多いです。聞いてほしいわけじゃなくて、しゃべって満足、ということも。
同じように、1人でお昼を食べていても、本人はむしろそうしたいと思っていることもあるし、ちょっかいを出されたり、変なあだ名で呼ばれていても、それが友達同士のコミュニケーションの形ということもあります。大人が自分たちの文化や価値観で決めつけず、まずはちゃんと気持ちを聞くことが大切だなと思う日々です。反対に、どうってことないように思えることで深く悩んでいたり、気にしてないふりをしているだけということも。さりげなく、気にはかけつつ、手はかけすぎずを心がけています。
ヒロック初等部には「自由」という時間があります。大人からすると、さぞ遊び倒すか、ごろごろするかと想像しがちですが、子どもたちは学習したり、時間が足りなかった調べものをしたり、工作の続きをしたりと、自分のニーズに沿って有効に活用するんですよね。個々によって必要な時間は違うので、それを調整するゆとりの時間って、子どもにとっても当たり前に必要だよなぁと、改めて気づかされます。
多様性にも寛容です。外国人講師が来て、日本語でコミュニケーションが取れなくてもさほど気にしないし、障害があるといわれる子がいても自然と受け入れて、柔軟に自身や学級のあり方を変えていきます。LGBTQの授業のときも「男の人同士が好きになったり、結婚しても別にいいじゃんね?」と、大人の先入観や偏見をいともたやすく越えていきます。
こうして子どもたちと接していると、子どもというのは大人にとっての異文化で、多様性に満ちているなぁと思うと同時に、自分や社会の矛盾や偏りに気づかされます。ベストセラー本や話題のセミナー以上に、学びの場の子どもたちの姿から多くの学びを得る日々です。
「大人ももっと学ばなきゃ!」と言われるようになってきましたが、教育や子育てに関しては、目の前の子どもから直接教わることが実は何よりも大きいし、圧倒的に足りていないと痛感しています。微力ながら今後も、ヒロック初等部の子どもたちから学んだことを、特等席にいられる幸運な“翻訳家”として、今後も多くの大人文化圏の皆さんにシェアしていこうと思います。
(注記のない写真:ペイレスイメージズ1(モデル) / PIXTA)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら