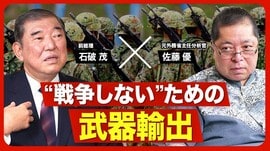「HSPの教員」が抱える悩み「職員室は刺激多い」、保護者や同僚の関係に対処法 光・音・言動に強反応、先天的に「安心」しづらい

(写真:buru / PIXTA)
HSPに対してはどのような配慮が必要なのか。みさき氏は、「HSPのすべてを理解してもらうのは難しい。でも甘えや根性論で片付けるのは時代遅れです。まずは、生まれ持った感受性の度合いは人それぞれ違いがあることを知ってほしい」と話す。また「ともさん」は、体制の工夫次第でHSPが教育現場で活躍できる場が広がると考える。
「HSPの教員は子どもの相談窓口になれると思います。小学校はクラス担任制のため、担任以外の先生がクラスを見る機会が少ない。ただ、HSP教員は悩みを抱えている子を見つけるのが得意なので、例えば複数の担任でチームを組んで役割分担をし、HSP教員は生徒のメンタルケアを担当する体制はよいかもしれません。その際は、担当業務として正式に割り当ててほしいです」(ともさん)
挫折を乗り越え、教員としての自信をのぞかせる「ともさん」。最後にHSPの教員へ、こうメッセージを送る。
「HSPの教員は全国にいますし、1つの学校にも数人いるはずです。僕がいちばんしんどかった時期は、SNSでの共感にも救われました。あなたの周りにもきっと、同じ悩みを共有できる人がいます。決して一人じゃないということを忘れずにいてください。私たちはつい、つらいのは自分が弱いからだと考えてしまいます。しかし、自分が何も変わらなくても、環境さえ変われば一気に好転することもあります。今がしんどいからといって、自分が教員に向いていないとは思わないでほしいです」
(文:末吉陽子、注記のない写真:USSIE / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら