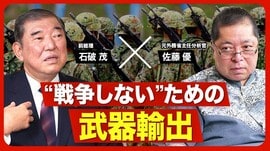「HSPの教員」が抱える悩み「職員室は刺激多い」、保護者や同僚の関係に対処法 光・音・言動に強反応、先天的に「安心」しづらい
ミラーニューロンには、他者の動作や感情を鏡(ミラー)のように自身の脳内に反映させる働きがあり、模倣や共感力にも影響する。脳神経の研究ではHSPの場合、このミラーニューロンの活性が一般より高いことがわかっており、同じ情報量でも通常より強い反応になるという。また、HSPがうつうつとしやすいことも認められている。自律神経を整える神経伝達物質である「セロトニン」を活用しにくい性質があるため、ストレス下で安心や落ち着きを得るまでに時間がかかったり、リラックスすることを難しいと感じるケースが多いのだそうだ。
HSPが持つ4つの特性と、得意分野・苦手分野
実は、HSPには物静かな人もいれば、コミュニケーション能力が高い人もいる。しかし、そのどんなタイプにも共通するとされるのが、「DOES/ドーズもしくはダズ」と呼ばれる次の4つの気質だ。
・神経の高ぶりやすさ(Overstimulated)
・感情反応や共感力が強い(Emotional Intensity)
・ささいなことを察知する(Sensory Sensitivity)
これを見て、「自分にも当てはまる」と思った人もいるかもしれない。HSPは障害や精神疾患とは異なるため医師の診断を必要とせず、セルフチェックで判断する。
「エレイン・アーロン博士のセルフテストは、信憑性があると思います。27の質問でHSPの可能性があるかどうかを知ることができますよ。HSPの日常的な感覚の例では、植物を見るだけで愛情が全身を駆け巡り、新芽が出るとまるで自分の子どもが生まれたかのようないとおしさを感じることもあるのです」(みさき氏)

(撮影:梅谷秀司)
ほかにも、叱られている人を見ると自分まで叱られている感覚になってしまい、ショックや恐怖でその場所を避けたいと感じたり、その光景が何度もフラッシュバックしたりする。また、光や音、においなどの刺激にも強く反応するため、職場のコピー機が動くと終始その音を聞き込んでしまったり、トナーのにおいが気になったりしてしまう。こうしたHSPの特性は強みにも弱みにもなりうるが、その命運を左右するのは人間関係を含む環境要因だとみさき氏は指摘する。
「環境感受性の研究によると、HSPは主観的に『自分によい影響を与える環境』では、こまやかさや予見的な面を生かして活躍することができます。ところが、主観的によくないと感じている環境においては、HSP独自の特性を発揮できなくなってしまうのです」
例えば、誤字脱字や異変の発見、リスクの提言や想定問答集の作成、人間関係の調整などは得意で、察知能力や気配りにおいて高い評価を受ける傾向にある。しかし一方で、無意識下でもつねに周囲にアンテナを張っているため、本人も気がつかないうちに疲弊していることが多いのも事実。それでも、「考えすぎじゃない?気にしすぎだよ」と言われて傷つくのを避けたい気持ちや、迷惑に思われたくないという一心で、人に悩みを打ち明けられないことがほとんどだそうだ。
「『いつも一定の水準で頑張らなければ』と自分自身のハードルを上げてしまうため、疲れたまま無理をし続けていることも。ある日突然電池が切れて、休職してしまうケースも見られます。人には調子の波がある、という点を自分も周りもよく理解しておいてほしいです」