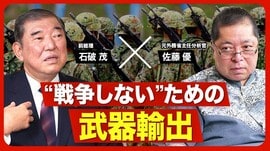「HSPの教員」が抱える悩み「職員室は刺激多い」、保護者や同僚の関係に対処法 光・音・言動に強反応、先天的に「安心」しづらい
職員室は「刺激が多い」、教員同士の人間関係にも悩み
タスクや悩みを1人で抱え込み、燃え尽きやすい傾向にあるというHSP。とくに教員は、自分の理想の教育像と現実とのギャップに苦しむことが多いとみさき氏は言う。
冒頭で紹介した「ともさん」も、繊細な性格に起因して教員同士の人間関係になじめず、一度は教職を退いた経験を持つ。もちろん児童はかわいく、長年憧れていた仕事だけにやりがいを感じていたが、神経をすり減らす出来事も多かったそうだ。
「例えば、児童同士がけんかした際に保護者から『先生の対応に問題があった』と指摘されたことがありました。自分を責めて、2カ月、3カ月と引きずってしまって……。似た状況になるとフラッシュバックして、『今回もああなるのでは』と悪い想像を広げていました。管理職も、しんどいときは相談するようにと言ってくれていましたが、つねに忙しそうな様子を見ると声をかけられませんでした」(ともさん)
新人の頃は先輩から連日「君の授業はここがいけない」とダメ出しを受けた。「今思うと、確かに力不足でした」と振り返るが、弱点や欠点を赤字で箇条書きにして渡されるなど、指導とわかっていてもやはりひどく落ち込んだという。
職員室の環境も苦痛なものだった。例えば、ある先生がその場にいない教員の悪口を話していた。しかし、いざ該当の教員が来ると何事もなかったかのように接する。こうした光景を目撃して心が冷えたという。「自分も同じように陰口をたたかれるのでは」という懸念がちらつき、同僚にも自分の悩みを打ち明けられなくなった。
そしてある時「ともさん」は、まだ人の残る職員室で説教を受ける。相手の立場が強くて同僚も止めに入れず、結局説教は2時間も続いた。そこでついに、「ともさん」は限界を迎えてしまう。ずっと志してきた仕事なのに、いとも簡単に心が折れた自分に絶望したという。
精神疾患を患って休職し、一時はどん底の生活を味わった「ともさん」。しかし、「次無理だったら、もう教員を辞める」と覚悟を決めて、教科担当制の私立小学校に再就職した。そして見事に完全復帰を果たすのだが、その理由は「自分のマインドが変わったからではなく、環境が変わったから」と「ともさん」は言う。先輩教員は「ともさん」のよい面にも着目してくれ、ミスがあっても一緒に解決してくれた。別の学校に移った現在も、保護者の言葉に傷つくことはあっても、同僚との人間関係は良好で居心地もよいそうだ。
「HSP=甘え」は間違い、精神論で片付けず理解ある社会へ
「自分が引きずるタイプなので、児童にもここぞというときでないと強く叱れません」。今も悩みは絶えないが、子どもたちの様子をよく観察するのが得意とあって、通知表の所見欄は書く内容に困らないという。日常的にもささいな変化や行動に気がつくため、「あいさつの声がいつもより大きかったね」「ゴミを拾ってくれていたね」と、発見を付箋に書いて児童のいすに貼るのが日課だ。「児童の成長を目の当たりにした瞬間は、教員をやっていてよかったと心からやりがいを感じます」。今、「ともさん」はHSPの強みを十分に発揮している。
HSP専門キャリアコンサルタントとして、教員からの相談も多数受けてきたみさき氏は、自分がHSPかもしれないと思った教員は、次のことを心がけてほしいと話す。
「大事なのは『線引き』です。児童・生徒や保護者に心ない言葉をかけられることもあるでしょう。指導の観点からその不適切な発言を追及するのも教員の役割かもしれませんし、保護者の声に寄り添いたい気持ちもあると思います。でもそれは、必ず自分の心のケアとセットで考えてください。相手の言葉を自分の中に『取り込む』のか『取り込まない』のか、自分の心を守りながらどこまでどのように接するか、その線引きをポリシーとして決めておくことが大切です。業務や担当範囲も明確に線引きして、オフの時間に良質な休養を取ることも重要です」(みさき氏)