「宿題」やめた岐阜小の校長、「学校と保護者の役割の整理を」と語る真意 狙いは「自ら学ぶ力の育成」と「働き方改革」
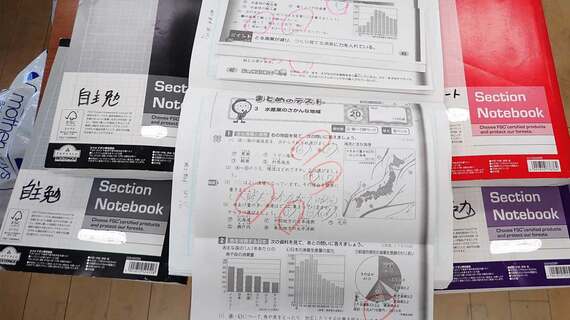
「一律の宿題」を廃止、きっかけは「教員の働き方改革」
宿題といえば、記憶の定着などのメリットが期待できる反面、「課される」という強制的な側面もあり、嫌々やるものになってしまっている場合も少なくない。
「私も子どもの頃から宿題が嫌いで、3人のわが子を育てる中でもこの学習スタイルはどうなのかなと思っていました。やらされている感覚や、宿題をやらないと叱られるという感覚を、子どもたちに持たせたくないと考えています」
そう話すのは、岐阜市立岐阜小学校校長の藤田忠久氏だ。社会が大きく変化している今、必要なのは未来を切り開いていく力であり、そのベースとなるのは自ら進んで学ぶ力だと藤田氏は考えている。
だから、児童が自ら課題を見つけて自主的に学ぶ習慣を身に付けることを目指し、今年度から「一律で課す宿題」を廃止して、児童とその保護者が主体となって進める「家庭学習」を提案した。しかし、実施に踏み切るまでには時間を要したという。

岐阜市立岐阜小学校校長
1961年岐阜県岐阜市生まれ。岐阜大学教育学部体育学科卒。1984年より岐阜県の公立小・中学校教員。岐阜市教育委員会指導主事を経て2010年度より小学校教頭。15年度より岐阜市立徹明小学校校長、17年度より統合新設校の岐阜市立徹明さくら小学校初代校長、19年度より現職。長年、体育科教育の実践や研究に尽力、県の小学校体育科研究部会長等の要職を歴任し、20年度「全国学校体育研究功労者表彰」を受ける。現任校の実践は19年度「岐阜県ふるさと教育表彰」最優秀賞、20年度「読売教育賞」社会科教育部門優秀賞、21年度「博報賞」日本文化・ふるさと共創教育部門博報賞・文部科学大臣賞を受賞
もともと宿題に疑問を持っていた藤田氏だが、実際に宿題廃止を考えるようになったのは、前任校で校長をしていた2017年ごろのこと。県の教育委員会から教員の働き方を工夫するよう指示が出たことで考えた策の1つが、担任業務の改革だった。とくに宿題の確認に割く時間は長いため、改善したいと思っていた。しかし当時は、教員にも保護者にも受け入れられるとは思えず、職員会議で「いつかはそうしたい」と提案するにとどまったという。
2019年度に現在の学校に校長として赴任し、ようやく昨年度、あるきっかけが訪れた。1年生を担任する初任者教員から「宿題を見るのに長い時間を要するため、児童と触れ合う機会がなかなか取れない」と悩む声が上がったのだ。
そこで藤田氏は、その学級の12月の懇談会に同席し、「教員が手を抜きたいわけではなく、宿題を見る時間を児童に寄り添う時間に充てたいので、家での学習は家庭にお任せしたい」と保護者に依頼。9割以上の保護者が出席していたが、意外にも反対の声は出なかったという。
赴任して3年間、全校体制での宿題廃止を表明できずにいたが、「受け入れてもらえるかもしれない」という感触を得た藤田氏。働き方改革のためにも、児童の自ら学ぶ力を育てるためにも、宿題廃止の実現を決意した。






























