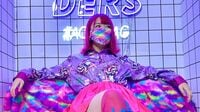奨学金サイト「ガクシー」会員増、背景に「放置されてきた2つの課題」 知られざる情報格差と業務非効率、DXで解消へ
「起業するに当たり調べてみると、米国の奨学金の種類は日本の10倍ほどあり、高等教育の授業料に占める奨学金の割合も日本は8%程度であるのに対し、米国では70%に上ることがわかりました。欧州も国の施策によって、大学の授業料が無償だったり学費が安かったりと、奨学金が必要ない場合が多い。例えば、フランスでは5~6割の学校の授業料は無償で、奨学金は企業が採用で学生を一本釣りするために提供するものくらいしかありません。一方、日本では東大の大学院生でも生活費に困り、アルバイトに時間を取られて研究に専念できないといった現状があります。こうした日本の将来を担う若者のペインを解決したいと思い、奨学金領域に特化したのです」
最大の課題は「情報の非対称性」と「運営現場の非効率性」
松原氏は、日本の奨学金の最大の課題は「情報の非対称性」と「運営現場の非効率性」だと考えている。「学費というテーマは誰もが通る道なのに、なぜか奨学金運営の現場ではこの2つの問題が長年放置されてきました。私たちはこれらをDX化によって解決したいと思っています」と語る。
今、多くの高校生や大学生は、奨学金情報を学校経由で受け取っている。しかし、その中身はJASSOの奨学金の案内がメインであり、企業や財団、自治体などが運営する奨学金情報は学生たちに十分に届いていない。地域や学校によっても受け取れる情報の質や量に差があり、奨学金を必要としている人に適切な情報や支援が届きにくいという現状があるという。この「情報の非対称性」を解決すべく、同社は奨学金サイトを作ったというわけだ。
また、同社の調査によると、奨学金の運営元の8割以上が、募集を郵送や窓口で受け付けており、その管理を紙とExcelで行っているという。このアナログな「運営現場の非効率性」を解消しようと提供を始めたのが、ガクシーAgentである。

「奨学金の応募者と運営元の支援を両輪で行い、将来的には就職支援サービス『リクナビ』の奨学金版のようなプラットフォームにしていきたい」と、松原氏。とくにガクシーAgentの導入が広がれば、運営元の業務が楽になるのはもちろん、学生も簡単にガクシーの中で複数の奨学金の応募や管理ができるようになり、双方の負担軽減が期待できる。
「大学に負荷が集中している点も大きな課題。JASSO関連の業務量が多く、大学は書類作成に追われています。ここを効率化する機能を9月にリリースしましたが、提案時から40~50件の相談依頼が入るなど反響が大きかったですね。それだけ学校の奨学金担当者の方々は事務業務を回すのに精いっぱいなんです。担当者の皆様が学生に『こんな奨学金があるよ』とフォローしてあげるような本来のお仕事に注力できるよう、今後も機能を向上させたいと思います」(松原氏)
若者がお金の心配なく挑戦できる「諦めなくていい社会」へ
松原氏は、給付型奨学金が一般的な海外と異なり、JASSOの奨学金の大半は返済が必要な貸与型である点も問題だと指摘する。実際、雇用の不安定化や学費の高騰などを背景に返済できないケースが増えており、厳しい取り立てなども社会問題化している。一方で、明るい動きもある。
「私たちの調査では、2015年ごろの日本の給付型奨学金は全体で100億円程度だったのですが、現在までに3000億円程度まで増えており、その8割ほどをJASSOが担っていることがわかっています。JASSOが17年度から返済義務のない給付型奨学金事業を始めているためです。背景には貸与型の社会問題化もありますが、国にはとくに博士や修士など優秀な人材を育成して国力を上げたいとの意図があるのでしょう。また最近のスタートアップ業界では、メルカリCEOの山田進太郎さんのように、ビジネスで一定の成功を収めた創業者などが後進のために財団を設立して奨学金制度を開始するような動きも増えてきています。こうした流れが続くのは望ましいことです」