練馬区の小学校12校、教員延べ約100名参加、「脱校内」研修の気になる中身 石神井台小をハブに教員同士が学ぶ場を創出
最後は、「練馬の魅力発信スライドを作ろう」をテーマに、テーブルごとに「練馬区の魅力」「とくに伝えたいこと」「スライド内容」についてホワイトボードに書きながらアイデアを出し合った。
「練馬といえば、緑とアニメの街」
「ブルーベリーもよく知られているよね」
「練馬の大根を使った練馬スパゲティのおいしさを伝えたい」
など学校の垣根を超えて、同じ地域の教員同士のにぎやかな対話が続いた。

横山氏は最後に、「私たちは、体に体力があるように、心にも『体力のようなもの』があります。心の体力を温めるには、日常のコミュニケーションが大切です。今日の体験を、職場や教室で一人ひとりの力が発揮されるような組織の運営や学びの場づくりにつなげていただければと思います」と呼びかけた。
温かな雰囲気の中、時には真剣に、時には楽しく学び合う教員たちの生き生きした姿が印象的だった。
自校以外の教員も「共に学ぶ」校内研修で新しい視点や気づきを
「夏の学びWeeeek! in2022」第2回は、調布市立多摩川小学校教諭の庄子寛之氏による「働き方を変えるマインドチェンジ」、第3回は環境活動家の露木志奈氏を講師に「Z世代に学ぶ環境問題の今」、最終回は、オオタヴィン監督を招いて映画『夢みる小学校』の上映会が行われた。
トータルで、区内の小学校12校、教員延べ約100名が参加したこの研修会を企画したのが、練馬区立石神井台小学校で研究主任を務める二川佳祐氏だ。
「校内研修は、文字どおり校内で行うのがセオリーですが、かねて『校内だけで閉じてしまっていいものだろうか』という課題感が自身の中にありました。前任校で研究発表会を担当した際、“外に開く”ことは、準備などを含めて確かに大変だけれども、新しい刺激を受けたり、自分のよい点や足りない点に気づき『もっと成長したい』という思いが強くなった経験があります。校内研修も、自校の先生だけではなく外部の方も招き入れ、共に学ぶことで、新しい視点や気づきが生まれるのではないかと思いました」

練馬区立石神井台小学校 主任教諭
今年度より同校の研究主任となった二川氏は、22年5月、熊本大学大学院特任教授の前田康裕氏を講師に、「GIGAスクール構想下での新しい学びとは」をテーマにZoomによる校内研修を企画。
「『当校だけの学びにするのはもったいない』と、この講演を練馬区内の教職員の皆さんと共有しようと動いたところ、さまざまな公的手続きが必要であることがわかりました。段取りの面で管理職の先生の手を煩わせてしまったのですが、何とか開催することができ、校内のみならず区内の教員の皆さんから大きな反響をいただきました。手続き面での反省点を生かしつつ、新たに企画したのが今回の『夏の学びWeeeek! in2022』です」
学校での仕事以外に、地域の大人が学びを通してつながるコミュニティーを立ち上げ、教育、家族、環境問題、街づくりなどをテーマとしたイベントを開催するなど、学校の“外”にも世界を広げ、発信を続けてきた二川氏。
「さまざまな催しを企画・運営してきた中で気づいたのが、『先生たちの学ぶ意欲がいちばん高いのは、現場の感覚が残る一方で何らかの課題も抱えがちな夏休みの初め』ということ。この時期に、『学ぶことは楽しい』と思えるような研修会を開催したいと、各方面で活躍しているすてきな方々をゲストティーチャーとしてお招きしました。 公教育の当たり前を取り払い、“いいものは広げ、みんなで分け合う”。こんな校内研修があってもいいのではないかと思います。今後は、保護者の方も参加できる研修会や区内の小中連携に加え、区外の学校と研究のシェアを行う会なども企画していきたいですね」

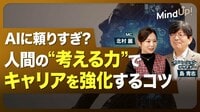


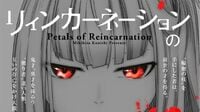


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら