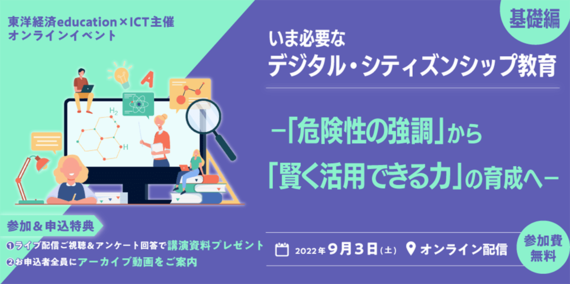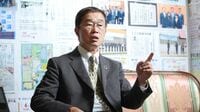世界に後れを取る「メディア情報リテラシー教育」今始めないとマズい訳 求められるデジタル・シティズンシップの視点
だ(誰):この情報は誰が発信したか?
い(いつ):いつ発信されたのか?
じ(事実):事実の根拠や参照はあるか?
か(関係):自分とどのように関係するか?
な(なぜ):情報発信の目的は何か?
このほか、インターネットを使って元の情報の社会的評価を調べる「横読み」なども情報源の真偽の検証に有効だというが、いずれも前提としては「探究学習で1人1台端末を使うことが重要」だと坂本氏は語る。そうすれば、子どもたちは調べものをする際にインターネットからも情報を収集し、思考を深めていくことになる。いわば日々の探究学習の活動そのものが、メディア情報リテラシーを絶え間なく鍛える場になりうるのだ。
「さらに言うと、探究学習を重視する新学習指導要領の土台はESD(持続可能な社会の創り手を育む教育)です。ESDもメディア情報リテラシー教育もユネスコ主導で推進されてきた教育で、これらの概念はデジタル・シティズンシップとも親和性が高い。ですから学校現場は、学習指導要領が求めるように、持続可能な社会の創り手を育むことを目指し、探究学習を軸に学校全体でカリキュラムマネジメント(以下、カリマネ)をいかに行っていけるかが、メディア情報リテラシー教育のカギになります」
とはいえ、どうカリマネを行えばよいのかまだ道筋が見えていない学校もあるだろう。そんな学校は、地域連携に着目するとよいと坂本氏はアドバイスする。
「日頃意識していないだけで、地域に根付いた教育はどこの学校もやっていますよね。その活動をESDの枠組みで捉え直せばカリマネはできます。そこにGIGA端末を持ち込むイメージで取り組めば、デジタル・シティズンシップやメディア情報リテラシーが重要であることがわかると思います。そうすると、探究学習も生きてきて、社会課題に対して自分は何ができるのかという学びにシームレスにつながっていくはず。最終的には学校の成果も発信できるでしょう」
また、司書教諭の専任化など、司書教諭や学校司書の充実を図ることも必要だという。司書たちが情報の専門家として、情報源の評価の方法をしっかり子どもたちに教える役割を担うのだ。「教員の多忙化が問題となっている状況からも、司書の専門性を高めることで対応するのが現実的ですし、これにより質の高いメディア情報リテラシー教育が期待できます」と、坂本氏は言う。
すでに大阪府吹田市や岐阜県岐阜市、鳥取県、愛媛県四国中央市、埼玉県の戸田市や久喜市、長野県の一部自治体など、デジタル・シティズンシップ教育に舵を切る教育委員会もある。今後は、こうした先進的な自治体と、情報モラル教育にとどまっている自治体との間でメディア情報リテラシーの格差が広がっていくことが考えられる。
「メディア情報リテラシー教育の大切さを理解されている先生方も増えてきていると感じます。ところが教育委員会や学校長の理解が進んでいないために、苦しんでいる先生方も多い。そうした先生方は、少なくとも自分が授業で情報を扱うときには『一歩立ち止まって考える』という視点を意識し、『だいじかな』や『さぎしかな』のリストを取り入れてみてほしい。これをやるだけでも、子どもたちにもたらす効果は大きく違ってきます」
(文:長谷川敦、注記のない写真:TATSU/PIXTA)
東洋経済education×ICT主催で坂本氏が登壇するイベントを開催します。詳しくは↓↓↓
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら