教育専門家10人が、学校関係者のために厳選「GWに読みたい」お薦めの本 個別最適な学び、哲学、部活動、学校改革など
中でも「近年、『哲学対話』が学校でも少しずつ実践されるようになっている」(苫野氏)と言うが、1960年代以降に世界各地の教育現場に広がった哲学対話は、日本でもアクティブラーニングの1つとして注目を集めている。
授業で「哲学対話」を行うとなると、ハードルが高いように感じる先生もいるかもしれないが、そこでお薦めしたいのが『哲学は対話する:プラトン、フッサールの〈共通了解をつくる方法〉』(著:西 研/筑摩書房)だという。
「さまざまなスタイルが提唱されている哲学対話だが、本書が重視するのは『共通了解』を見いだし合う対話。昨今の世界情勢を見ても痛烈に感じるように、互いに価値観や考えの異なる私たちは、共に生きるためには何とかして共通了解を作り合う必要がある。『人それぞれ』では済まされない場合は多々あるのだ。哲学は、そのための思考の宝庫。ぜひ、多くの教育関係者の間で、この英知が共有されてほしいと思う」
こちらは、「多くの市民が哲学の対話に参加し、それを楽しんでもらえるようになってほしい」と話す哲学者・西研氏の著書。ものごとの「よさ」について「なぜよいのか」「どういう点でよいのか」を問うことで一人ひとりの生き方と、社会のあり方とを「よりよき」ものにしようと配慮することが哲学の目的と説く。プラトンやフッサールの哲学を押さえつつも現在の対話に生かす方法が学べる1冊だ。
7. 『そろそろ、部活のこれからを話しませんか』(著:中澤篤史)

名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授
(写真:内田氏提供)
一方、学校現場において早急に解決すべき課題として「教員の働き方改革」がある。急務とされながらも、なかなか進まない教員の働き方の改善を図るうえで今、期待が寄せられているのが部活動改革だ。
部活動の運営が教員の残業を前提としていたり、全員顧問制によって競技経験のないスポーツの顧問を担当しなければならなかったり、その指導が教員の大きな負担となっている。だが、「子どもたちのために教員は身を削ってでも頑張るべき」という意識や文化をいよいよ見直すべきときに来ているのではないだろうか。
そんな中、教員の働き方改革や部活動負担の問題などに詳しい名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授の内田良氏が選んだのは、『そろそろ、部活のこれからを話しませんか 未来のための部活講義』(著:中澤篤史/大月書店)だ。
「『部活博士』と呼ぶべき部活動研究のトップランナーが、その研究の成果を、実に平易な言葉と統計によって提示してくれている。生徒の負荷や事故から教師の長時間労働まで、また、部活動の過熱の歴史から今日的な課題さらには近未来の活動のあり方まで、重要なトピックが幅広くカバーされている。海外の事例もまた、日本的部活動の『当たり前』を、効果的に揺さぶってくれる。部活動のすべてを、1冊でわかりやすく教えてくれる良書だ」
「部活は楽しい」「部活を指導してこそ一人前」など、学校の当たり前を壊すのには時間がかかる。だが内田氏自身、「部活がしんどい」「部活やめたい」という教員の声に向き合いながら徐々に部活動改革のうねりを広げてきた。実際、文部科学省をはじめスポーツ庁や文化庁で部活動のあり方を見直す議論が始まっている。
子どもはもちろん、教員も含めて元気で笑顔に集える学校空間にするには、部活動改革は避けて通れない道といえるのではないだろうか。
8. 『心が元気になる学校』(著:副島賢和)
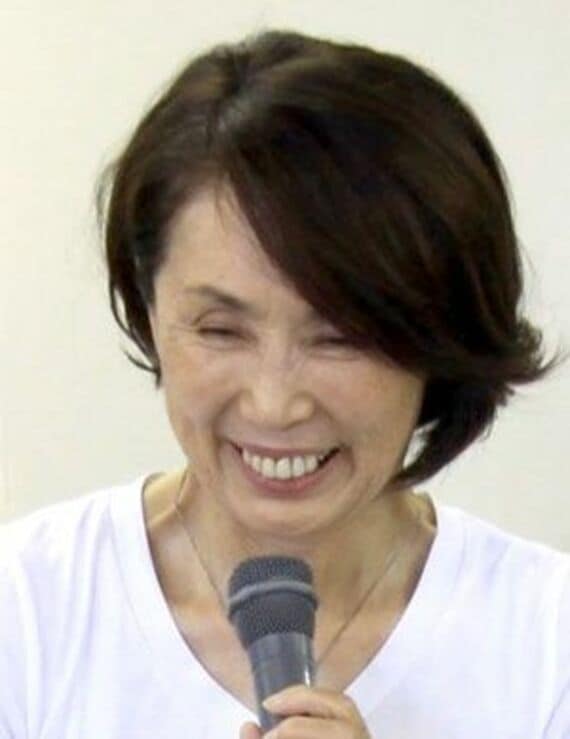
大阪市立大空小学校 初代校長
(写真:木村氏提供)
「大人は子どもが安心できる環境をつくるだけでいい」と話すのは、大阪市立大空小学校 初代校長の木村泰子氏だ。木村氏は同校で「不登校ゼロ」を目指し、特別支援教育の対象となる子どももそうでない子どもも、共に学び合う教育体制を敷いたことで知られている。
当時の経験から得たものを、教員を引退した現在も精力的に発信し続ける木村氏は、大人の一言が「子どもが言いたいことを言えない」関係をつくると話す。
子どもに言うことを聞かせるのではなく「聞く」「受け止める」姿勢が必要だと。何を聞いても「別に」「うるさい」「わからない」と言うような子は、しつこく追いかけないのもコツだという。そんな子どもの本音、気持ちを読み解く達人ともいうべき木村氏がお薦めするのが、『心が元気になる学校 ―院内学級の子供たちが綴った命のメッセージ』(著:副島賢和/プレジデント社)だ。
「院内学級の子どもたちがつづった命のメッセージです。著者の副島賢和さんは『大丈夫だよ』という言葉の裏側にある意味。『別に』という言葉に隠された本当の気持ち。『何でもないよ』という言葉が発しているSOS。これらを入院中の子どもたちから学ばれました。子どもたちのどんな感情も大切にしてくれる大人が、あなたの周りにもきっといるからと本書は締めくくられています。先生たちや子どもの周りの大人たちにぜひ読んでいただきたい1冊です」

































