教育専門家10人が、学校関係者のために厳選「GWに読みたい」お薦めの本 個別最適な学び、哲学、部活動、学校改革など
「この本には、『統計』は何のために必要なのか、『統計』を扱う際には何に気をつければよいのかが数式を使わずに平易に書いてある。『統計』が大切なことはわかっているが数学は苦手という人が、『統計』について何となく理解するにはよい本である。私は、基礎から始めて早々に挫折するより、何となく理解してから興味・関心を持った分野を順に深めていくほうが合理的であると思う。数学の苦手な人の統計分野の最初の1冊として適切ではないかと思います」
14年にビジネス書大賞、17年に日本統計学会出版賞を受賞した統計学の入門書ともいうべき本書は、統計家である西内啓氏が最新の事例と研究結果を基に、基礎知識と統計学の主要6分野を横断的に解説している。
4. 『ケーガン協同学習入門』(著:スペンサー・ケーガン)
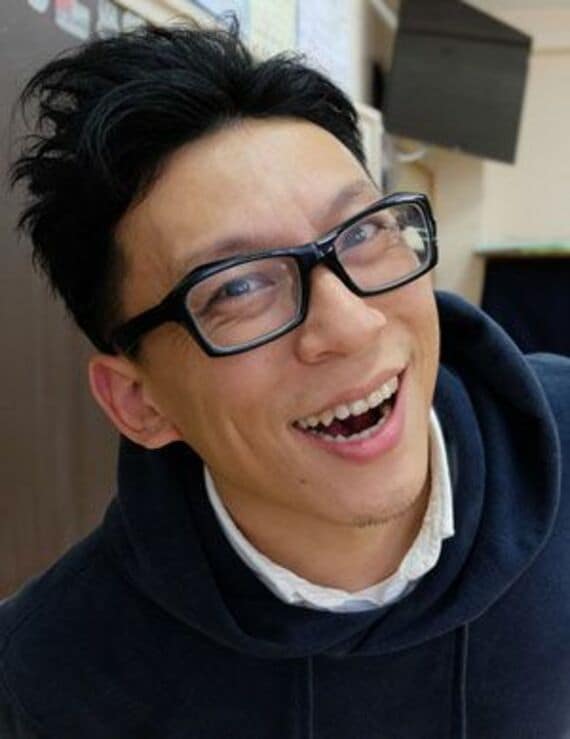
フリーランスティーチャー
(写真:田中氏提供)
今回の選書には、現職の先生にも協力いただいた。フリーランスティーチャーとして活躍する田中光夫氏がお薦めするのは、『ケーガン協同学習入門』(著:スペンサー・ケーガン/大学図書出版)だ。
田中氏は、10年ほど前に日本協同教育学会(JASCE)主催の認定ワークショップに参加したことを機に、協同学習の理論や実践を学んでいる。文部科学省が学習指導要領で示す「協働学習」は、子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学びで、グループで課題解決に取り組む学習だ。
一方、「協同学習」もペアやグループで学習するものの、仲間と一緒に活動するうえでの目的などに明確な定義があるのが特徴だという。
「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の一体的な充実によって『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善を、と提言した文科省。2030年以降の社会を生きる・つくるうえで求められる力、『多様性の尊重』『持続可能な社会』『共生社会』を実現するためには『協働』が欠かせません。それらについて学ぶために重要なのが『協同の理念』と考えます。『協働と協同の違いって?』『具体的な手段とは?』が学べる一書です」
米国では19世紀ごろから協同学習が活用されていて、その技法の多くは本書の著者であるスペンサー・ケーガン博士によって紹介されている。協同学習のエッセンスを簡潔にまとめた入門書の全訳で、ぜひ田中氏の実践をまとめた「子どもが自ら学び出す「協同学習」超重要な4前提」と一緒にお読みいただきたい。
5. 『教師のための教育効果を高めるマインドフレーム』(著:ジョン・ハッティら)

HILLOCK(ヒロック)初等部 校長
(写真:蓑手氏提供)
昨年、公立小学校を辞め、今年4月にオルタナティブスクールのヒロックを東京・世田谷に開校、校長を務める蓑手章吾氏がお薦めするのは、『教師のための教育効果を高めるマインドフレーム:可視化された授業づくりの10の秘訣』(著:ジョン・ハッティ、クラウス・チィーラー/北大路書房)だ。
情報教育、ネットリテラシー教育、SDGs教育、キャリア教育など――。学校では教科の指導とは別に、社会の変化に応じて生じるさまざまな課題に対応する教育が求められている。まさにこれからの社会を生きる子どもたちに必要な教育である一方、ただでさえ忙しい学校現場でどのように取り入れていくべきかについては課題が多いといわざるをえない。
ICTを活用した教育に実践的な経験を持つほか、特別支援学校でのインクルーシブ教育や発達の系統性、学習心理学にも関心を持つ蓑手氏は、子どもたち目線での学びのあり方や教師の役割について問い直す。
「学校現場では『やらなければいけないこと』が次から次へと押し寄せてきます。しかし、大切なのは『なぜそれをやるのか』であり『どんな子どもを育てたいのか』です。この書籍には、教育現場での長年にわたる膨大な調査データによって解明されてきた最先端の学習科学と、教師のあり方や学ぶべきことが書かれています。教師が目的を明確にし、根性や努力や我慢以外の方法を子どもたちに提示できる。そんな教師でありたいですよね」
本書では、学習を成功へと導く授業を行うために、教師は自身の指導と役割をどう考えるべきか、熟練教師の実践知とメタ分析によるエビデンスを示しながら10の「心的枠組み」を提示している。子どもたちと日々向き合う、教師が抱えるリアルな悩みに寄り添う1冊といえそうだ。
6. 『哲学は対話する』(著:西 研)

哲学者、教育学者
熊本大学教育学部准教授
(写真:苫野氏提供)
さまざまな新しい教育が学校で始まる中、道徳が小学校で2018年度、中学校で19年度に教科化されたことも大きな話題となった。そんな中、哲学者で教育学者の苫野一徳氏は、「道徳教育は本来学校でやるべきではない」と話す。
代わりに道徳科でやるべきなのは「市民教育」と訴える苫野氏が、その実践方法として提案するのが「哲学対話」「学校・ルールを作り合う道徳教育」「プロジェクトとしての道徳教育」の3本柱だ。

































