東京都の水辺再開発に強い関心を寄せているのが、江戸時代から営々と続いてきた屋形船業界だ。舟運活性化に何が足りないのかを聞いた。

活性化に「物理的な制約」
――日本橋川、神田川界隈で水辺の再開発が進んでいます。再開発によって東京の舟運は活性化すると思いますか。
日本橋川は船が航行するには難しい。僕も船を壊しながら20年間、1000万円の損を出して勉強したが、(日本橋川の)橋梁は高さがまず低い。日本橋の上流に一石橋があって、これが特に低い。大きな屋形船がここから上流にいくのは難しいだろう。
三菱地所によって大手町の鎌倉橋付近が再開発され、桟橋も設置される予定だが、航行できる船は限られる。
神田川では逆に干潮時に浅くなり、プロペラ(スクリュー)で動く船の航行が難しい。特にネックになるのが万世橋付近だ。万世橋は地下鉄銀座線の旧万世橋駅が地下にあって、橋の下にトンネルが走っている。ここの川底が浅くなっている。





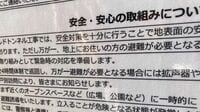



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら