目的のためなら敵さえ優遇 「映画の力」を信じた独裁者
評者/法政大学名誉教授 川成 洋

[Profile] Bill Niven 英ノッティンガム・トレント大学のドイツ現代史の教授。研究領域はナチズム、ヒトラー、第三帝国の記憶、東ドイツの歴史と記憶、現代ドイツ、20世紀ドイツの映画と文学など。本書(原著は2018年刊行)が本邦初訳。
第1次世界大戦で完敗したドイツは、天文学的な額の賠償金支払い、海外領土の放棄などを含むベルサイユ条約を受諾した。こうした恥辱に終止符を打つためのメッセージを、拡声器のごとく放ったのがヒトラー。本書は彼が映画をいかに利用したかを明らかにしている。

1933年の政権掌握以来、彼は官邸と自邸の大広間にホームシアターを備え、ほぼ毎晩餐後、2〜3時間、映画を鑑賞する「映画中毒」だった。そこには、ユダヤ人、ロシア人、米国人が制作した映画までもが含まれていた。「映画は世界を変える力がある」と固く信じていたヒトラーは、映画制作・公開などの実務はゲッベルス宣伝大臣に委ねたが、その最終的決定権は自分が握った。第2次大戦前、ヒトラーは自身が登場する週間ニュース映画の上演館に姿を現し、その映画館を興奮のるつぼと化すこともしばしばだった。
芸術的なプロパガンダ映画を望んでいたヒトラーは、33年のナチス党大会の記録映画の監督を31歳のレニ・リーフェンシュタールに託した。その出来栄えに満足し、34年、35年の党大会、さらに36年のベルリン・オリンピックの記録映画『オリンピア』も任せ、彼女も負託に応えた。『オリンピア』は、ナチズムの負の性格、つまり欧州征服の野望や人種的偏見などを隠蔽し、ヒトラーを完璧に洗練された温和な人物として描き、ナチズムとヒトラーに関する心地よい神話を創り上げた。






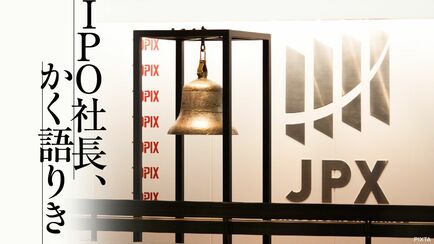






















無料会員登録はこちら
ログインはこちら