
前号に引き続き、上司が仕事をしない、あるいは能力がない場合について述べる。意外と面倒なのは、上司が仕事をあえてサボタージュしているときだ。部下からは、やるべき仕事を十分に行っていない、あるいはまったく行っていないように見える。しかし、上司は「こんなことはやっても意味がない。そう遠くない将来に軌道修正がなされる」ということをわかっているので、あえて手を抜いているのだ。
こういう上司は将来、出世する。なぜなら、組織の方針に「間違っています」とあえて異議を唱えて疎まれることがない。部下にも無理をさせない。したがって、部下から恨まれることもない。
1988年6月に筆者は、モスクワの日本大使館で勤務を始めた。当時は、ゴルバチョフ・ソ連共産党書記長が熱心に反アルコールキャンペーン(節酒運動)を展開していた。レストランでも午後5時までは酒類が提供されなくなった。酒販店も午後3時まで、アルコール飲料を販売しなくなった。


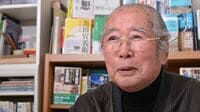




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら