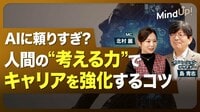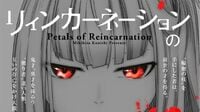顧問強制しない米国に学ぶ「部活動改革」のヒント 対価や専門管理職で公平さや負担軽減を図る
また、民間委託や地域移行、地域との連携については、学校運動部、民間、地域、家庭の守備範囲をわかりやすくするべきだと思う。子どもたちのオーバーユースや燃え尽きを防ぐ必要があるからだ。
スポーツ庁は2018年に「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を作り、スポーツ医科学の観点も踏まえて、週2日以上の休養日の設定、平日は1日2時間程度の活動、学校の休業日は1日3時間程度の活動を推奨している。学校と地域との連携でも、このガイドラインに沿った活動量であるべきだろう。
しかし、ガイドラインから逃れて運動部活動をする「闇部活」を防ぎながら、地域と連携することは意外と難しいかもしれない。とくに学校と地域の民間業者が連携して運動部活動を行う場合である。文部科学省や学校が「平日に学習塾で子どもが勉強できるのは2時間まで」などと強制できないように、民間が担う運動部の活動内容に学校がとやかく言うことはできないかもしれない。過度な介入は、民業を圧迫するだけでなく、子どもの自由時間の使い方を校則で縛ることにもなる。
また、学校運動部を地域移行するなどして縮小した場合、学校外でのスポーツ活動と掛け持ちする子どもが増えることも予想される。シーズン制を敷く米国でも、オフシーズンに学校外のチームにも所属していることでスポーツ活動に時間を割きすぎているケースがあるため、日本も子どもの活動量をしっかり見守りたい。そこは保護者の仕事になってくるだろう。活動量だけではなく、地域部活動の指導者の不適切な言動があった場合には、誰が窓口となってその調査や改善に当たるのかも、保護者と子どもは知っている必要がある。
こういったことから、地域との連携においては、学校と地域や民間の守備範囲を保護者にもわかりやすく周知されるべきだろう。
これからは、日本でも、教員以外の大人が運動部指導に関わることになるため、学校運動部の理念を各学校で改めてはっきりさせて共有する必要がある。そして、部活動指導を引き受ける教員とそうでない教員、また、教員と外部からの指導者の働きに対し、公平に報いるシステムづくりと、その運営管理が求められるのではないだろうか。
(注記のない写真:m.Taira/PIXTA)
執筆:谷口輝世子
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら